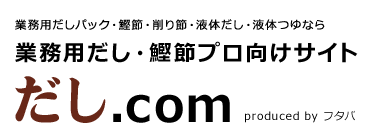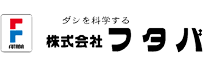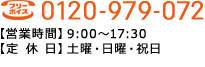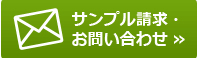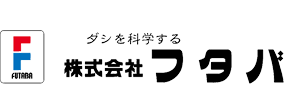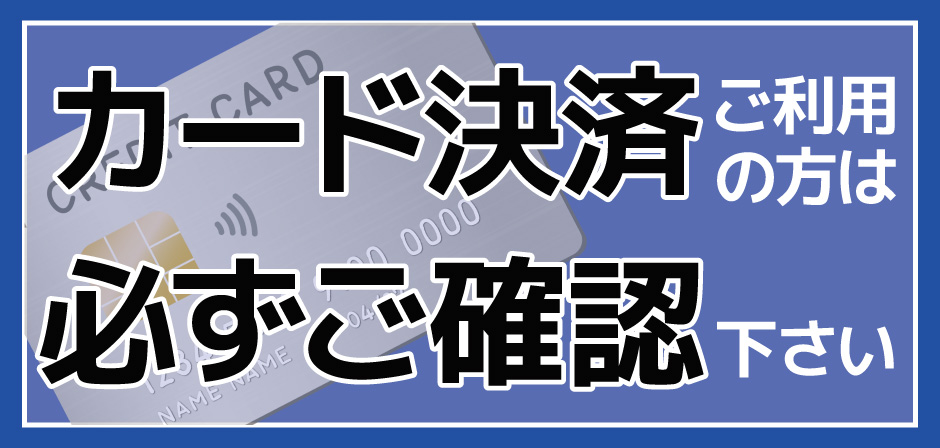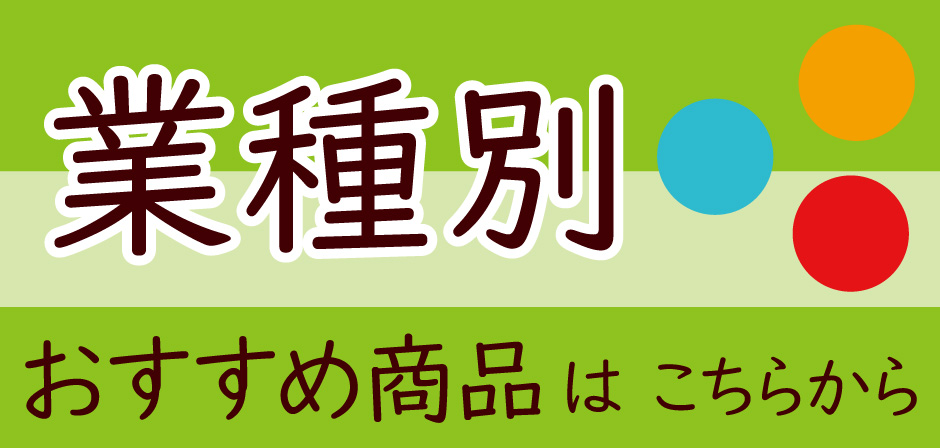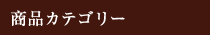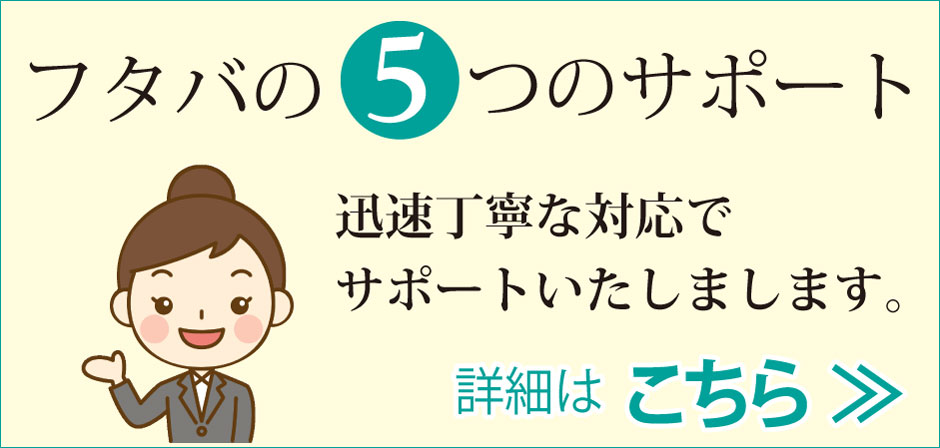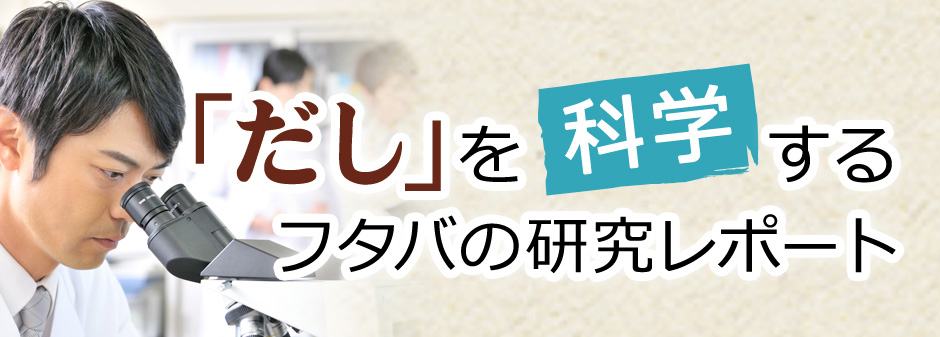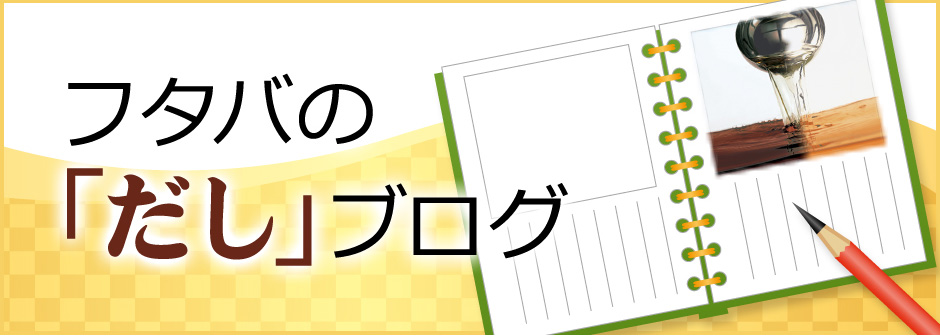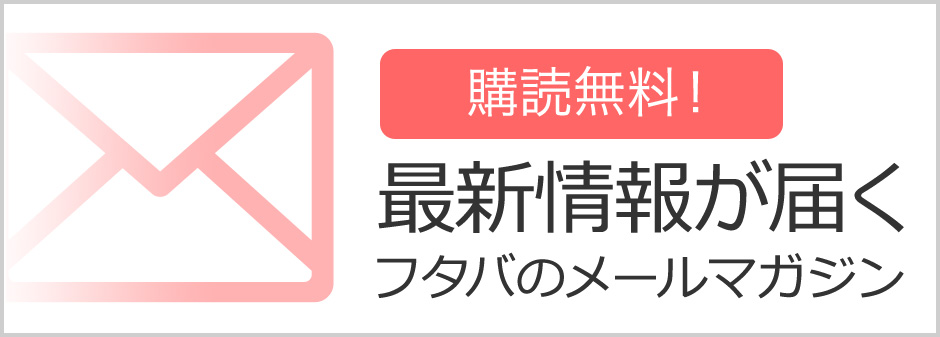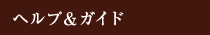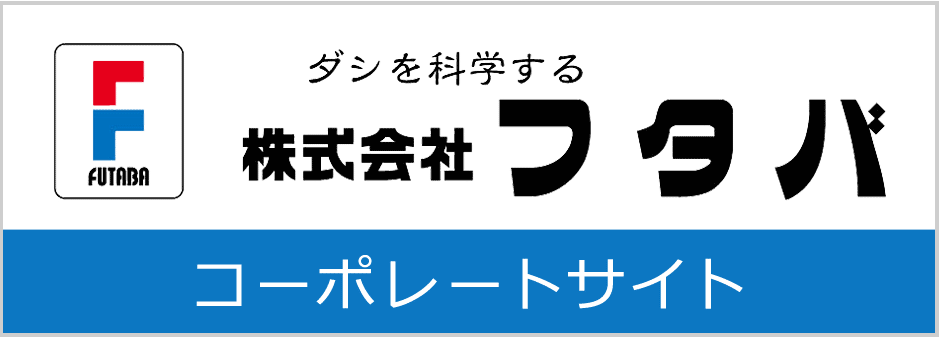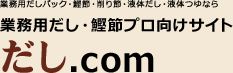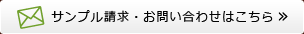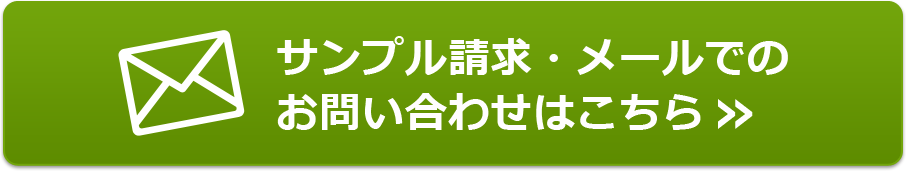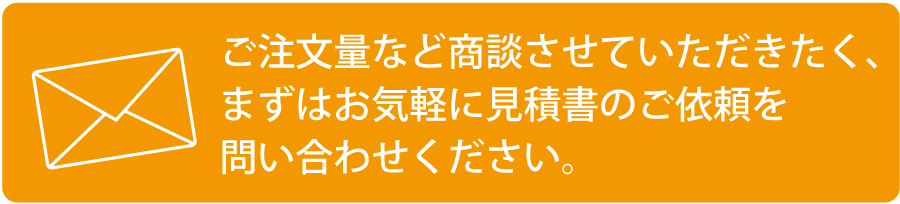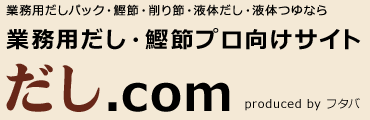「うま味」この言葉から、あなたはどのようなイメージを思い浮かべますか。
和食の繊細な風味でしょうか。
それとも、単なる「美味しい」という感覚の一種でしょうか。
実はこの「うま味」、世界中で人気を博している、奥深い魅力を持つ味覚なのです。
その人気の背景には、科学的な根拠や文化的な要素、そして私たちの進化の歴史までが深く関わっています。
そこで今回は、「うま味」の世界的な人気とその理由を、多角的に探っていきます。
うま味の世界的人気と背景
うま味の科学的魅力とは
「うま味」は、甘味、酸味、塩味、苦味に続く第五の基本味として知られています。
100年ほど前に日本の化学者、池田菊苗博士によって発見されたこの味は、グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸といったうま味物質によって生み出されます。
これらの物質は、タンパク質の摂取を感知するシグナルとして、私たちの脳に「これは栄養価の高い食べ物だ」という情報を伝えます。
つまり、うま味を感じるということは、私たちの生存本能と深く結びついていると言えるでしょう。
さらに、これらのうま味物質を組み合わせることで、相乗効果によってより強い「うま味」を感じることができることも、その魅力の一つです。
昆布と鰹節の出汁が、まさにその好例と言えるでしょう。
食文化への浸透と影響
うま味は、単なる味覚にとどまりません。
それは、世界の食文化に深く根付いた、重要な要素となっています。
和食では、古くから出汁が料理のベースとして用いられ、素材のうま味を引き出す技術が高度に発達してきました。
出汁は、昆布や鰹節などを煮出して抽出する、シンプルながらも奥深い技法です。
一方、西洋料理ではスープストック、中国料理では白湯などが、同様の役割を果たしています。
それぞれの文化圏において、独自の食材や調理法を用いながら、うま味を最大限に活かす工夫が凝らされています。
うま味を意識した調理は、塩分を減らしつつも、深い味わいを生み出すことができるため、健康志向の高まりにも合致しています。

うま味人気拡大の要因分析
グローバル化と食の多様化
近年、世界的なグローバル化によって、食文化の交流が加速しています。
さまざまな国の料理が容易に手に入るようになり、人々は新たな味覚を求めるようになりました。
その中で、「うま味」は、他の基本味とは異なる、独特の深みと複雑さで、世界中の食卓を魅了しています。
特に、和食の世界遺産登録を契機に、「うま味」を含む和食への関心は飛躍的に高まりました。
健康志向の高まりと関わり
健康志向の高まりも、「うま味」人気拡大の大きな要因となっています。
うま味物質は、カロリーが低いにも関わらず、深い満足感を与えてくれます。
そのため、健康を意識しながらも、食事を楽しむことができるという点で、多くの人々から支持されています。
また、うま味を活かした調理法は、塩分を抑えたり、油脂の使用量を減らしたりすることも可能にするため、健康的な食生活を送りたいと願う人々にとって、理想的な選択肢となっています。
さらに、うま味成分は、古くから生命維持に不可欠な必須アミノ酸を含むタンパク質の摂取を促す役割を果たしてきたとされています。

まとめ
「うま味」の世界的な人気は、その科学的な魅力、食文化への浸透、そしてグローバル化や健康志向の高まりといった複数の要因が複雑に絡み合った結果です。
それは、単なる「美味しい」という感覚を超え、私たちの生存本能や文化、そして健康的な食生活にも深く関わる、普遍的な味覚と言えるでしょう。
「うま味」の探求は、これからも食文化の新たな可能性を切り開いていくでしょう。
また、ヴィーガン認定された昆布を使い動物性原料を一切使用していない出汁もあり、幅広い人が利用できるようになってきています。
私たちは、この奥深い味覚を通して、食の喜びをさらに深く味わうことができるのです。