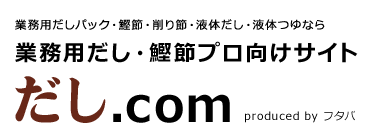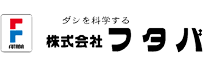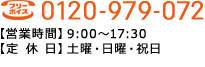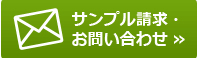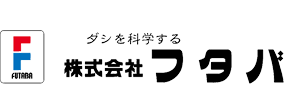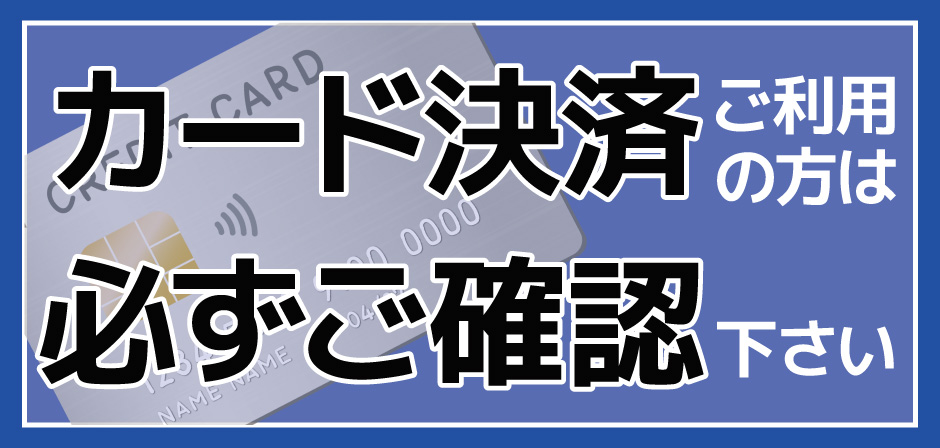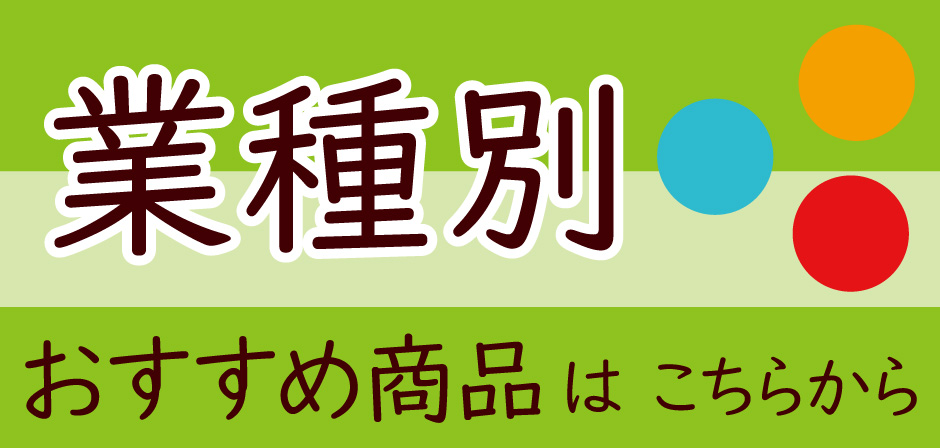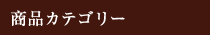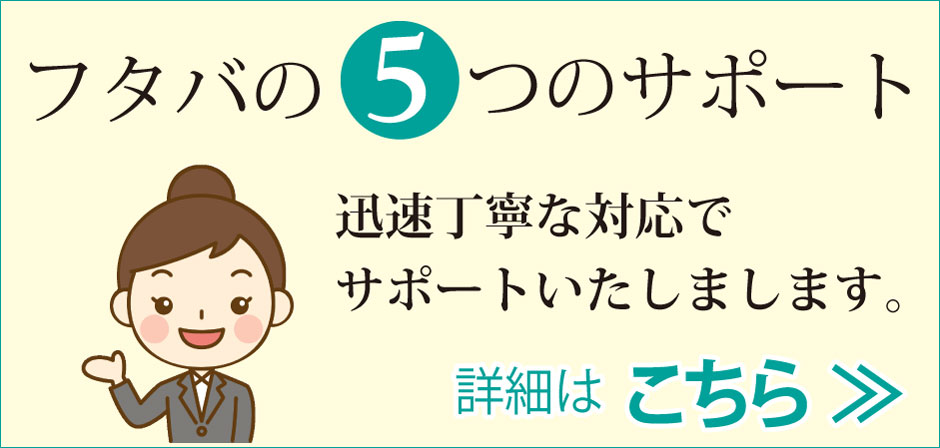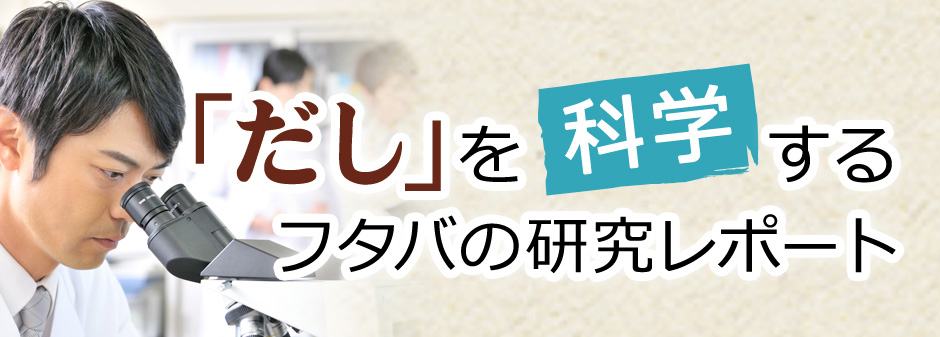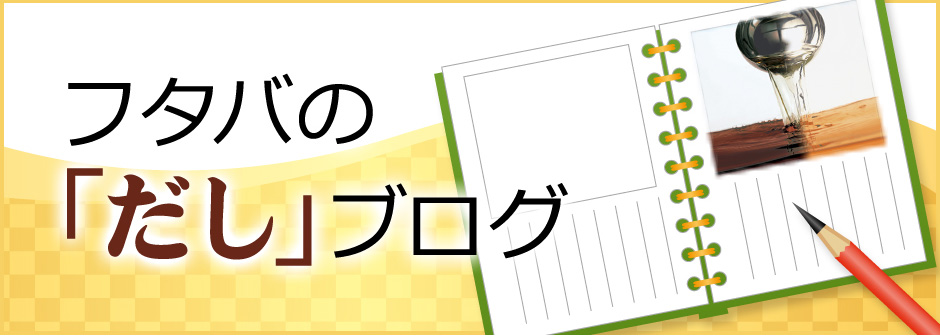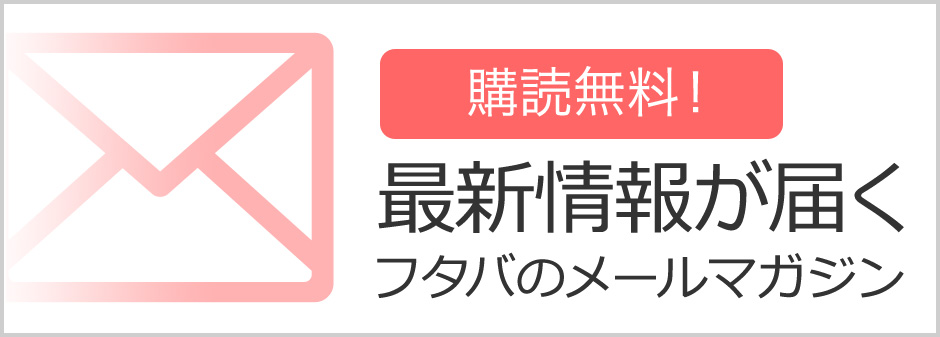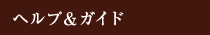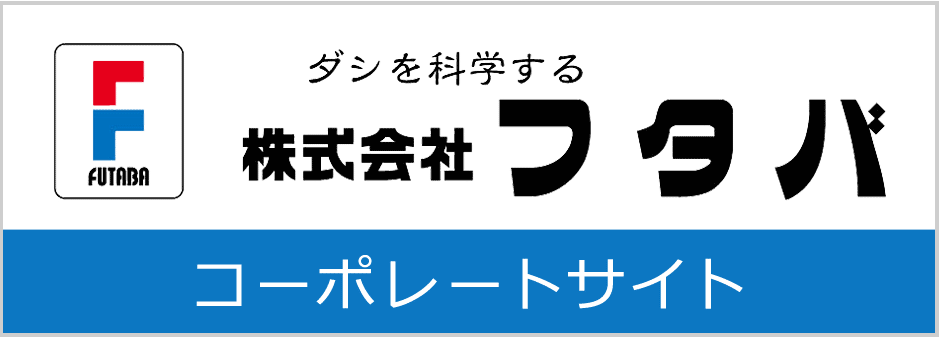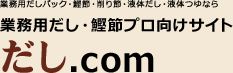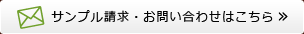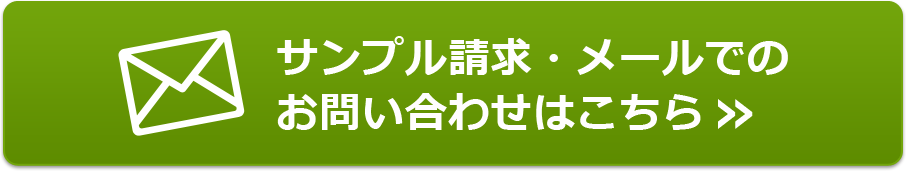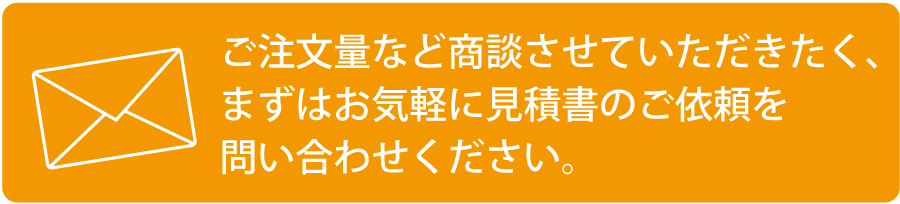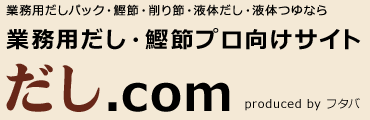飲食店におけるメニュー開発では、味や見た目だけでなく、原価や業務効率といった経営視点も欠かせません。
特に昨今では、食品ロスの削減や人手不足への対応も急務となっています。
そうした中で注目されているのが「濃縮出汁」の活用です。
本記事では、メニュー開発の基本視点とともに、濃縮出汁を活かした効率的なメニューづくりのコツをご紹介します。
メニュー開発のコツを理解するための基本視点
メニュー開発における目的設定と方向性の考え方
メニューを新たに作る際には、まず「何のために開発するのか」という目的を明確にする必要があります。
たとえば「客単価を上げたい」「ロスを減らしたい」「回転率を上げたい」など、目指す方向が変われば設計するメニューの内容も大きく異なります。
目的があいまいなままでは、開発の軸がぶれ、メニュー全体のバランスも崩れがちです。
開発段階の初期に、経営目標と連動した明確な目的を立てることが重要です。
顧客ニーズと競合動向を把握するためのリサーチ手法
次に重視したいのが、顧客のニーズや競合店の傾向を的確に把握することです。
顧客の好みは時期やトレンドによって変わります。
アンケートやSNSの投稿内容、売上データから人気メニューを洗い出し、そこから新しいニーズを探るのが効果的です。
また、競合店の価格帯や提供スピード、メニュー構成を調べることで、自店の立ち位置や差別化のヒントが得られます。
現場視察やレビューサイトの分析も参考になります。
原価と売上データに基づくメニュー分析の基本
メニュー開発においては、感覚ではなく数値に基づいた判断が不可欠です。
まずはABC分析で既存メニューの売上と利益を可視化しましょう。
「よく出るが利益が薄いA品目」「出数は少ないが高利益のB品目」などの傾向を把握することで、何を残し、何を刷新すべきかが見えてきます。
また、FLR比率(原価・人件費・家賃の合計)を意識し、価格設定と利益率を管理することで、メニューの収益性を安定させることができます。

濃縮出汁を活用した効率的なメニュー開発の実践法
食材共通化によるロス削減とメニュー展開の工夫
濃縮出汁は、複数のメニューに応用が利く点が大きなメリットです。
たとえば同じ出汁をベースに、うどん・煮物・茶碗蒸しなどの複数メニューを構成すれば、食材の在庫管理もシンプルになり、廃棄のリスクを抑えられます。
さらに、味の統一感も生まれるため、店舗全体のブランディングにもつながります。
共通食材を意識した設計にすることで、ロス削減とメニューの幅を両立することが可能になります。
味の安定化と時短調理を実現する濃縮出汁の活用方法
飲食店では、限られた人手での安定した味づくりが求められます。
濃縮出汁を活用すれば、誰が調理しても同じ味に仕上がるため、クオリティのばらつきを防げます。
さらに、計量・抽出・加熱といった工程を省けるため、調理時間の短縮にも直結します。
ランチ営業や回転率が求められる時間帯でも対応しやすくなり、業務の負荷軽減に貢献します。
濃縮出汁を使ったメニュー設計の考え方と組み立て例
実際のメニュー設計では、「主力メニュー」「サイドメニュー」「季節メニュー」など、構成ごとに濃縮出汁の使い道を整理することがポイントです。
たとえば、主力メニューに使用する出汁は、風味や濃さをカスタマイズできるものを選び、サイドメニューでは汎用性の高い出汁で手軽に仕上げるなどの工夫ができます。
また、出汁の種類を月ごとに入れ替えることで、季節感のあるメニュー展開も実現できます。

まとめ
メニュー開発では、目的設定・リサーチ・分析といった基本視点を押さえることが、的確な方向性を見出す第一歩です。
加えて、濃縮出汁を活用することで、業務の効率化や味の安定、ロス削減など複数の課題を同時に解決できます。
共通食材としての強みを活かしながら、メニューの幅や展開力を高めていく工夫が求められます。
日々の営業と連動した実践的なメニュー設計を意識することで、利益向上につながるメニューづくりが実現できるでしょう。