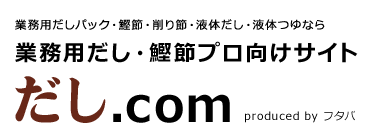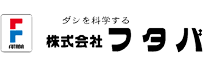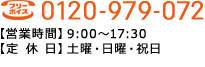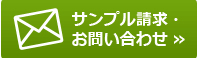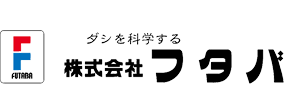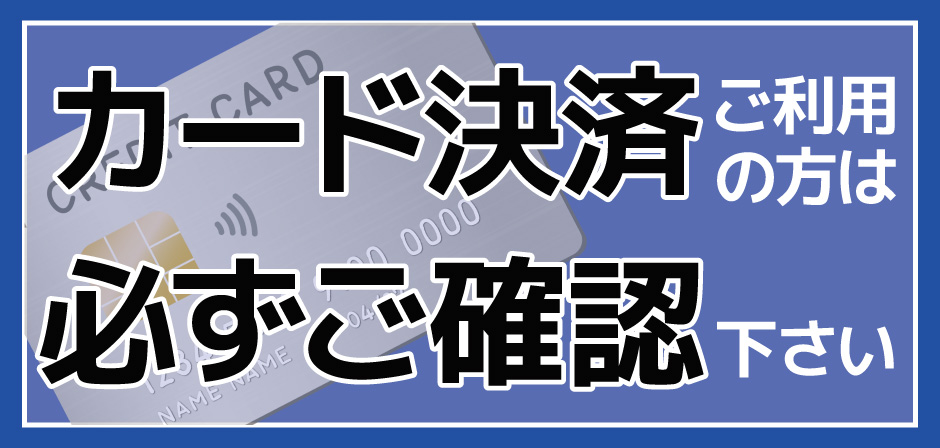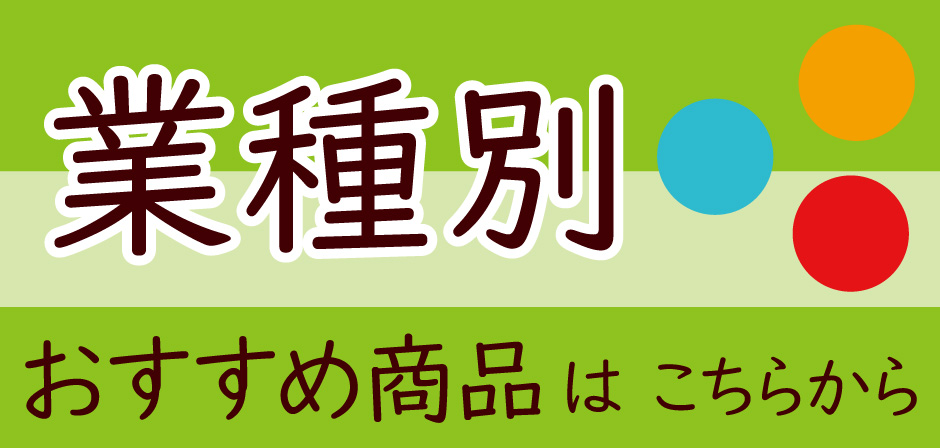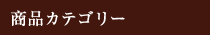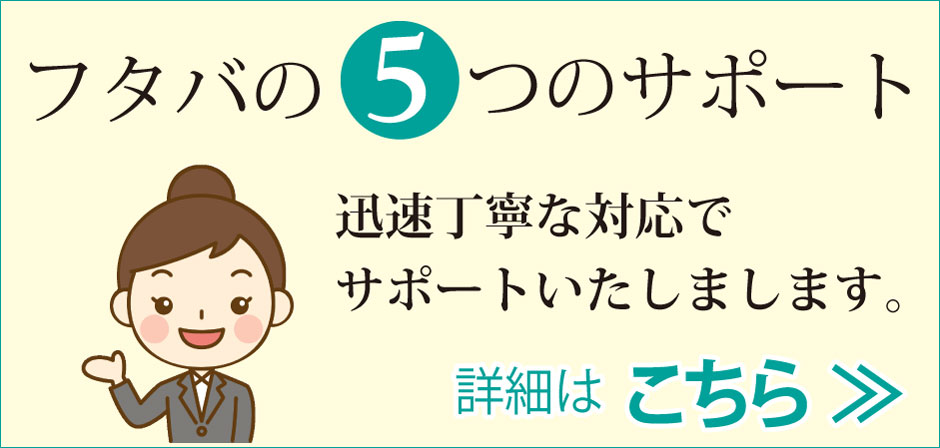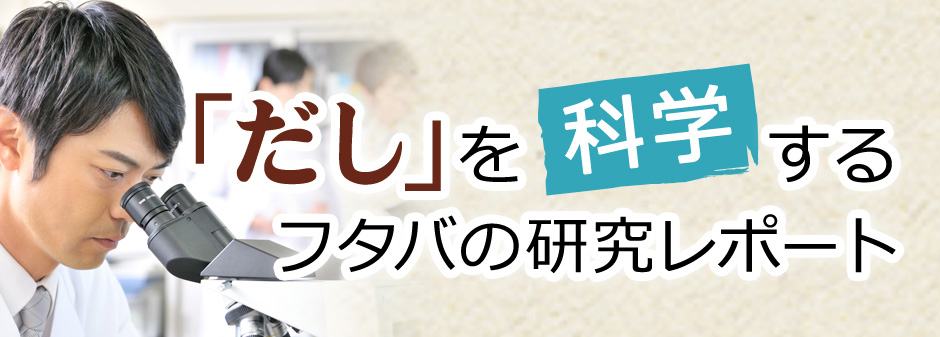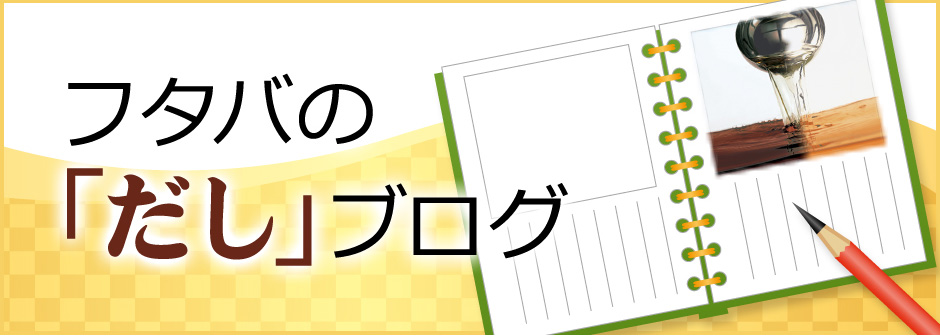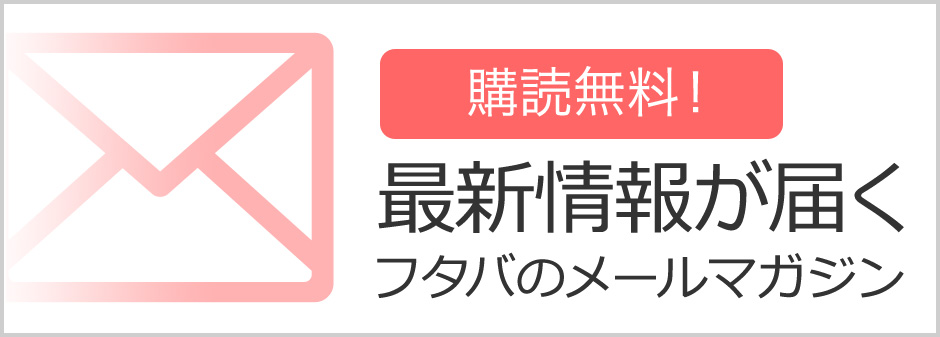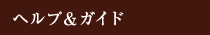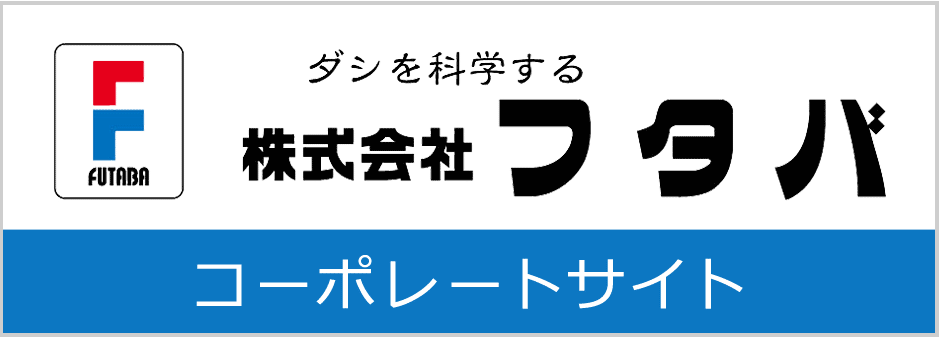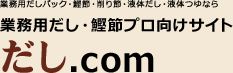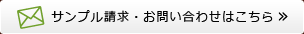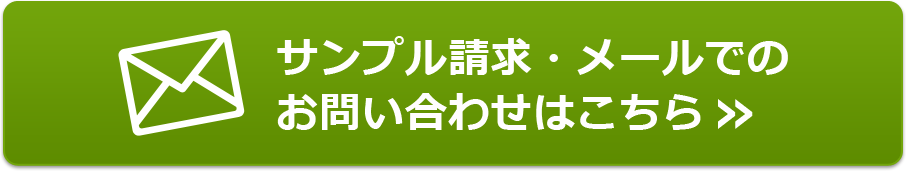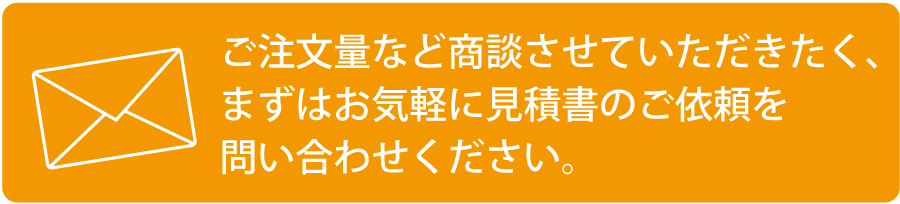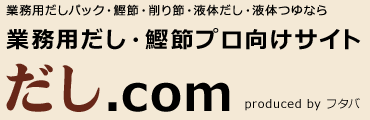いりこは、煮干しの別名として知られ、カルシウムやタンパク質が豊富な食材です。
手軽に購入でき、様々な料理に使われていますが、そのまま食べることを検討している方もいるのではないでしょうか。
今回は、いりこを生で食べる際の安全性と、より美味しく食べるための方法について解説します。
いりこの安全性
いりこの種類と安全性
いりこは、原料となるカタクチイワシの種類や加工方法によって、安全性に若干の違いが生じることがあります。
一般的に流通しているいりこは加熱処理が施されているため、寄生虫や菌のリスクは比較的低いといえます。
しかし、完全にリスクがないとは言い切れません。
特に、無添加や生に近い状態で販売されているいりこは注意が必要です。
購入する際には、製造工程や原材料をよく確認し、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが重要となります。
また、産地や漁獲方法なども安全性の判断材料となります。
例えば、水質が良好な海域で獲れたカタクチイワシを使用している製品は、より安全性の高いものと言えるでしょう。
さらに、消費者の口コミやレビューなども参考にすることで、より安心して食べられるいりこを選ぶことができます。
寄生虫や菌のリスクと対策
いりこに寄生する可能性のある寄生虫としては、アニサキスなどが挙げられます。
アニサキスは低温で長時間保存することで死滅しますが、完全にリスクを排除するためには、加熱調理が最も効果的な方法です。
また、菌に関しては、保存状態によっては腐敗菌などが繁殖する可能性があります。
特に、高温多湿の環境での保存は避けるべきです。
購入後は、冷蔵庫で適切に保存し、賞味期限内に消費することが大切です。
さらに、いりこの表面に付着している汚れや異物は、流水で丁寧に洗い流すことで、菌のリスクを低減することができます。
そして、調理前にしっかりと水気を切ることも、菌の繁殖を抑える上で有効な手段となります。
安全に食べるための下処理
いりこを生で食べる際には、適切な下処理を行うことで安全性を高めることができます。
まず、流水で丁寧に洗い、汚れや異物を除去します。
その後、塩水に浸けることで、残留物や菌を除去する効果が期待できます。
塩水に浸ける時間は、いりこの量や状態によって調整する必要がありますが、数分から1時間程度が目安です。
また、天日干しや低温乾燥を行うことで、水分を飛ばし、腐敗菌の繁殖を抑えることができます。
さらに、冷蔵庫でしっかりと冷やすことで、いりこの身を引き締め、より美味しく食べることができます。
ただし、これらの下処理は完全にリスクを排除するものではないことを理解しておく必要があります。

いりこをそのまま美味しく食べるには?
新鮮ないりこの選び方
新鮮ないりこを選ぶためには、いくつかのポイントがあります。
まず、色つやを確認しましょう。
新鮮ないりこは全体に光沢があり、体全体がしっかりとしています。
また、においにも注意が必要です。
新鮮なものは、特有の魚介類の香りが程よく感じられ、生臭さや酸っぱい臭いはしません。
さらに、サイズや形にも注目しましょう。
同じ種類であれば、大きすぎず小さすぎない、形が整っているものが良いでしょう。
加えて、購入する際は、できるだけ新しい製造日のものを選ぶと、より新鮮な状態で楽しむことができます。
ただし、これらの基準は、いりこの種類によっても異なるため、注意が必要です。
おすすめの食べ方
新鮮ないりこは、そのまま食べても美味しくいただけます。
特に、頭と内臓を取り除いたものは、食べやすく、独特の旨みとコクを楽しむことができます。
そのまま食べるだけでなく、サラダや和え物などの料理にも活用できます。
例えば、細かく刻んでドレッシングに混ぜたり、和え物の具材として加えるのもおすすめです。
また、刻んでふりかけのように使うのも良いでしょう。
生のまま食べる場合は、必ず新鮮なものを選び、下処理をしっかり行いましょう。
美味しい味付け方
いりこをそのまま食べる場合、シンプルに塩を振るだけでも美味しくいただけます。
また、醤油やみりん、ごま油などを少量加えても風味が増し、より美味しくなります。
例えば、醤油とみりんを1:1で混ぜたものに、いりこを軽く漬け込むのもおすすめです。
柑橘系の果汁を絞るのも良いでしょう。
柚子やスダチなどの果汁は、いりこの風味を引き立てます。
お好みで、刻んだネギや生姜などを加えるのも良いでしょう。
味付けは、いりこの種類や鮮度、個人の好みに合わせて調整することが重要です。
いりこの適切な保存方法
いりこは、保存方法によって鮮度や味が大きく変化します。
新鮮な状態を保つためには、冷蔵庫での保存がおすすめです。
特に、生で食べる場合は、冷蔵保存が不可欠です。
冷蔵庫の中でも、水分が多く残っていると腐敗しやすいため、十分に乾燥させてから保存することが重要です。
乾燥剤と一緒に密閉容器に入れて保存すると、より効果的に鮮度を保つことができます。
また、冷凍保存も可能です。
冷凍する場合は、密閉容器に入れて保存しましょう。
冷凍保存した場合は、解凍せずに調理することがおすすめです。

まとめ
今回は、いりこを生で食べる際の安全性と、より美味しく食べるための方法について解説しました。
いりこは、適切な下処理と保存方法を守れば、安全に美味しくいただくことができます。
新鮮ないりこを選び、適切な方法で調理・保存することで、いりこの持つ豊かな風味を最大限に楽しむことができます。
新鮮な状態での確認、適切な下処理、そして保存方法に気を配り、安全で美味しいいりこ体験をしてみてください。