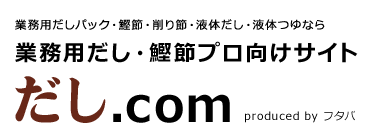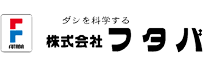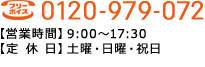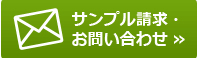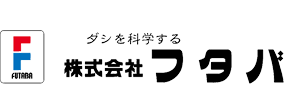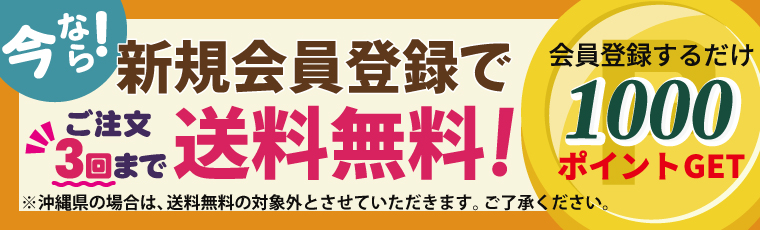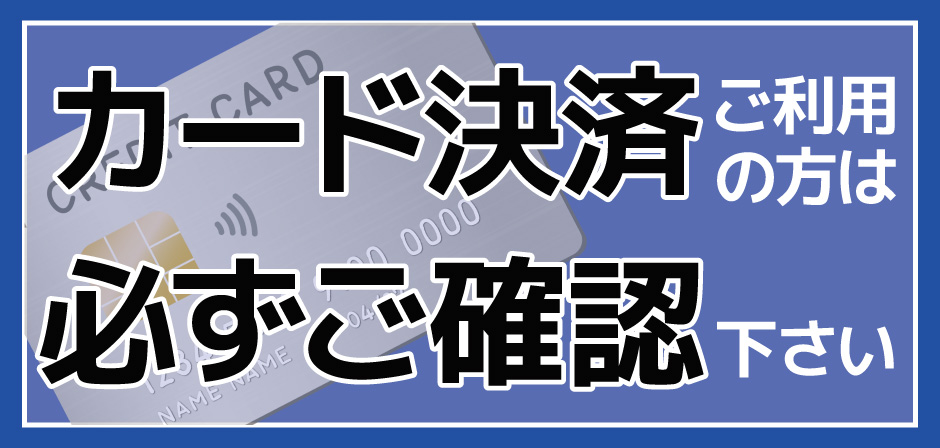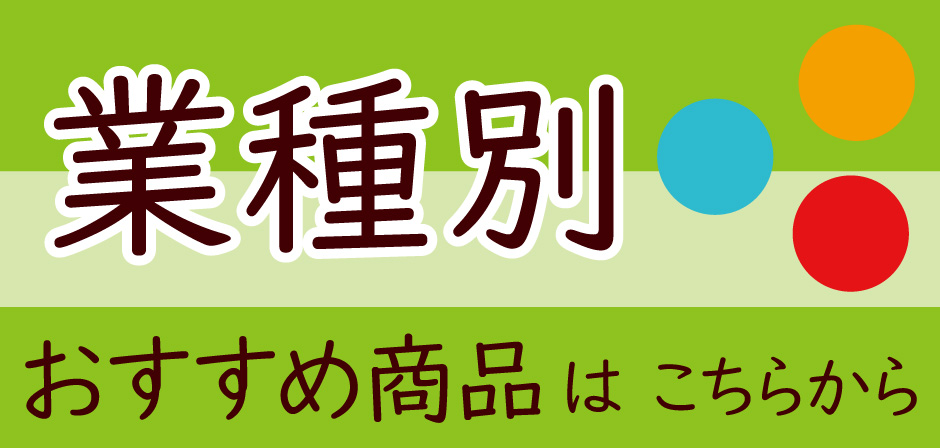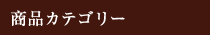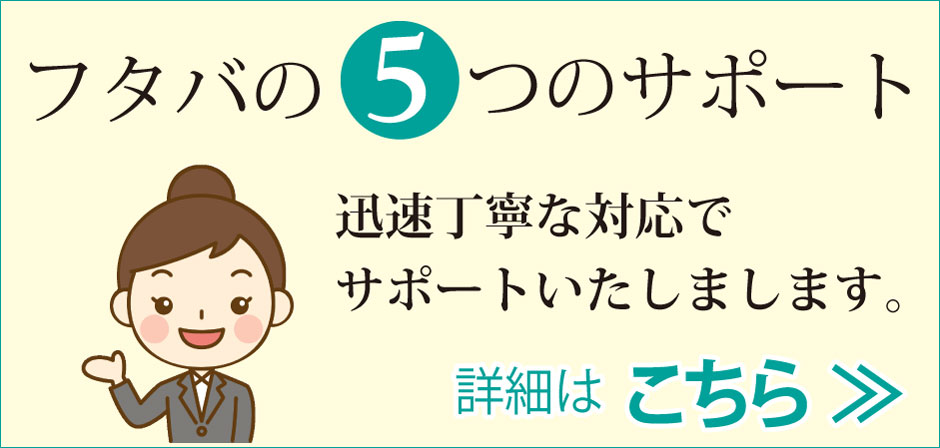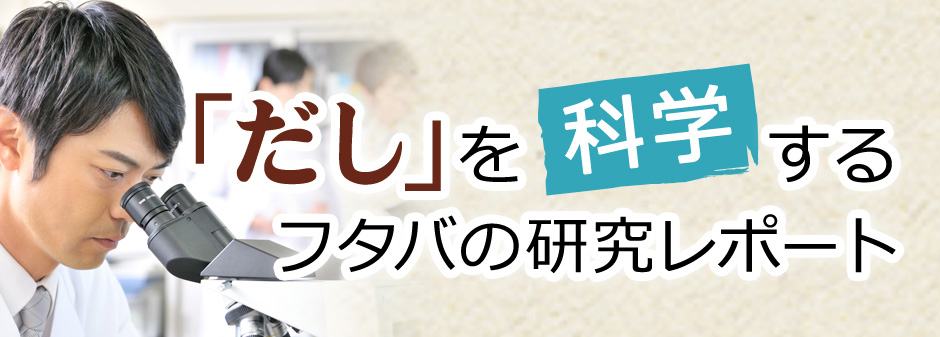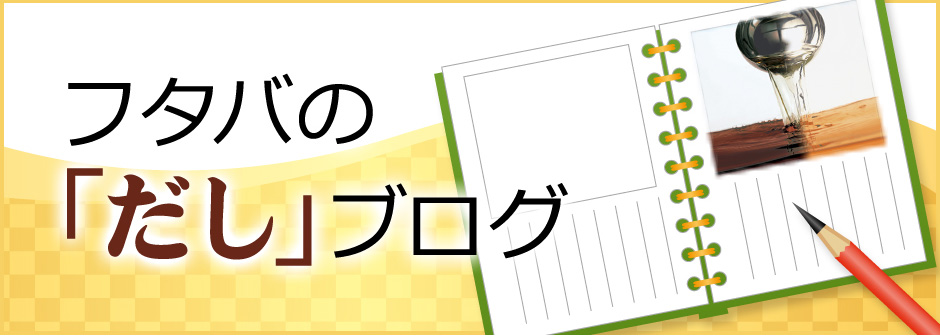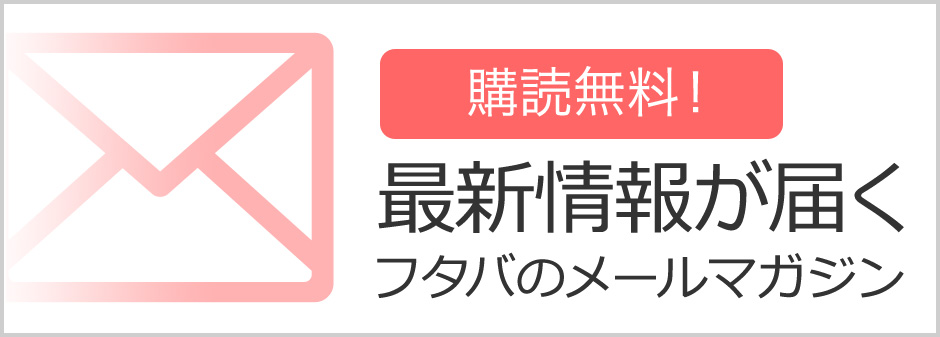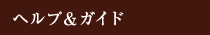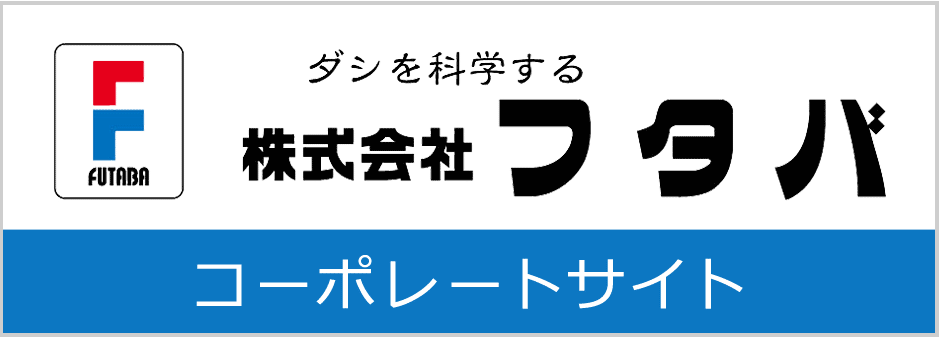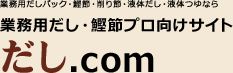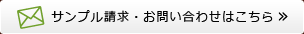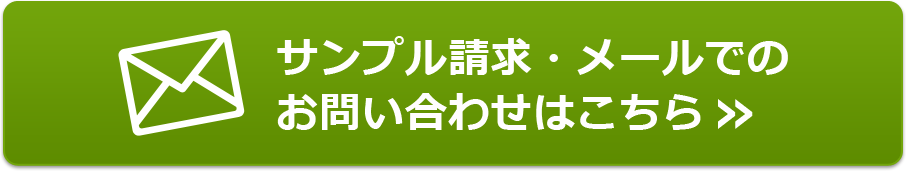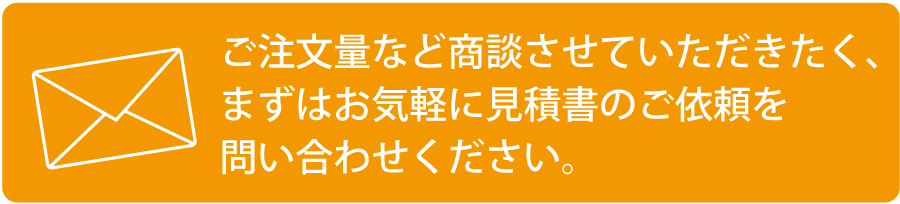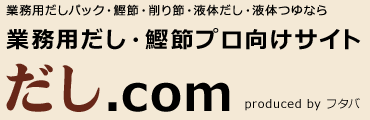料理の世界で「うま味」という言葉は頻繁に耳にするものですが、その科学的な背景や具体的な影響について詳しく知っている方は意外に少ないかもしれません。
この不思議な味覚を理解し、家庭での料理に活用する方法を探ることで、日常の食事が一層豊かなものに変わるでしょう。
さらに、日本食に欠かせない「だし」の取り方をマスターすることは、料理の基本を固める上で非常に重要です。
これから、うま味の成分とその効果、そしてだしの取り方と活用法について、具体的に掘り下げていきましょう。
うま味の基本
うま味成分の科学的説明
うま味とは、グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸といったアミノ酸や核酸から成る味覚の一つです。
これらの化学成分は、食材の自然な風味を強化し、舌の上で複雑な味わいを生み出します。
たとえば、グルタミン酸はトマトやチーズに豊富に含まれ、これが熟成する過程で増加するため、熟成チーズや完熟トマトの深い味わいの源となっています。
うま味が料理に与える効果
うま味成分を料理に加えることで、全体の味のバランスが向上し、食材本来の風味が際立ちます。
例えば、うま味が豊富な食材を使ったスープは、味わいが深く感じられ、満足感が増します。
この効果は、料理全体の味を引き立てるため、少量のうま味成分で大きな差を生むことが可能です。
うま味成分を含む代表的な食材
既に触れたトマトやチーズの他に、昆布や魚介類、キノコ類もうま味成分を豊富に含みます。
特に昆布にはグルタミン酸が豊富で、これを使っただしは日本料理における味の基底を形成します。

だしの基本的な取り方と活用法
家庭で簡単にできるだしの取り方
昆布だしは、水に昆布を数時間浸させるだけで簡単に作ることができます。
また、鰹節を使った鰹だしは、熱湯をかけて数分間待つだけで、芳醇な風味のだしが取れます。
これらのだしは、さまざまな料理の土台として使用でき、その手軽さから日常的に取り入れやすいです。
だしを使用した料理例
だしを使った代表的な料理には、みそ汁やうどん、煮物がありますが、これらは日本の家庭料理において基本中の基本です。
だし一つを変えるだけで、料理の風味が大きく変わるため、多様な味わいを楽しむことができます。
だしの種類とその特徴
昆布だしは深い旨味が特徴で、清潔感のある味わいがします。
一方、鰹だしは独特の芳ばしさがあり、味に奥行きを加えます。
他にも、椎茸だしや鶏肉を使っただしなど、使用する材料によってまったく異なる特徴を持つだしを作ることが可能です。
だしを使うことのメリット
だしを使う最大のメリットは、自然な味わいで料理の深みを増すことです。
化学調味料に頼らずとも、これら天然のだしで十分な味付けが可能となり、料理の健康面でも安心感が増します。

まとめ
うま味成分の効果的な使用と、家庭で簡単に取り入れることができるだしの基本について解説しました。
うま味成分を含む食材の選び方や、それを活かした料理方法を理解し、実践することで、毎日の食事がより豊かで満足感のあるものになるでしょう。
また、さまざまな種類のだしを使い分けることによって、料理の幅が広がり、家族や友人を驚かせる料理を提供できるかもしれません。
これらの知識が、より良い料理を目指す一助となれば幸いです。