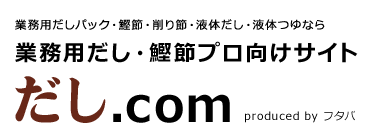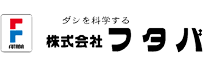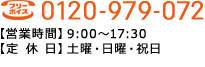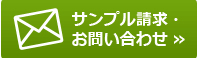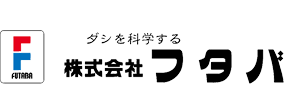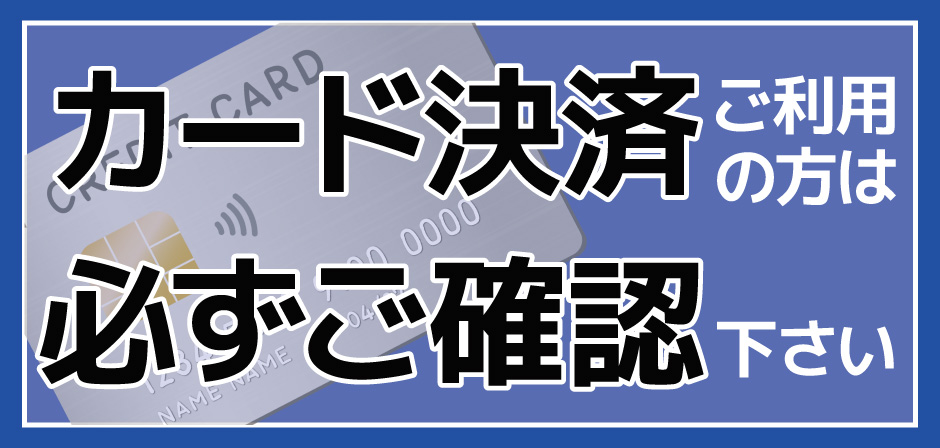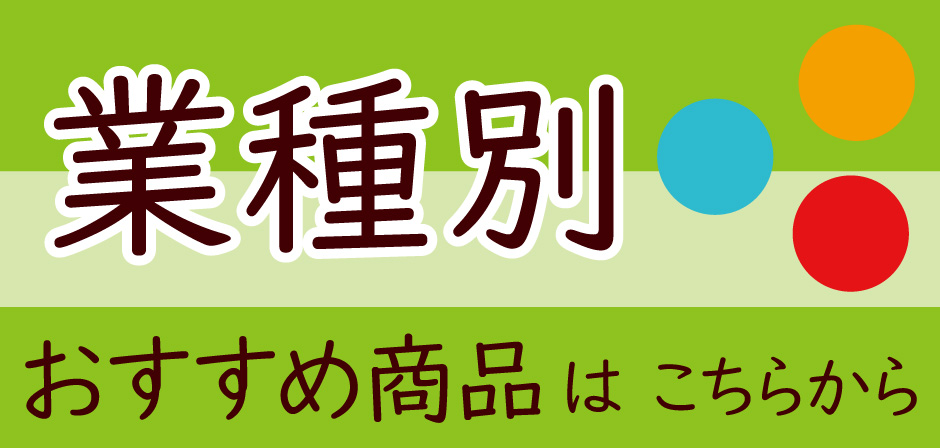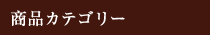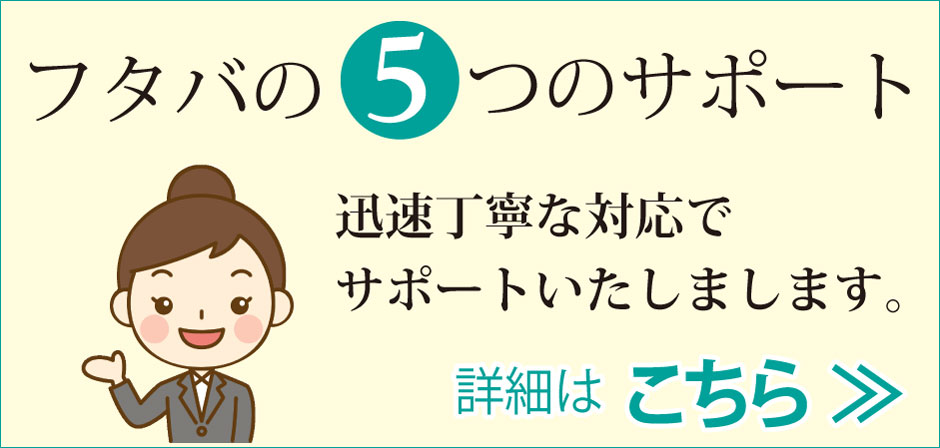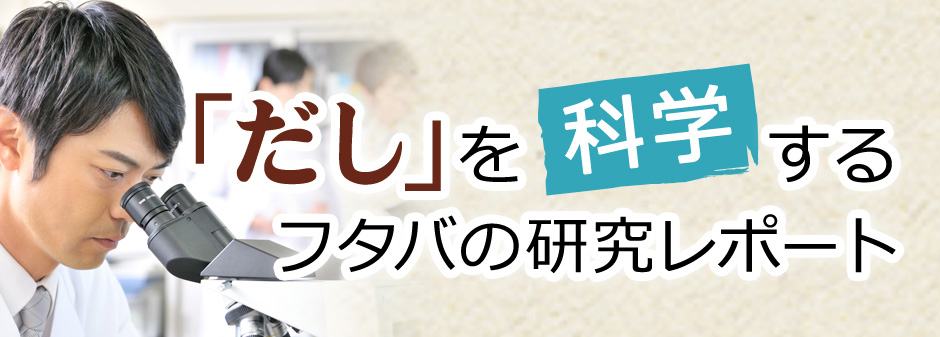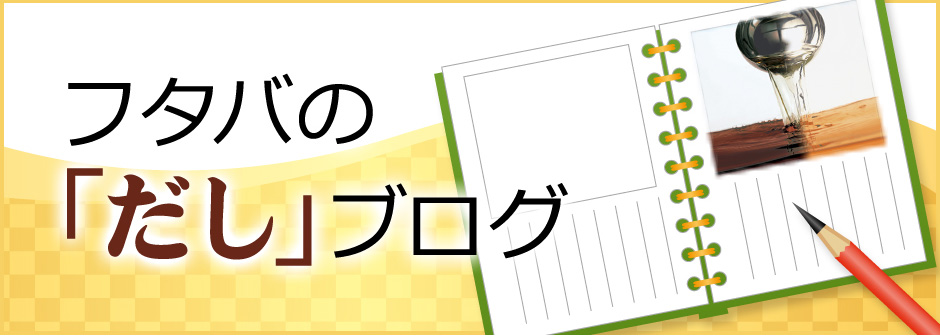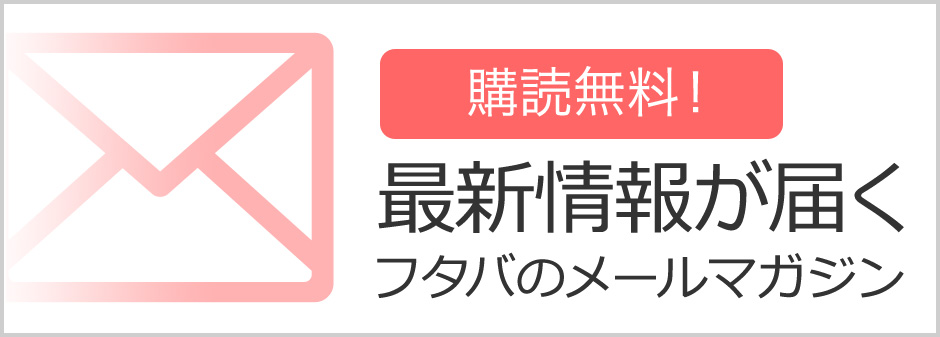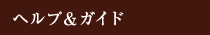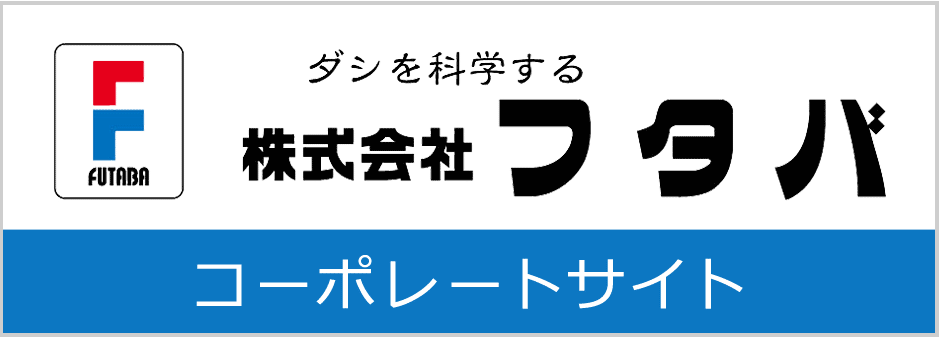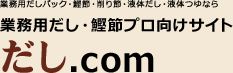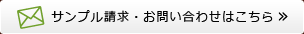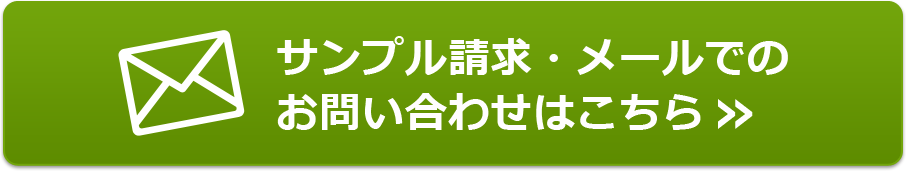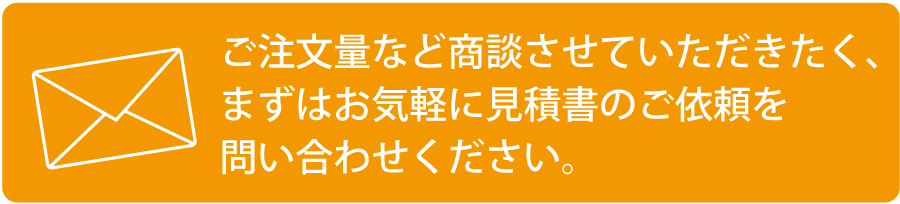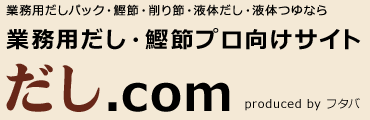「だし」の旨味、その奥深さを知り尽くしていますか?
料理の魂とも言える「だし」の風味を決定づけるのは、実は、食材に含まれる様々な成分の複雑な相互作用です。
その中でも特に重要な役割を果たすのが、旨味成分の一つであるイノシン酸。
この神秘的な成分を深く理解することで、料理は新たな境地へ到達するでしょう。
イノシン酸の性質、食材への含み方、そして料理における活用法を、一緒に探求していきましょう。
イノシン酸とは何か
イノシン酸の定義と性質
イノシン酸は、核酸を構成する成分の一つであるヌクレオチドの一種です。
具体的には、リボ核酸(RNA)の構成成分であり、動物の筋肉や魚介類に多く含まれています。
独特の旨味を持つことで知られ、特に5′-イノシン酸が強い旨味を示します。
一方、2′-イノシン酸や3′-イノシン酸はほとんど旨味を感じません。
この違いは、リン酸基の位置によって生じます。
うま味成分としての役割
イノシン酸は、グルタミン酸やグアニル酸と共に「三大うま味成分」の一つに数えられます。
単体でも強い旨味を持ちますが、他のうま味成分と組み合わせることで相乗効果が生まれ、より深い旨味を創り出します。
この相乗効果は、料理の風味を格段に向上させる鍵となります。
三大うま味成分との関係
イノシン酸は、グルタミン酸(昆布などに豊富)やグアニル酸(干し椎茸などに豊富)と組み合わせることで、それぞれの旨味が何倍にも増強される相乗効果を示します。
例えば、カツオ節(イノシン酸)と昆布(グルタミン酸)を組み合わせただしは、この相乗効果の好例です。
それぞれの成分の特性を理解し、適切に組み合わせることで、奥行きのある風味豊かなだしを実現できます。

イノシン酸の料理への応用
イノシン酸を含む食材
イノシン酸は、カツオ節、イワシ(煮干し)、サバなどの魚介類、鶏肉、豚肉、牛肉などの肉類に多く含まれます。
また、乾燥させた椎茸にも含まれています。
これらの食材は、だし汁をとる際や、料理の素材として、イノシン酸を効果的に摂取する手段となります。
料理における活用法
イノシン酸を効果的に活用するには、素材の特性を理解することが重要です。
例えば、カツオ節はだし汁として、肉類は炒め物や煮込み料理として活用できます。
乾燥椎茸は、水戻しすることでイノシン酸を効率的に抽出できます。
それぞれの食材の特性を生かした調理法を選択することで、より深い旨味を引き出すことができます。
イノシン酸を増やす調理法
イノシン酸は、食材の熟成過程で生成されます。
特に魚介類や肉類では、死後、酵素の働きによってアデノシン三リン酸(ATP)からイノシン酸が生成されます。
適切な熟成を行うことで、イノシン酸の量を増やし、旨味を濃縮することができます。
ただし、熟成には細心の注意が必要です。
腐敗が始まる前に、適切なタイミングで調理することが重要です。
また、低温でじっくりと水戻しすることで、乾燥椎茸からイノシン酸を効率的に抽出することもできます。
まとめ
イノシン酸は、料理の風味を決定づける重要な旨味成分です。
その性質や、他のうま味成分との相乗効果を理解することで、より深く豊かな味わいを生み出せます。
様々な食材に含まれるイノシン酸を効果的に活用し、調理法を工夫することで、料理の技量をさらに高めましょう。
イノシン酸は、単なる旨味成分ではなく、料理の創造性を刺激する、無限の可能性を秘めた成分なのです。
今日から、料理にイノシン酸の魔法をかけてみてください。