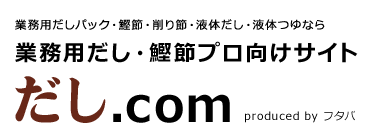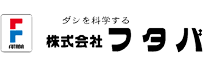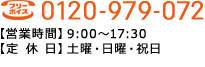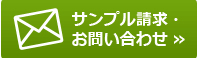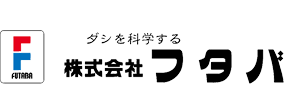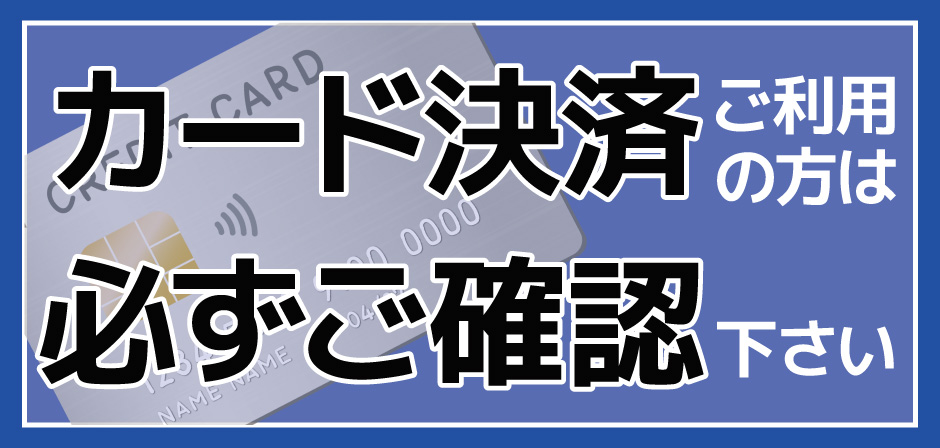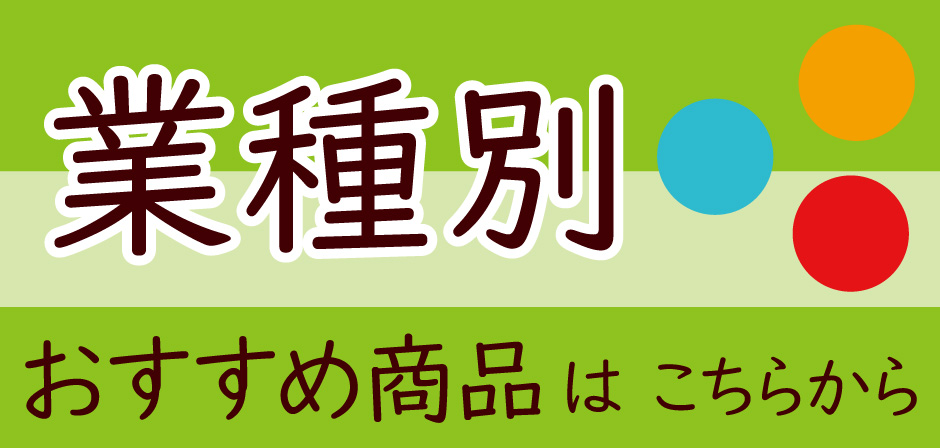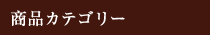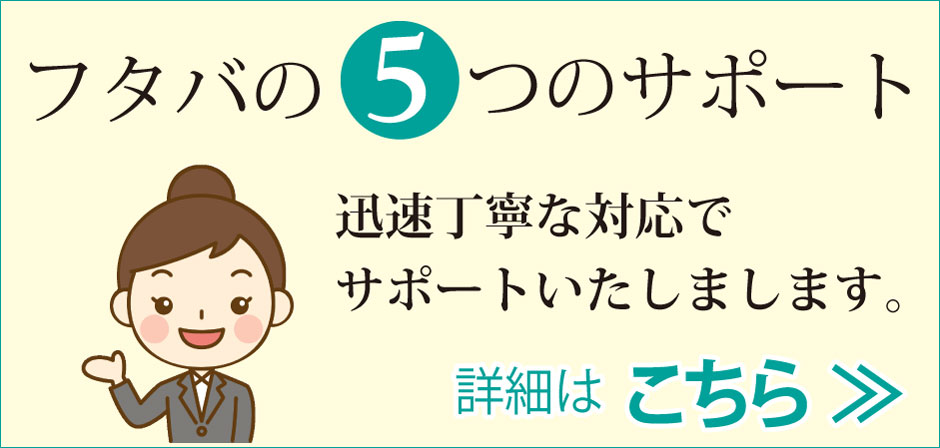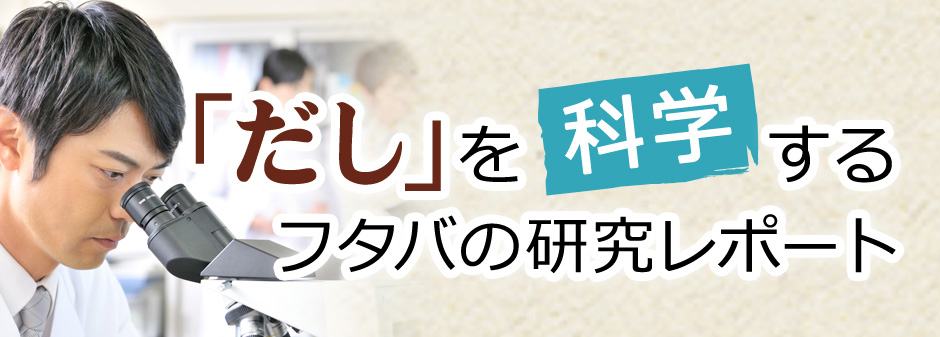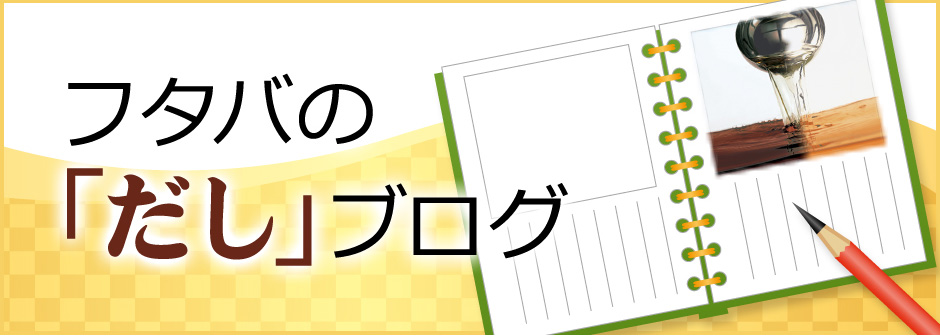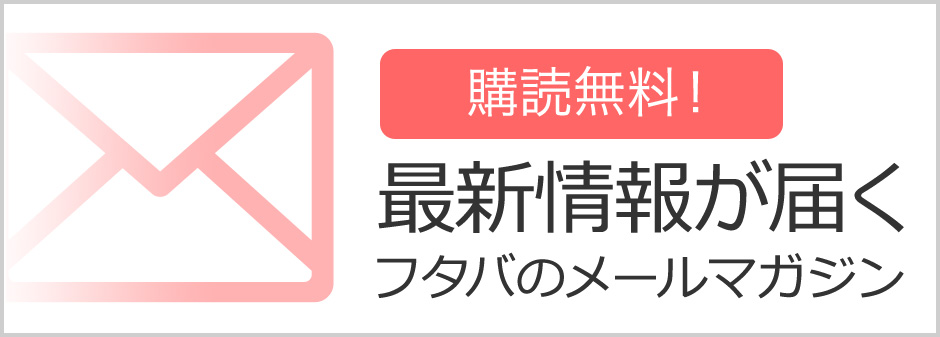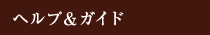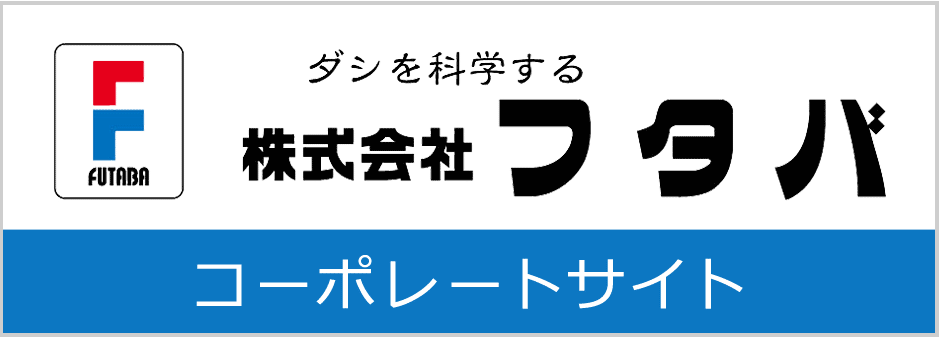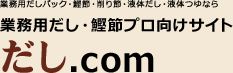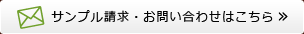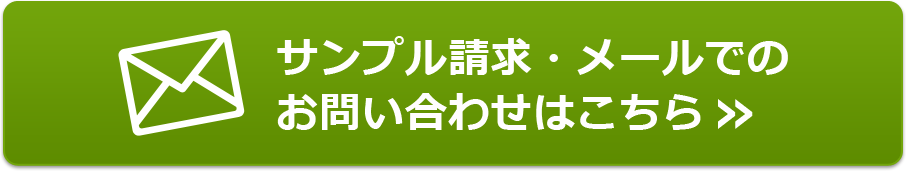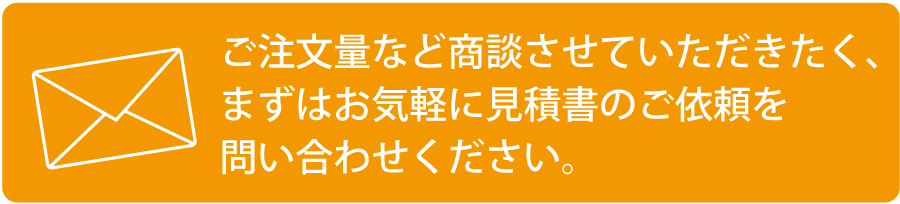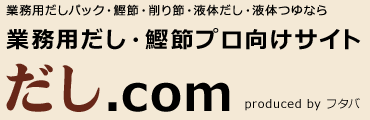オマール海老と伊勢海老。
どちらも高級食材として知られ、豪華な食卓を彩る存在です。
しかし、その見た目や価格の類似性とは裏腹に、両者には多くの違いが存在します。
見た目だけでは判断しづらいその違いを理解することで、より深く食材の魅力を堪能できるでしょう。
今回は、オマール海老と伊勢海老の分類、生態、価格、食味、そして代表的な料理まで、多角的に比較することで、それぞれの個性を浮き彫りにします。
オマール海老と伊勢海老の分類と生態
オマール海老の分類と生態
オマール海老は、エビ目ザリガニ下目アカザエビ科ロブスター属に分類される海洋性甲殻類です。
名前は「海老」ですが、実際はザリガニの仲間です。
大西洋のノルウェーから地中海近辺、アメリカ東海岸、アフリカ南岸、南大西洋のトリスタンダクーニャなどに生息し、通常75センチメートルほどまで成長しますが、まれに1メートルを超えるものもいます。
脱皮を繰り返すことで成長し、内臓も含めて再生するため、「老いることがない」とも言われます。
ただし、脱皮できないほど殻が硬くなると死んでしまうため、不老不死というわけではないでしょう。
低脂肪で、タンパク質、リン、亜鉛などのミネラル、ビタミンB12が豊富です。
オスはメスより大きな爪を持ちますが、メスの方が肉厚で美味とされています。
伊勢海老の分類と生態
伊勢海老は、エビ目イセエビ下目イセエビ科イセエビ属に分類される、正真正銘のエビです。
日本の房総半島から台湾に至る太平洋沿岸地域、朝鮮半島南部、インド洋の熱帯地域など、広い範囲に生息しています。
体長は30センチメートル程度が一般的で、40センチメートルを超えるものは稀です。
太い円筒形で、全身が赤褐色のトゲのある硬い殻に覆われています。
2対の触覚も硬い殻に覆われています。
名前の由来は、伊勢地方がかつて主要産地だったことにあります。
日本では古くから食されており、文献にも1500年代からその記述が見られます。
生息地の比較
オマール海老は主に大西洋に広く分布し、ヨーロッパや北米で多く漁獲されます。
一方、伊勢海老は太平洋西岸、特に日本近海に多く生息しています。
生息域の違いは、それぞれの体の色や形、そして食味にも影響を与えていると考えられます。

オマール海老と伊勢海老の価格・食味・料理
価格帯の比較と市場動向
オマール海老と伊勢海老はどちらも高級食材ですが、価格は産地やサイズ、季節によって変動します。
一般的に、伊勢海老の方がオマール海老よりも高価です。
オマール海老は、産地やサイズによって価格差が大きく、ヨーロピアンオマールはアメリカンロブスターより高価です。
伊勢海老は、近年価格が高騰傾向にあります。
食味の比較と特徴
オマール海老はプリッとした弾力のある食感が特徴です。
一方、伊勢海老はオマール海老ほど弾力はありませんが、まろやかで濃厚な旨味が魅力です。
生でも加熱しても美味しく食べられます。
オマール海老は、内臓(味噌)も美味しく食べられることが特徴です。
代表的な料理と食べ方
オマール海老は、グリル、ソース、フランベ、リゾット、スフレ、サラダ、カルパッチョ、パスタなど、様々な料理に用いられます。
ビスクやテルミドールは代表的なフランス料理です。
伊勢海老は、刺身、焼き物、鍋物など、様々な料理に使われますが、日本では刺身で食べるのが一般的です。
オマール海老とロブスターの関係
オマール海老とロブスターは、同じ生物を指す別名です。
「オマール(homard)」はフランス語、「ロブスター(lobster)」は英語です。
アメリカンロブスターとヨーロピアンオマールでは、食味や価格に違いがあります。
ヨーロピアンオマールの方が、身が詰まっていて甘みとうまみが濃厚で上質とされ、希少性から価格も高くなっています。

まとめ
オマール海老と伊勢海老は、分類、生態、生息地、価格、食味、そして料理法において多くの違いを示します。
オマール海老はザリガニの仲間で、大西洋に広く分布し、プリッとした弾力のある食感が特徴です。
一方、伊勢海老はエビの仲間で、太平洋西岸に多く生息し、まろやかな旨味が魅力です。
価格は伊勢海老の方が一般的に高価ですが、オマール海老も産地やサイズによって価格差が大きいです。
それぞれの特性を理解した上で、料理や好みに合わせて選び、高級食材の美味しさを堪能しましょう。
両者の違いを知ることは、より豊かな食体験につながるでしょう。
高級食材を選ぶ際の判断材料として、本記事が役立つことを願っています。
当社ではオマール海老のスープベースを販売しています。
気になった方はぜひチェックしてみてください。