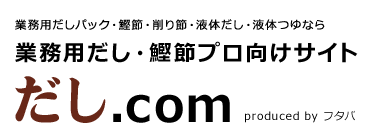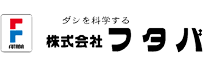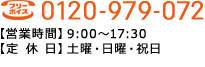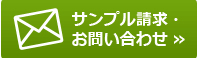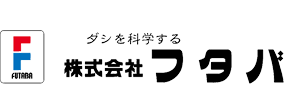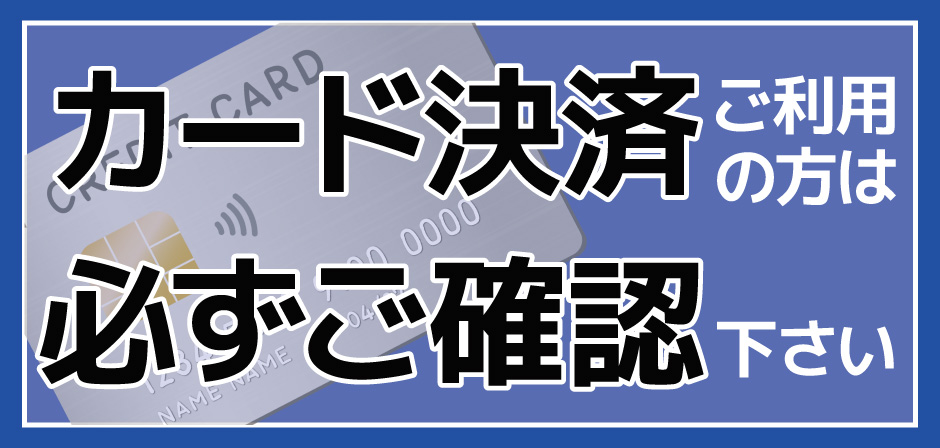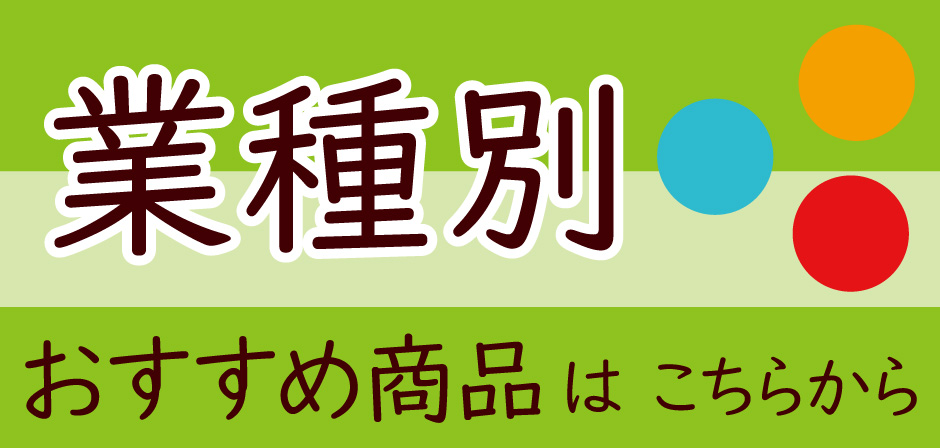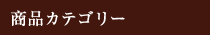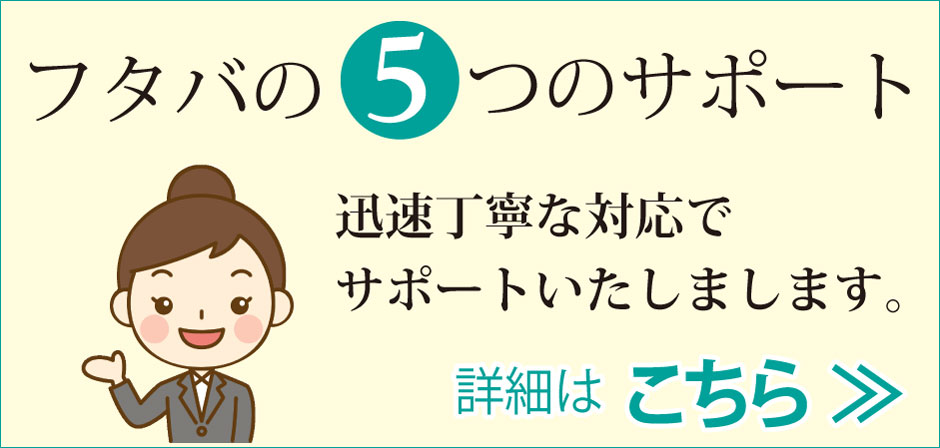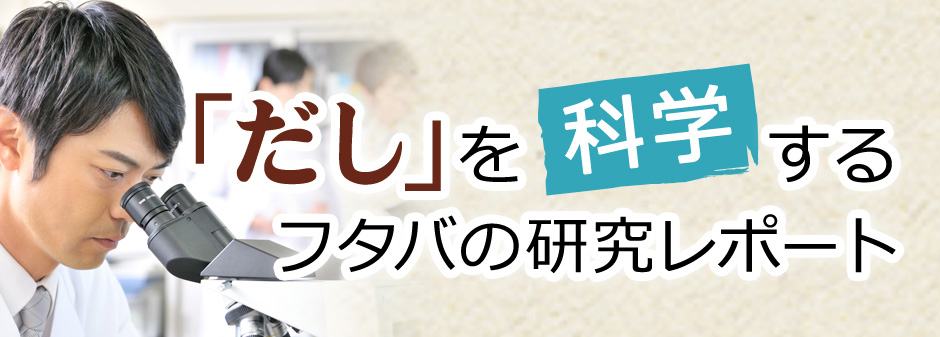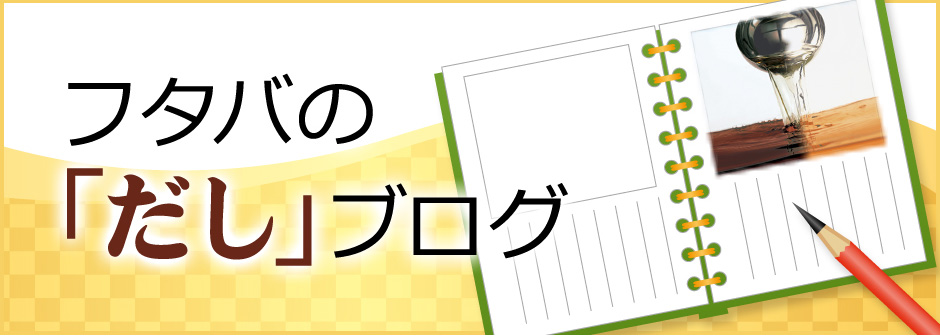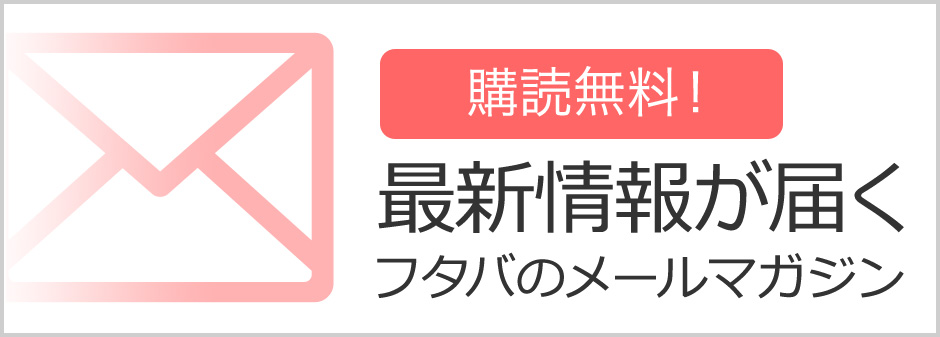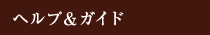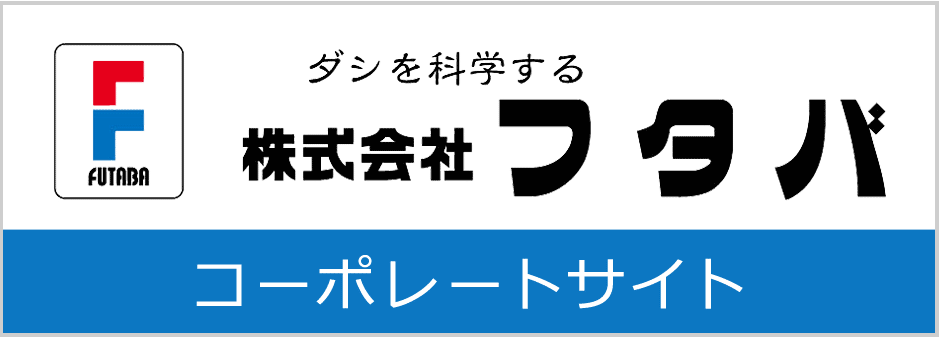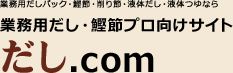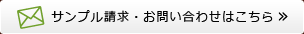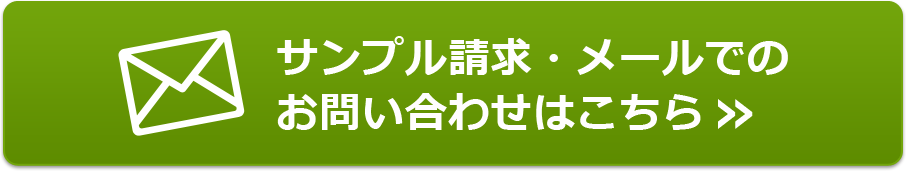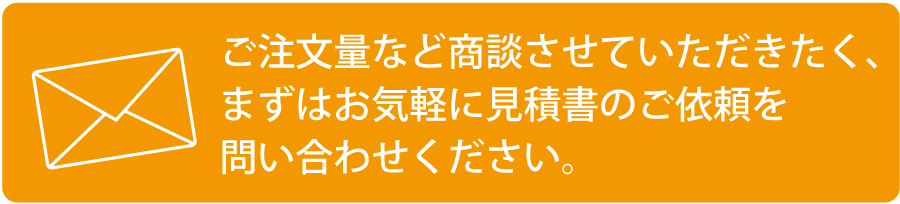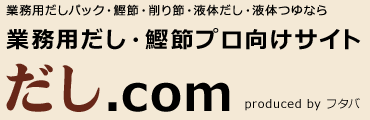和食の魂ともいえる「出汁」。
その中でも、奥深い味わいと豊かな香りを生み出す合わせ出汁は、料理の美味しさを何倍にも引き上げてくれます。
しかし、その魅力を最大限に引き出すには、適切な作り方と活用法が不可欠です。
今回は、合わせ出汁の究極の取り方から、その効果的な活用法、そして保存方法までを網羅的にご紹介します。
料理の腕を一段と上げたい方、ぜひ最後までお読みください。
合わせ出汁の究極の取り方
昆布と鰹節の最適な組み合わせ
合わせ出汁のベースとなるのは、昆布と鰹節。
昆布は、旨味成分のグルタミン酸を豊富に含み、上品な甘味ととろみを与えます。
一方、鰹節は、イノシン酸という旨味成分を多く含み、コクと深い味わいをプラスします。
昆布と鰹節の組み合わせは、それぞれの旨味成分が相乗効果を発揮し、単体よりもはるかに深い味わいを生み出します。
一般的には、昆布10gに対して鰹節20g程度の割合がおすすめです。
ただし、使用する昆布や鰹節の種類、好みの味によって調整してみてください。
理想的な火加減と時間
昆布は、水に浸して1時間ほど置いておくことで、旨味が十分に抽出されます。
その後、弱火でゆっくりと温め、沸騰直前に昆布を取り出します。
沸騰させてしまうと、昆布からぬめりが出てしまい、出汁が濁ってしまうため注意が必要です。
昆布を取り出した後、鰹節を加え、再び弱火で10~15分間加熱します。
この時、沸騰させないように、ごく弱火でじっくりと煮出すことがポイントです。
沸騰させると、鰹節から雑味が出てしまい、せっかくの旨味が損なわれてしまいます。
火を止め、鰹節が沈むまで置いておくことで、余熱でも旨味を抽出できます。
プロが教える濾し方
出汁を濾す際には、清潔な布巾や晒、または厚手のクッキングペーパーなどを敷いたザルを使用します。
濾す際は、ゆっくりと静かにこすようにすることで、出汁の濁りを防ぎ、澄んだ美しい仕上がりになります。
濾し終わった後、布巾やペーパーの四隅を折りたたんで、箸を使って軽く絞ることで、より多くの出汁を抽出できます。
熱くなっていますので、火傷には十分注意しましょう。
出汁のうま味成分と効果
合わせ出汁の旨味成分は、昆布由来のグルタミン酸と鰹節由来のイノシン酸が中心です。
これらの旨味成分は、相乗効果によって、単体で摂るよりもはるかに強い旨味を感じさせてくれます。
科学的にも、その相乗効果は4~8倍にもなることが証明されています。
また、合わせ出汁は、塩分控えめの料理を作る際にも役立ちます。
出汁の旨味を効果的に活用することで、塩分を減らしつつ、満足感のある味わいを提供することが可能です。

出汁の活用法と保存方法
合わせ出汁を使った料理
合わせ出汁は、和食のあらゆる料理に活用できます。
味噌汁、うどん、そば、お吸い物などの汁物はもちろんのこと、煮物、茶碗蒸し、鍋物などにも最適です。
素材本来の味を引き立て、上品な風味を添えてくれます。
出汁のうま味を最大限に活かすコツ
出汁の旨味を最大限に活かすためには、素材の組み合わせにも注意が必要です。
例えば、淡白な味の食材には、より濃厚な出汁を使うことで、奥行きのある味わいに仕上がります。
逆に、濃い味の食材には、あっさりとした出汁を使うことで、バランスの良い仕上がりになります。
また、出汁を加えるタイミングも重要です。
煮物などでは、仕上げに加えることで、素材の風味を損なうことなく、旨味をプラスできます。
出汁の保存方法と期間
作った合わせ出汁は、冷蔵庫で2~3日、冷凍庫で1~2週間程度保存可能です。
冷凍する際は、製氷機で氷のように凍らせておくと、必要な分だけ取り出して使えるので便利です。
出汁パックの活用法
市販の出汁パックも手軽で便利です。
様々な種類があるので、好みに合わせて選んでみましょう。
ただし、塩分が含まれているものも多いので、塩分摂取量に気を付けて使用することが大切です。

まとめ
合わせ出汁は、昆布と鰹節の絶妙な組み合わせによって生まれる、和食の基礎となる重要な調味料です。
この記事で紹介した、最適な材料の組み合わせ、火加減、濾し方、保存方法などを参考に、究極の合わせ出汁を作ってみてください。
そして、その深い旨味を活かした、様々な料理に挑戦してみましょう。
きっと、料理の幅が広がり、食卓がより豊かになるはずです。
最高の合わせ出汁で、美味しい料理を楽しみましょう。