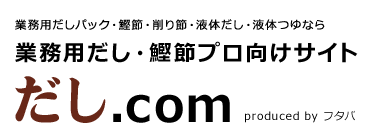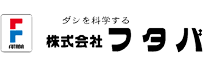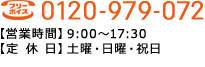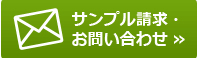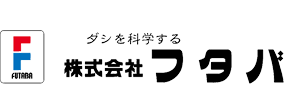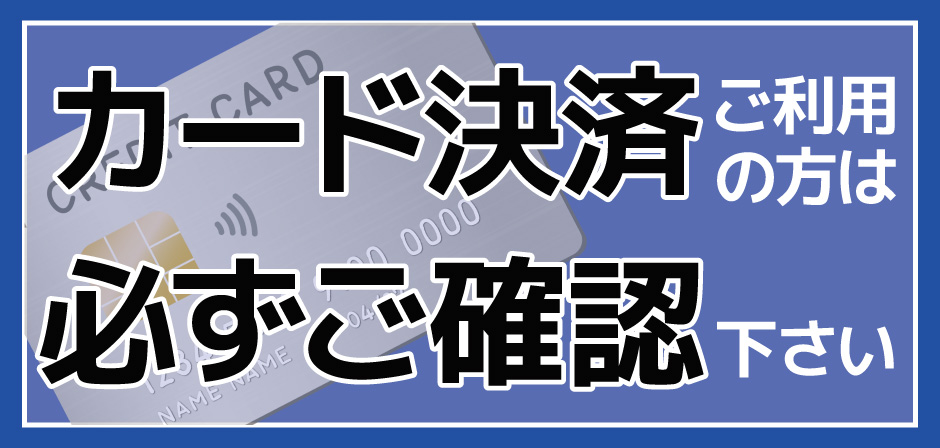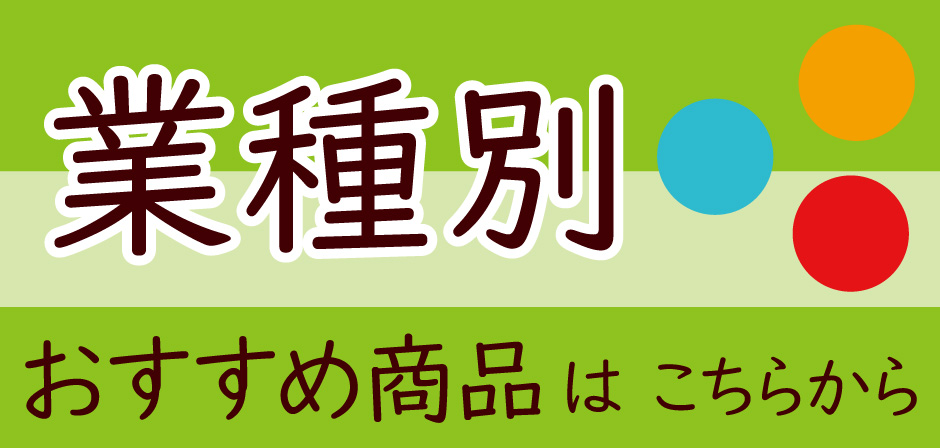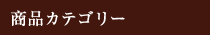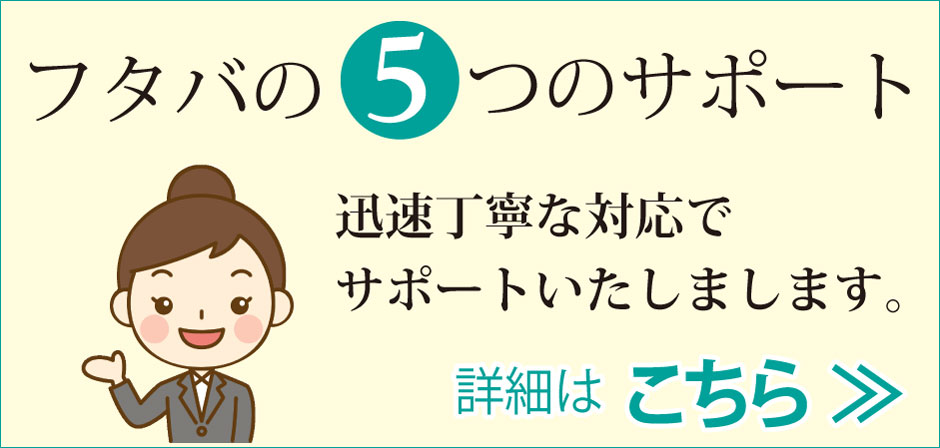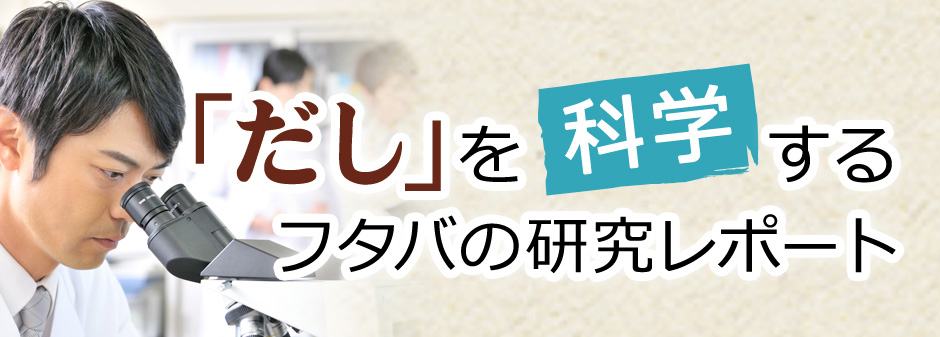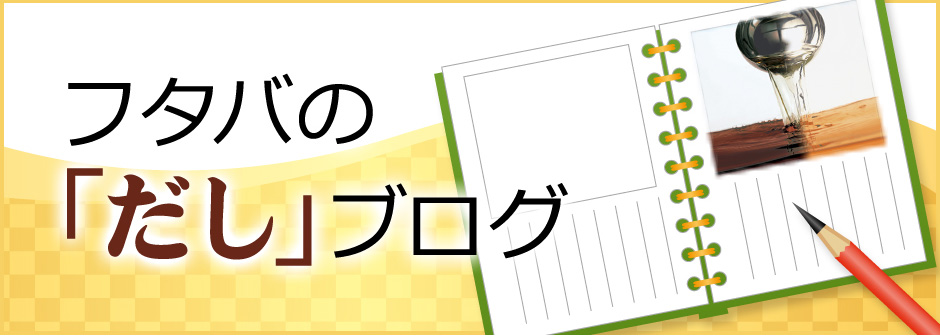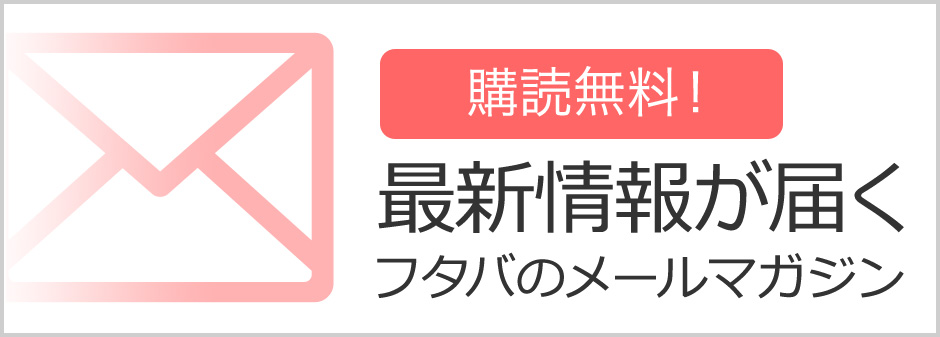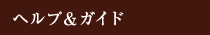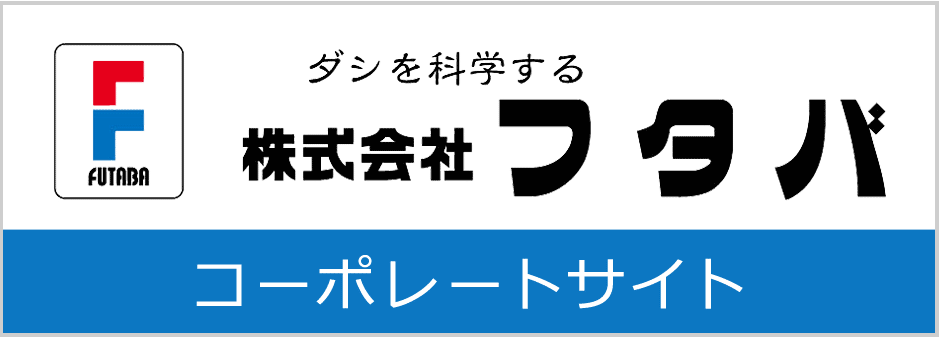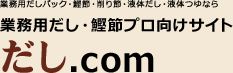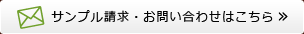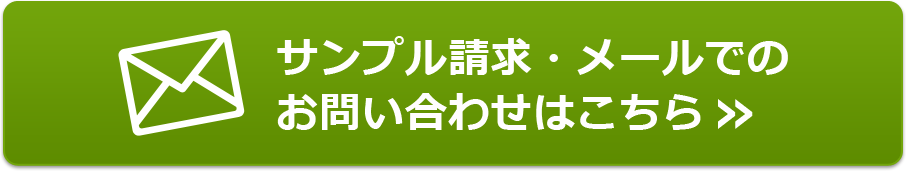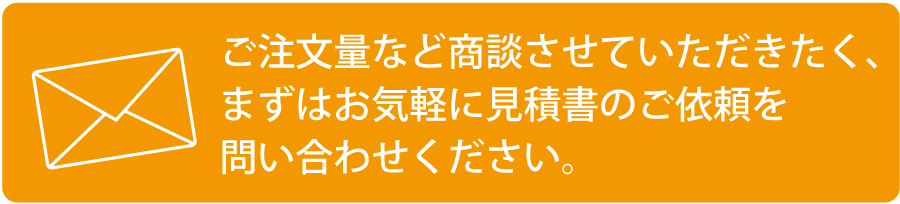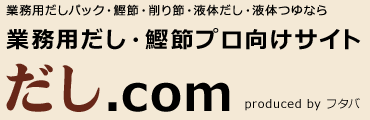毎日多くのうどんを提供する厨房では、うどんつゆ選びは大きな課題です。
コストと品質、そして味、どれを優先すべきか迷うことはありませんか?
最適なつゆを選べば、厨房の効率化とコスト削減、さらにはお客様満足度向上にも繋がります。
今回は、業務用うどんつゆ選びのポイントと、効果的な活用法をご紹介します。
厨房の負担軽減と利益向上を目指して、一緒に最適なつゆを探していきましょう。
業務用うどんつゆの選び方
予算と使用量の見極め
業務用うどんつゆは、価格帯や容量が様々です。
まず、1ヶ月あたりのうどん販売量や、1杯あたりのつゆ使用量を正確に把握しましょう。
そこから、1ヶ月に必要なつゆの量を計算し、それを基準にコストパフォーマンスの高い商品を選び出すことが重要です。
大量に使用する場合は、大容量タイプの方が単価が安くなる傾向があります。
しかし、保管スペースや賞味期限なども考慮する必要があります。
価格だけでなく、トータルコストを計算してみましょう。
味の濃さや風味の比較
関東風は濃口醤油を使用し、色が濃くしっかりとした味付けが特徴です。
一方、関西風は薄口醤油を使用し、透き通った色であっさりとした味付けです。
使用する醤油の種類だけでなく、昆布や鰹節などの出汁の種類や割合によっても味が大きく変わります。
サンプルを取り寄せ、実際に味見をして、お店のコンセプトやターゲット層に合った味を選ぶことが大切です。
また、かえしを使用するタイプとしないタイプがあり、かえしを使用するタイプは味の調整が容易です。
品質管理と安全性への配慮
業務用うどんつゆは、常に安定した品質を保つことが重要です。
製造メーカーの品質管理体制や、原材料の安全性についても確認しましょう。
HACCP対応など、食品衛生管理の基準を満たしているかどうかも重要なポイントです。
賞味期限や保存方法についても注意深く確認し、適切な保管方法で品質を維持しましょう。
賞味期限が近いものは優先的に使用し、在庫管理を徹底することが重要です。
関東風関西風の選択
地域性やお店の客層によって、関東風か関西風かを選択する必要があります。
関東風は濃い味が好まれる地域、関西風はあっさりとした味が好まれる地域など、地域差があります。
お店のターゲット層や、提供するうどんの種類に合わせて最適なものを選びましょう。
両方の味を用意し、お客様の好みに応えるという選択肢もあります。

業務用うどんつゆの効果的な活用
コスト削減のための工夫
つゆの濃度を調整することで、コスト削減を図ることができます。
かえしを使用するタイプであれば、出汁の量を調整することで、味の濃さを簡単に変えることができます。
また、つゆの使い回しは避け、衛生面にも注意しましょう。
無駄な廃棄を減らすため、正確な需要予測と在庫管理が不可欠です。
うどんつゆの応用レシピ
うどんつゆは、うどん以外にも様々な料理に使用できます。
例えば、煮物や丼つゆ、かけつゆとして活用できます。
創意工夫次第で、メニューのバリエーションを増やし、食材の無駄を減らすことも可能です。
スタッフにレシピを共有し、活用を促すことも効果的です。
保管方法と賞味期限管理
業務用うどんつゆは、直射日光や高温多湿を避け、冷蔵庫で保存することが重要です。
賞味期限を常に確認し、古いものから使用しましょう。
適切な保管方法を守れば、品質を維持し、食中毒のリスクを軽減できます。
在庫管理システムを活用し、賞味期限切れによる無駄をなくしましょう。

まとめ
業務用うどんつゆ選びは、コスト削減と顧客満足度の両立が求められます。
予算、使用量、味、品質、そして地域性を考慮し、最適なつゆを選び、効果的に活用することで、厨房運営の効率化と利益向上に繋げることが可能です。
この記事で紹介したポイントを参考に、賢く業務用うどんつゆを選び、お店の繁盛に役立ててください。
常に品質管理を徹底し、お客様に安全で美味しいうどんを提供しましょう。