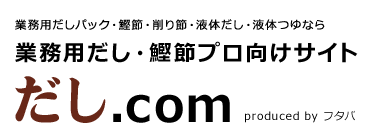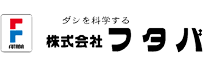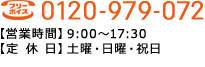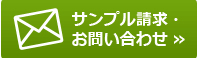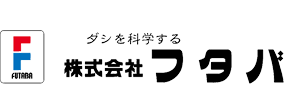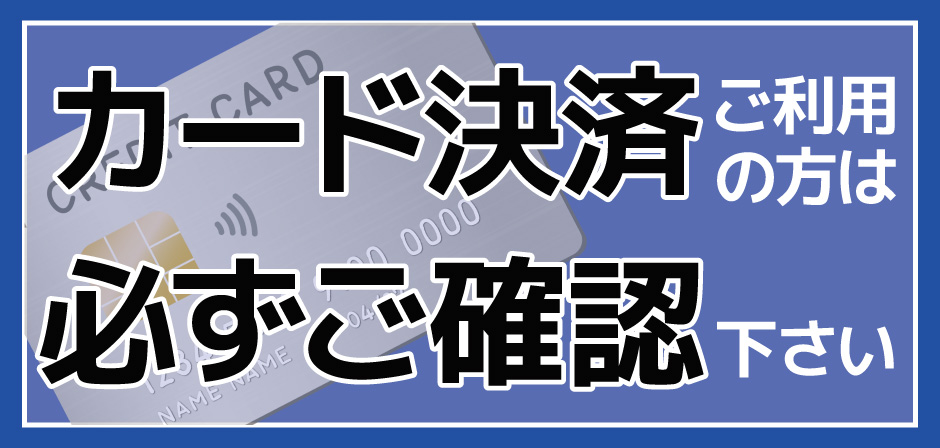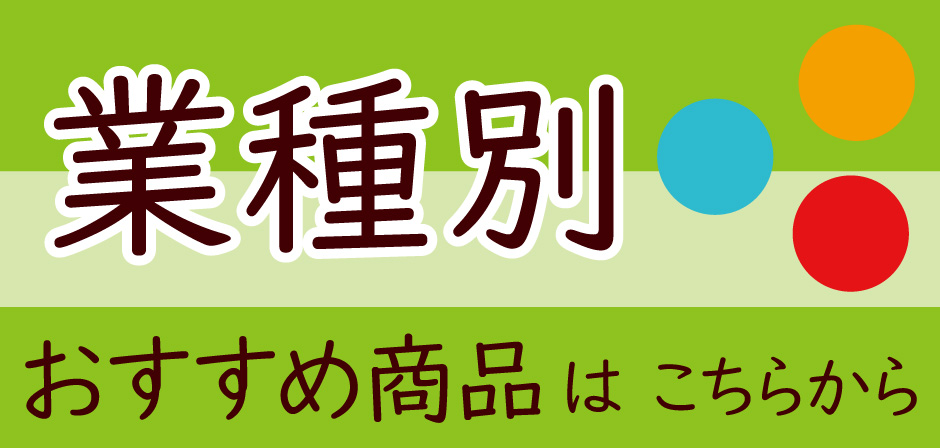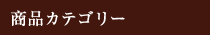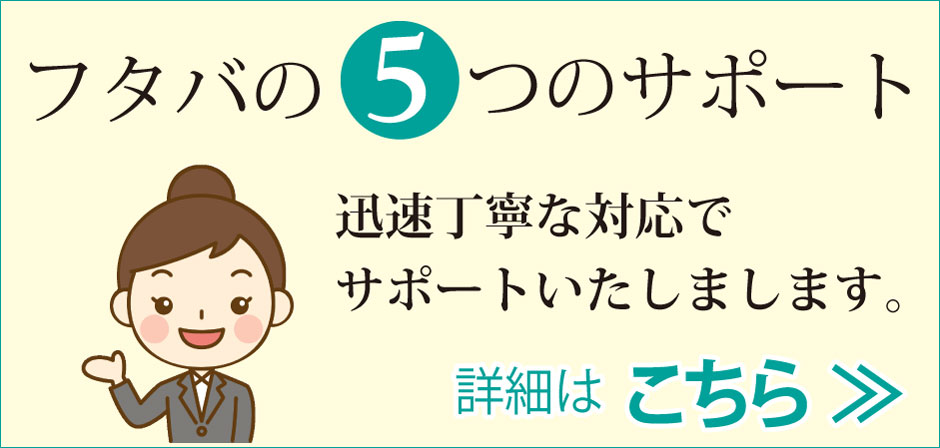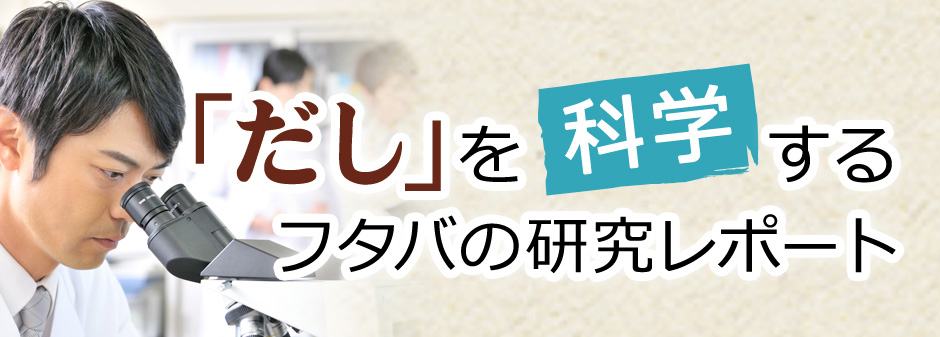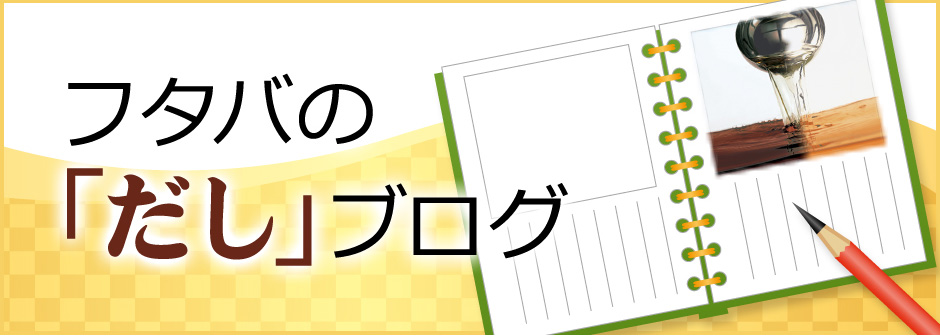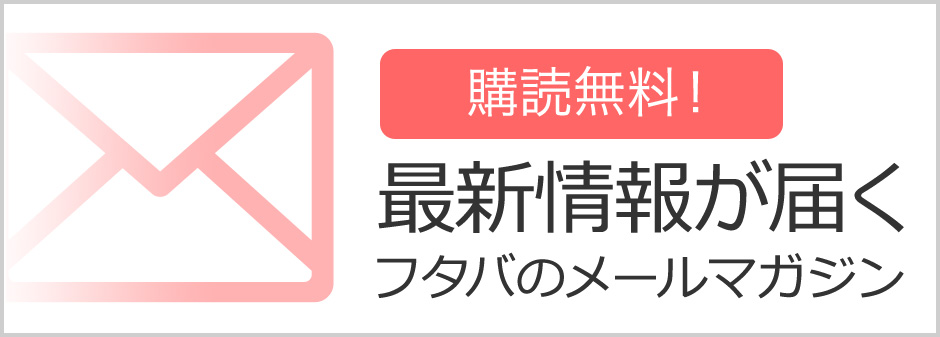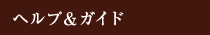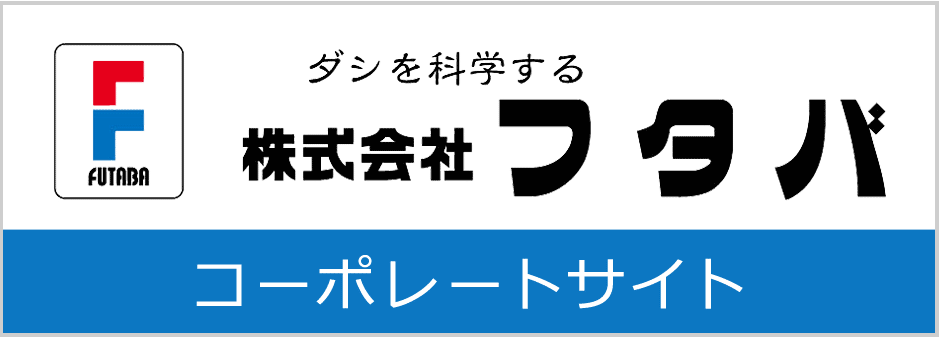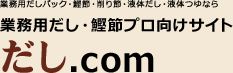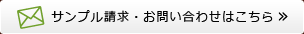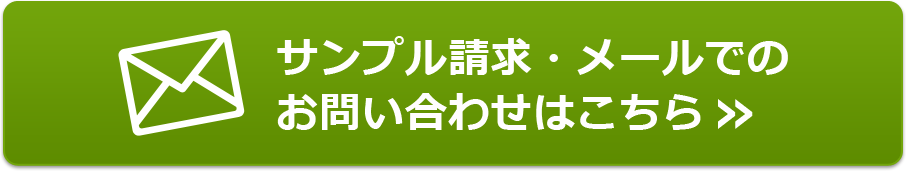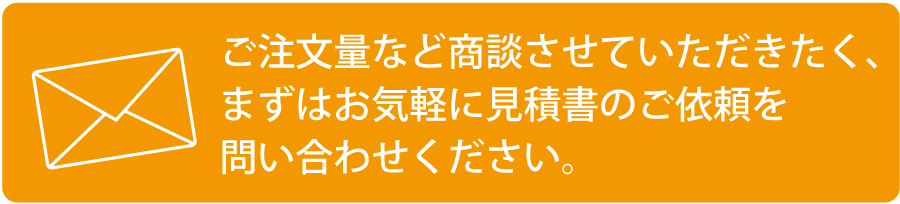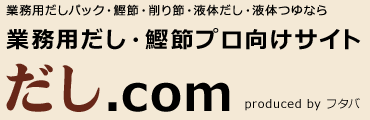お正月といえば、欠かせないのがお雑煮です。
地域によって様々なバリエーションがありますが、今回は関東風お雑煮に焦点を当てて、その特徴や作り方を解説します。
関東風お雑煮の特徴
醤油ベースで澄んだつゆ
関東風お雑煮は、醤油ベースの澄んだつゆが特徴です。
関西風のお雑煮のように白味噌を使うことはなく、醤油、みりん、塩などで味付けされた、あっさりとした上品な味わいが魅力といえます。
この澄んだつゆは、鶏肉と野菜から丁寧に取った出汁がベースになっています。
さらに、素材の旨みが凝縮されているため、具材本来の味をしっかりと楽しむことができるのです。
丸餅を使うのが一般的
関東風お雑煮では、丸餅を使うのが一般的です。
一方で、関西風お雑煮では角餅を使うことが多く、東西で違いが見られます。
丸餅の柔らかな食感と、澄んだつゆとの組み合わせが絶妙なバランスを生み出しているといえます。
餅のサイズは、お好みのものを使用できます。
しかし、大きすぎると食べにくくなるため、一口サイズにカットするのがおすすめです。
一口サイズにすることで、食べやすさが格段に向上します。
鶏肉と野菜の出汁でシンプルに味わう
関東風お雑煮は、鶏肉と野菜の出汁をベースに作られるため、素材の味がシンプルに楽しめます。
鶏ガラや鶏むね肉を使用し、大根、人参、里芋などの野菜と一緒にじっくりと煮込むことで、旨みのある深いコクが生まれます。
また、余計な調味料を加えず、素材本来の味を活かした、すっきりとした味わいが特徴です。
そのため、素材本来の旨みを最大限に引き出した、奥深い味わいを楽しむことができるのです。

関東風お雑煮の材料は何が必要?
鶏肉大根人参里芋など
鶏肉は、鶏ガラや鶏むね肉など、お好みの部位を使用できます。
鶏ガラを使う場合は、より深いコクのある出汁が得られます。
野菜は、大根、人参、里芋などが一般的です。
また、椎茸や白菜など、お好みの野菜を加えても美味しくいただけます。
これらの野菜は、大きめにカットすることで、煮崩れを防ぎ、食べ応えのあるお雑煮に仕上がります。
醤油みりん塩で味付け
関東風お雑煮の味付けは、醤油、みりん、塩が基本です。
醤油は、淡口醤油を使うと、より上品な仕上がりになります。
みりんは、甘みとコクをプラスします。
さらに、塩で味を調えることで、バランスの良い味わいに仕上がります。
これらの調味料の分量は、使用する材料や好みに合わせて調整してください。
もち菜三つ葉などの青菜はお好みで
仕上げに、彩りとしてもち菜や三つ葉などの青菜を加えるのもおすすめです。
これらの青菜は、さっと湯がいてから加えることで、鮮やかな緑色がつゆに映え、見た目にも美しいお雑煮になります。
青菜の爽やかな風味も加わり、より一層美味しくなります。
もちろん、青菜はあくまでもアクセントなので、無くても問題ありません。

関東風お雑煮の基本的な作り方
鶏肉と野菜で出汁をとる
まず、鶏肉と野菜を鍋に入れ、たっぷりの水を加えて火にかけます。
沸騰したらアクを取り除き、弱火でじっくりと煮込みます。
時間をかけて煮込むことで、鶏肉と野菜の旨みがしっかりと出汁に溶け込み、深みのある味わいが生まれます。
例えば、煮込み時間は、鶏ガラを使う場合は1時間以上、鶏むね肉の場合は30分程度を目安にしてください。
醤油ベースのつゆを作る
鶏肉と野菜の出汁がとれたら、醤油、みりん、塩で味を調えます。
出汁の量に合わせて、調味料の量を調整してください。
味見をしながら、自分好みの味に仕上げることが大切です。
餅を焼く
丸餅は、軽く焼いてからつゆに加えます。
焼くことで、餅の表面が香ばしくなり、つゆとの相性も良くなります。
また、焼きすぎると焦げてしまうため、弱火でじっくりと焼いてください。
盛り付ける
最後に、お椀に焼いた餅を入れ、つゆを注ぎます。
鶏肉と野菜を盛り付け、お好みで青菜を加えて完成です。
彩り豊かに盛り付けることで、見た目も食欲をそそる一品になります。
まとめ
関東風お雑煮は、醤油ベースの澄んだつゆと丸餅が特徴の、あっさりとした上品な味わいが魅力のお雑煮です。
鶏肉と野菜の出汁をベースに、シンプルな味付けで素材本来の味を楽しむことができます。
そのため、お正月の食卓にぴったりの一品といえます。
今回ご紹介した手順を参考に、ぜひご家庭で関東風お雑煮を作ってみてください。