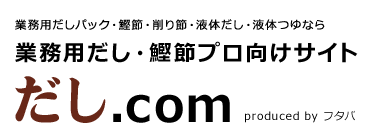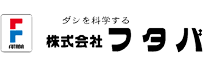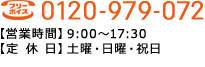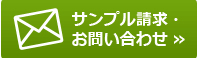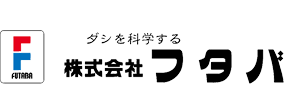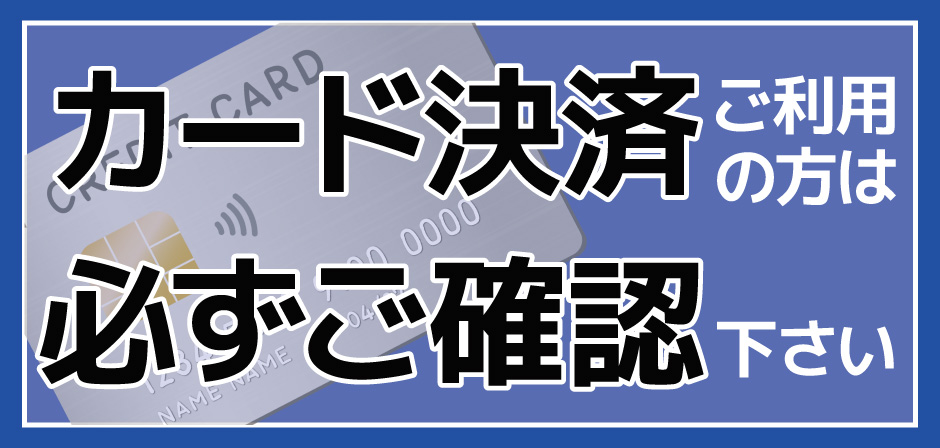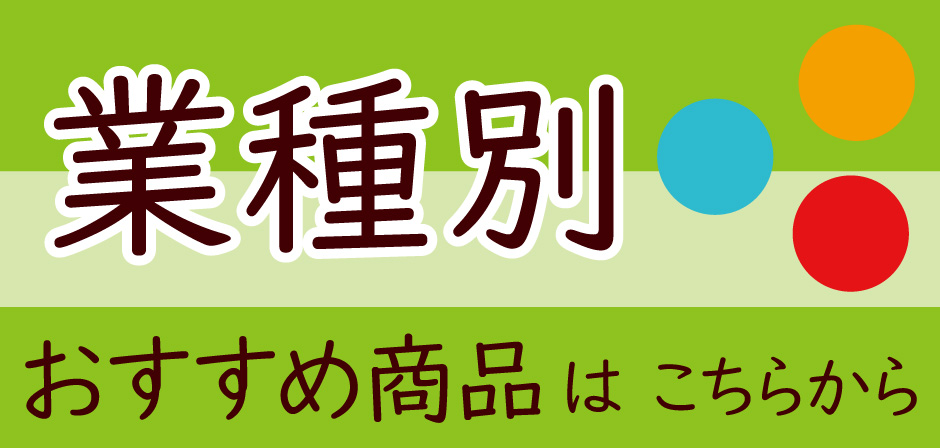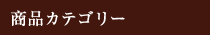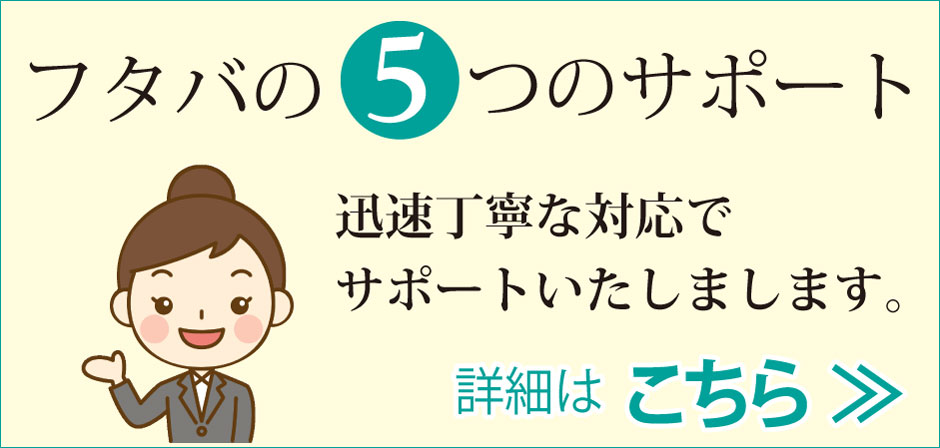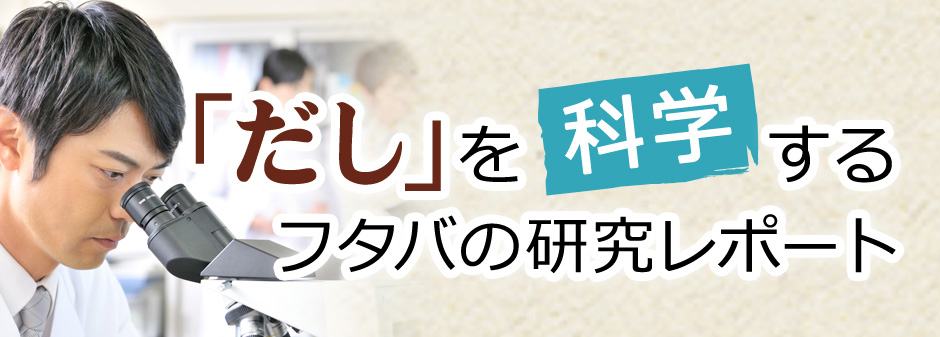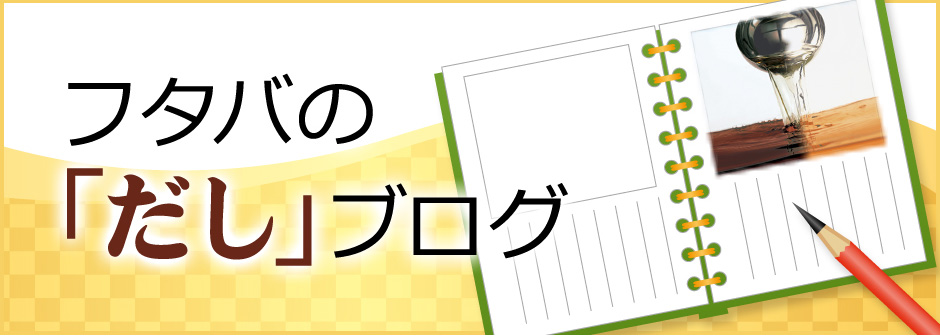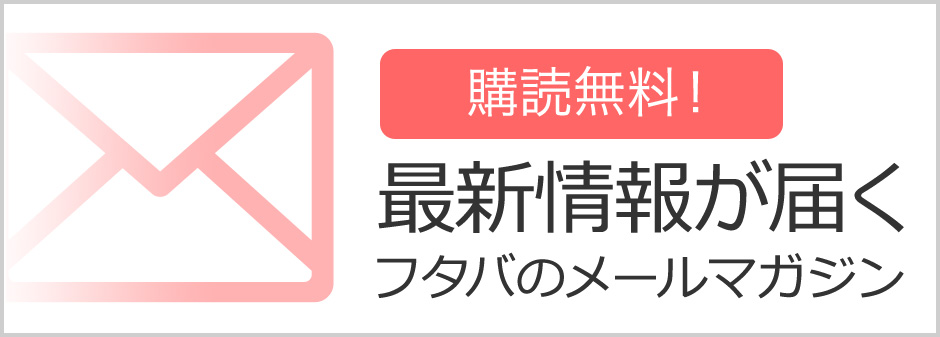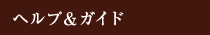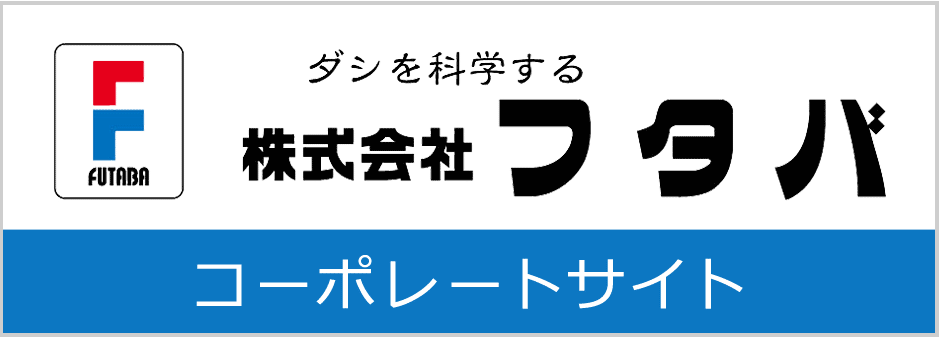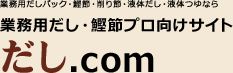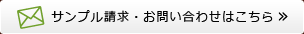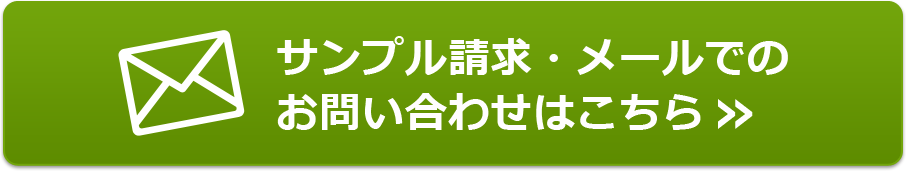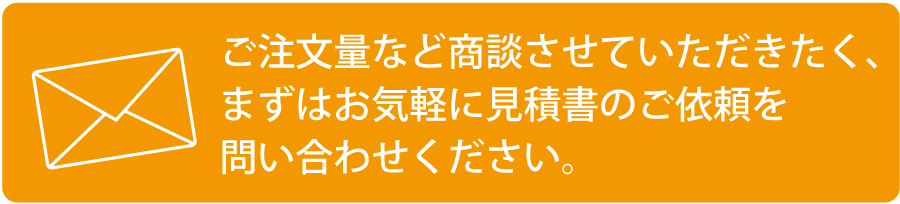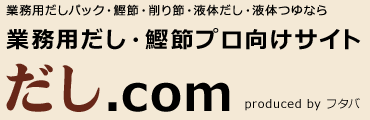飲食店経営において、「利益が思うように残らない」と感じる場面は少なくありません。
そうした悩みの背景には、原価率の高さやコスト管理の難しさが潜んでいます。
特に人手不足や仕入れ価格の変動など、変数の多い飲食業では、原価率のコントロールが経営の明暗を分ける要因にもなります。
本記事では、飲食店の原価率に関する基本的な知識と、濃縮出汁を活用したコスト削減のヒントをご紹介します。
日々の仕入れやメニュー開発に活かせる実践的な視点を提供します。
原価率の基本と飲食店が抱える課題
原価率の計算方法とFLコストの考え方
飲食店における「原価率」とは、売上に対する食材費の割合を示す指標です。
基本的な計算式は「原価率 = 食材費 ÷ 売上 × 100」で算出されます。
売上が同じでも食材費が高ければ利益は減るため、原価率の管理は収益の安定に直結します。
また、飲食店経営では「FLコスト」が重要視されます。
F(Food=食材費)とL(Labor=人件費)を合わせたもので、全体売上の55〜60%以内に収めるのが理想とされています。
これを超えると、利益が圧迫されやすくなります。
業態別の平均原価率とその違い
飲食店の原価率は業態によって大きく異なります。
たとえば、高級レストランでは30%以上の原価率が一般的である一方、居酒屋やカフェなどは25%前後が多い傾向にあります。
ラーメン店は25〜30%、和食店では30%超になることも珍しくありません。
この違いは、使用する食材の単価や提供する料理の性質によるものです。
したがって、自店舗の業態に合った原価率を理解し、それに見合う価格設計や仕入れ戦略を立てることが不可欠です。
ロス率・歩留まりが原価率に与える影響
原価率のコントロールでは、仕入れた食材をどれだけ無駄なく使えるかも鍵となります。
ロス率とは、仕入れた食材が廃棄される割合であり、これが高ければ食材費の無駄が増え、原価率も上昇します。
また、歩留まり(可食部率)も重要です。
たとえば野菜や肉などは、下処理によって実際に提供できる部分が限られます。
歩留まりの低い食材は実質的な原価が高くなるため、扱い方によっては原価率の上昇につながります。

濃縮出汁で原価率を下げる仕組み
濃縮出汁がもたらすコスト削減効果
濃縮出汁は、少量で深い旨味が出せるため、コスト削減に有効な素材です。
仕込み時間の短縮にもつながり、ガス代や水道代といった副次的な経費も抑えることができます。
また、素材に頼らず味の均一性を保てるため、ロスの低減にも寄与します。
天然素材を一から煮出す場合に比べ、歩留まりのばらつきが少ないのも利点です。
こうした要素が複合的に作用し、原価率の改善に大きく貢献します。
原価率改善における濃縮出汁の導入ポイント
濃縮出汁を活用する際は、用途に応じたタイプを選定することが重要です。
たとえば和風出汁ならば、そば・うどん・煮物などの料理に合わせて、味の濃さや香りのバランスが適したものを選ぶべきです。
導入前には、既存メニューにどのように組み込めるかをシミュレーションし、実際のコスト試算を行うことが効果的です。
また、スタッフへの調理指導も忘れてはなりません。適量を守ることが、味とコストの安定化に直結します。
濃縮出汁を活用したメニュー設計のコツ
濃縮出汁を使ったメニュー開発では、再現性の高さと原価率の抑制がポイントになります。
たとえば、ベースに出汁を使ったスープ料理や煮物、または丼ものは、少ない食材でも満足感を出しやすく、利益率も高くなりやすい傾向があります。
さらに、濃縮出汁をベースに複数のメニューを展開することで、在庫回転率の向上とロス削減も狙えます。
一つの素材を多用途に活かすという視点が、限られたリソースの中で利益を最大化する鍵となります。

まとめ
飲食店経営において、原価率のコントロールは継続的な課題です。
業態に応じた平均値を理解し、FLコストやロス率、歩留まりの観点から見直すことが必要です。
そこで有効な手段の一つが、濃縮出汁の活用です。
味の再現性やロス削減、調理の効率化といった多方面でコストダウンが期待できます。
まずは既存メニューに取り入れられる部分から導入を検討し、利益体質の強化を目指しましょう。