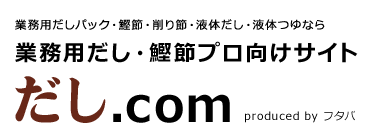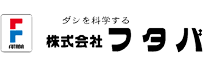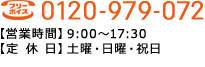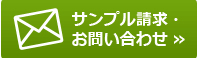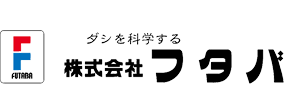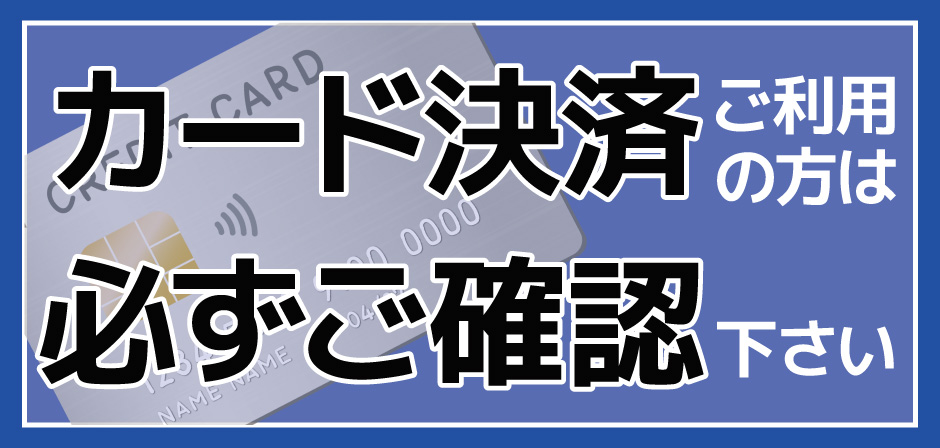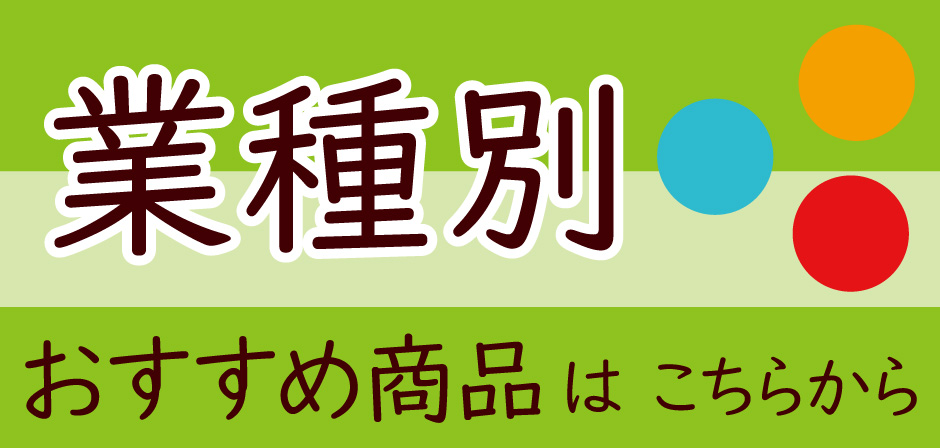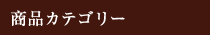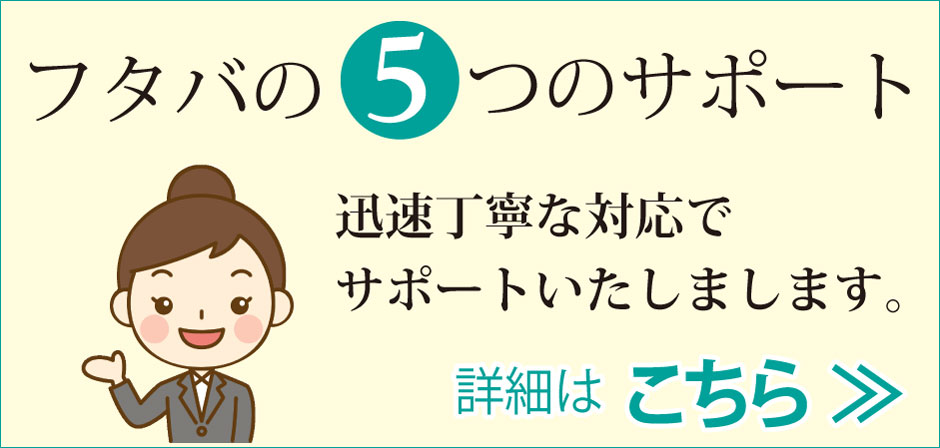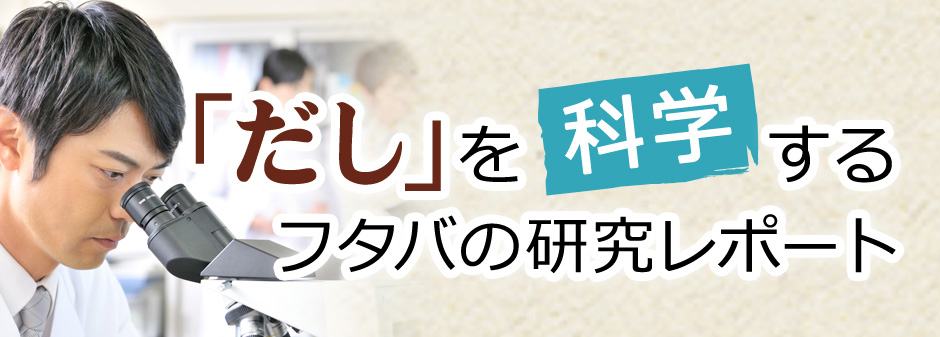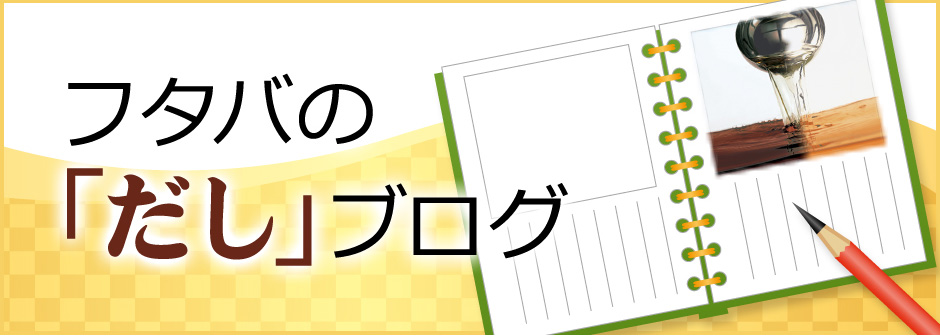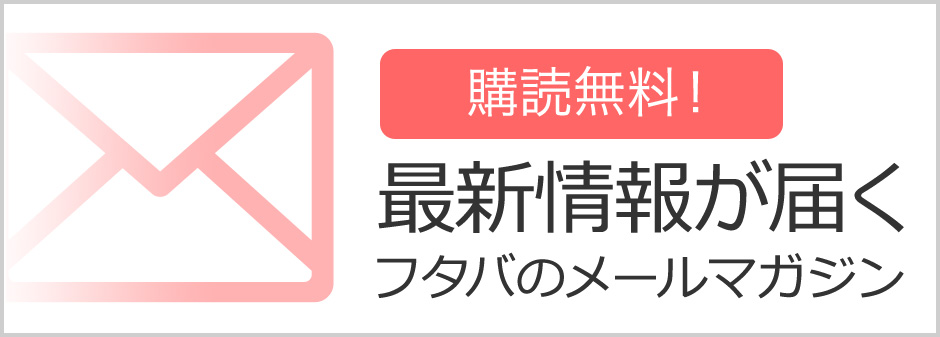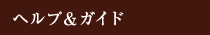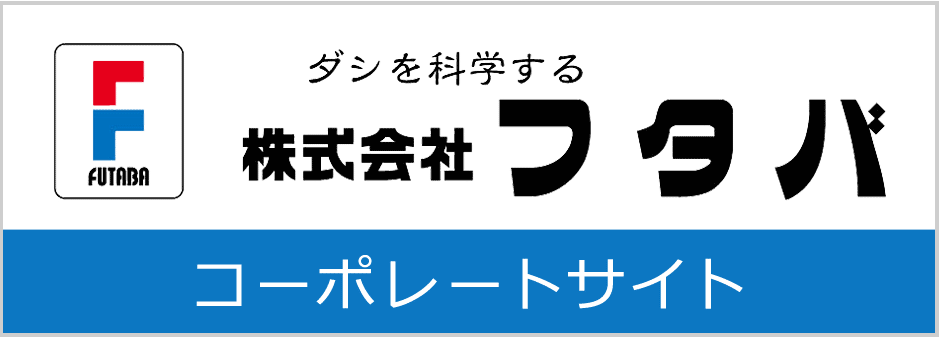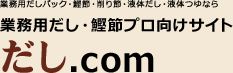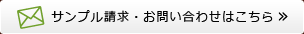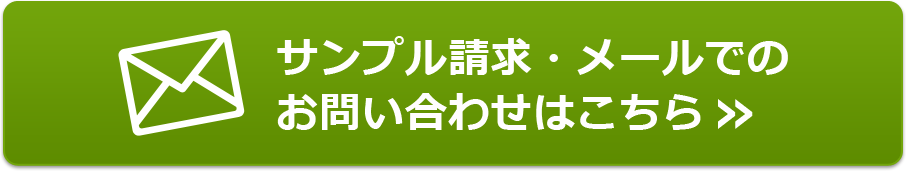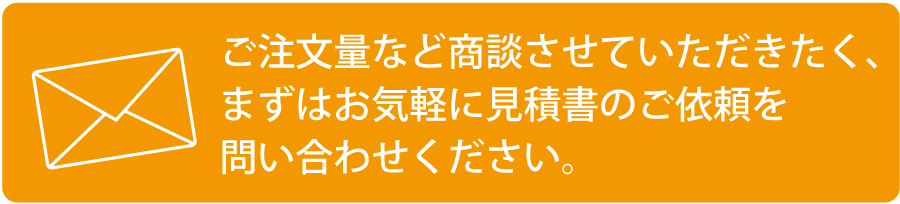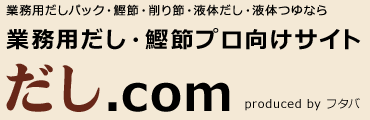飲食店の経営において、原価率の上昇は見過ごせない課題です。
日々の仕入れや調理工程の中で、少しずつコストが膨らんでいると感じる場面は多いかもしれません。
特に最近では、食材価格の変動や人件費の上昇が影響し、利益率を圧迫する要因となっています。
この記事では、原価率が上がる具体的な要因を整理し、それに対する有効な対策として「業務用濃縮だし」の活用方法をご紹介します。
日々のオペレーション改善のヒントとして、参考にしてみてください。
原価率上昇の主な要因とその影響
仕入れ価格の高騰とその影響
昨今、食材の価格は安定せず、特に輸入原材料や水産物などは価格が大きく変動します。
この影響を直接受けるのが飲食店の仕入れコストです。
仕入れ先の選定や価格交渉がうまくいかないまま放置すると、原価率はじわじわと上昇していきます。
結果として、売上に対するコスト比率が悪化し、利益が圧迫される形になります。
歩留まりの低下による原価率の上昇
調理工程でのロスや食材の無駄も、原価率上昇の大きな原因です。
食材のカットミス、余分な廃棄、保存状態の悪化などが重なると、食材を本来の用途に使い切れず、結果として歩留まりが悪化します。
歩留まりの低下は見えにくいコストですが、積み重なると大きな影響をもたらします。
メニュー構成の不均衡がもたらす原価率の上昇
高コストのメニューが売れ筋となっている場合や、売価設定が原価に見合っていない場合、全体としての原価率が高くなる傾向があります。
また、人気メニューに原価が偏っていると、いくら他のメニューで調整しても収支バランスは崩れがちです。
メニュー構成と売上比率を見直すことが重要です。
FLコスト(原価+人件費)の管理の重要性
原価だけでなく、人件費も含めたFLコストのバランスが取れていないと、店全体の利益率が悪化します。
例えば、調理工程が複雑で人手がかかるメニュー構成になっていると、人件費が増加し、結果としてFLコストが高止まりしてしまいます。
業務の効率化と連動した原価率管理が求められます。

業務用濃縮だしを活用した原価率改善策
業務用濃縮だしの特徴と利点
業務用濃縮だしは、安定した品質と長期保存が可能な点が特長です。
分量の調整が容易で、味のブレを防ぎながらも、仕込みにかかる手間を軽減できます。
必要な分だけ使えるため、食材ロスも削減可能です。
また、他の原材料と比べて単価が安定しているため、コスト管理がしやすくなります。
業務用濃縮だしを活用した仕入れコストの削減方法
だし素材を一から仕込む場合、昆布や鰹節といった材料費に加え、時間と人件費もかかります。
濃縮だしを使えば、こうした仕込みの手間を省略でき、仕入れる原材料の種類も絞れるため、仕入れ総額の削減につながります。
必要量を調整して無駄なく使える点も、コスト削減に貢献します。
業務用濃縮だしを活用した歩留まりの改善方法
濃縮だしは液体またはペースト状で提供されるため、計量や保管が簡単です。
食材のように皮を剥く、カットするなどの処理が不要で、仕込みロスが出ません。
また、保存性が高いため、使いきれずに廃棄するといった無駄も防げます。
結果として、歩留まり率を高く維持することが可能です。
業務用濃縮だしを活用したメニュー構成の最適化方法
濃縮だしを使えば、複数のメニューに共通して使える「ベースの味」を確保できます。
これにより、少ない食材数で多様なメニュー展開ができ、原価の分散効果が得られます。
また、味の調整がしやすくなることで、客単価に合わせた売価設定もしやすくなり、メニュー全体の原価率を安定させることができます。
業務用濃縮だしを活用したFLコストの管理方法
濃縮だしの導入により、調理工程の簡略化が可能になります。
これにより、熟練スタッフでなくても一定の味を再現できるようになり、人件費の最適化が図れます。
また、仕込みや調理時間の短縮により、スタッフの稼働時間を減らすことも可能です。
結果として、FLコスト全体の見直しと最適化が実現できます。

まとめ
飲食店における原価率上昇の要因は多岐にわたり、それぞれが収益構造に影響を与えています。
仕入れ価格の変動や歩留まりの低下、メニュー設計の偏りといった問題に対し、対策を講じることが不可欠です。
そこで有効な手段のひとつが、業務用濃縮だしの活用です。
調理の効率化とともに、仕入れや人件費の最適化にもつながるため、全体としての原価率改善が期待できます。
日々の業務の中に取り入れやすく、効果も持続しやすい点が大きな魅力です。