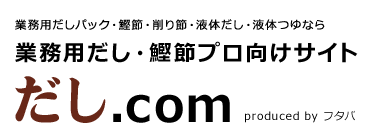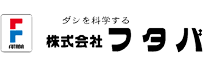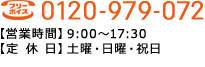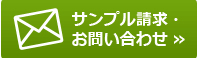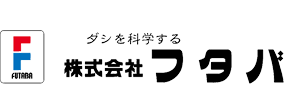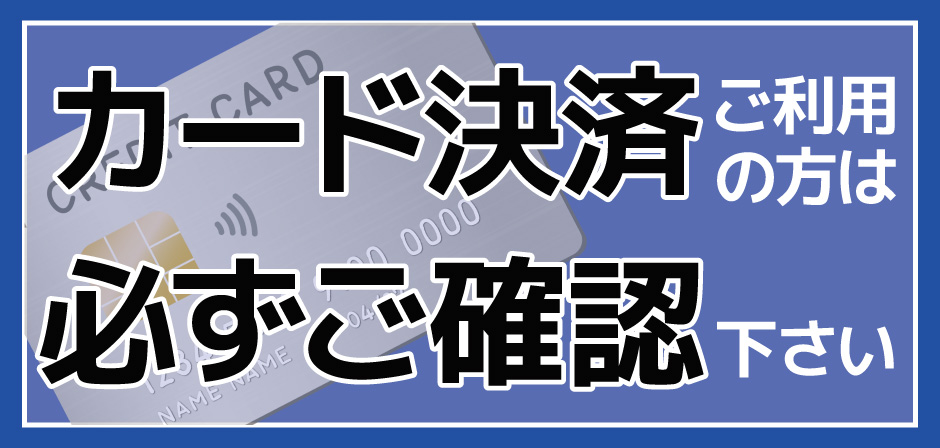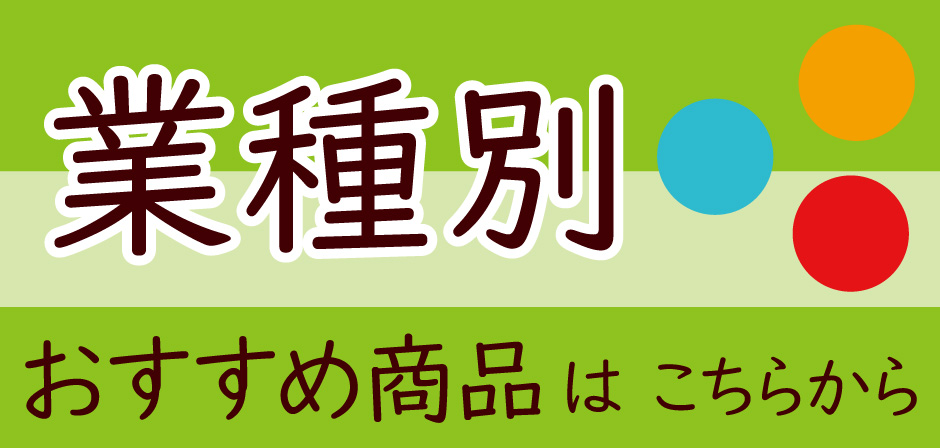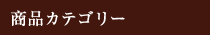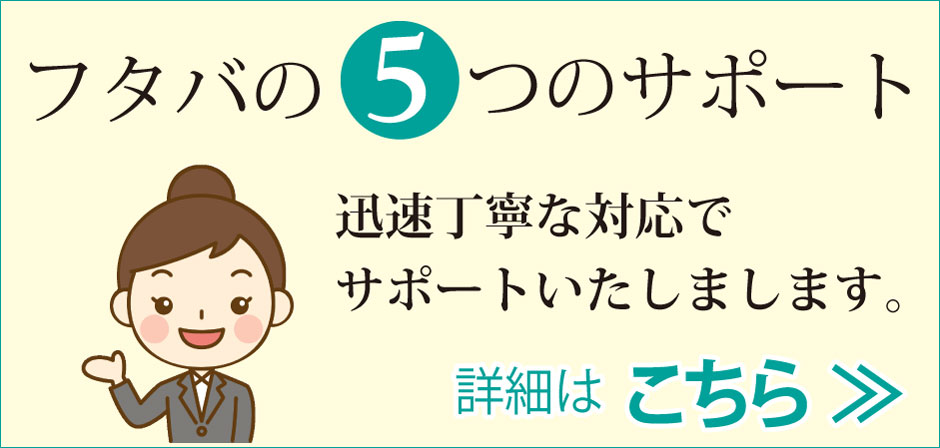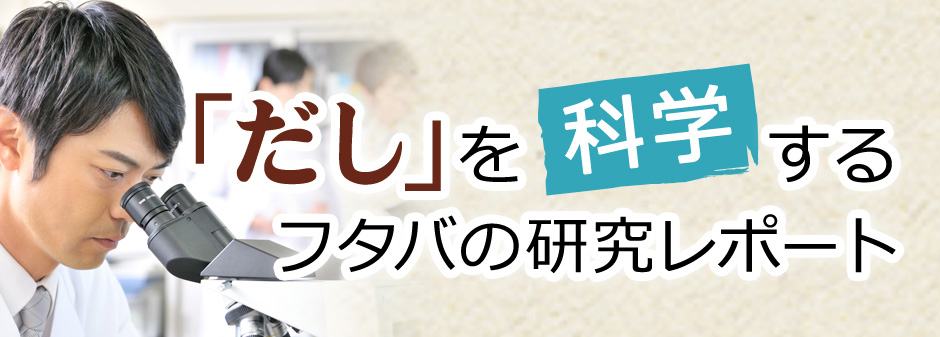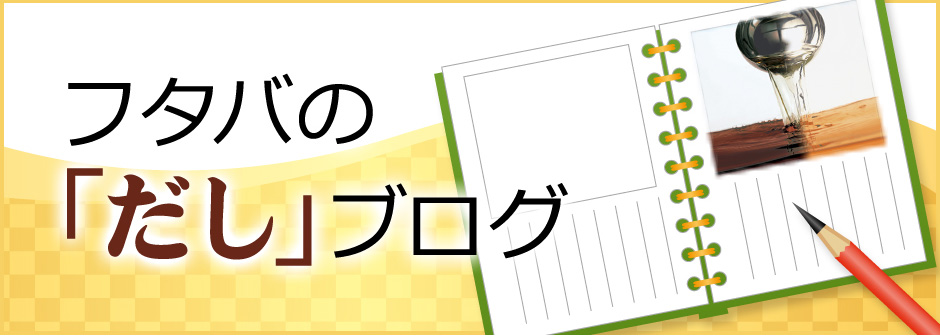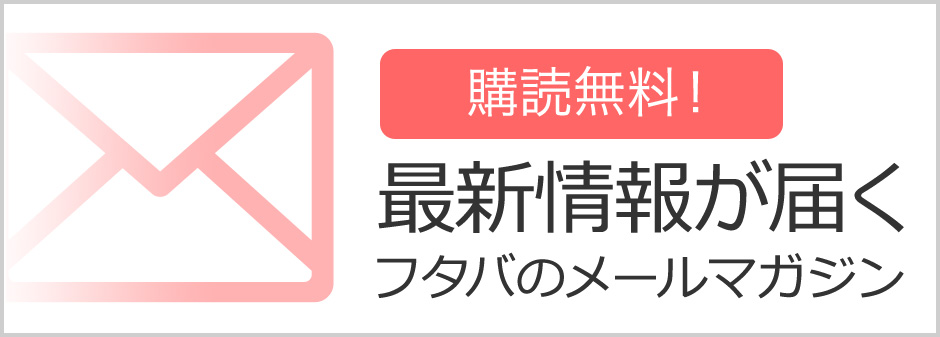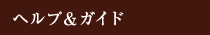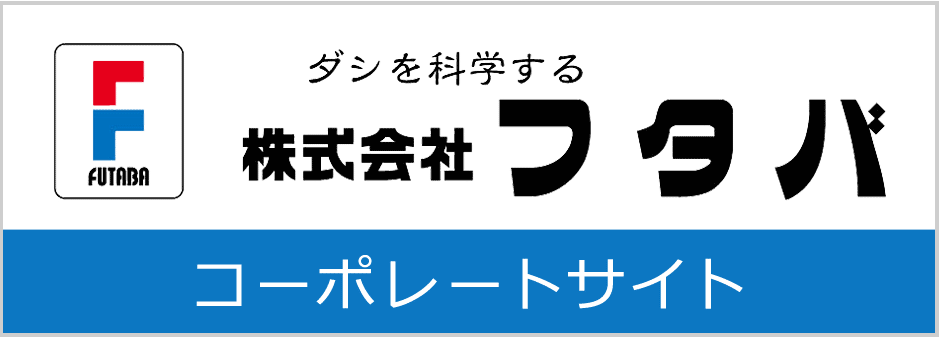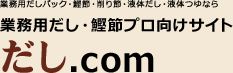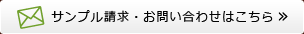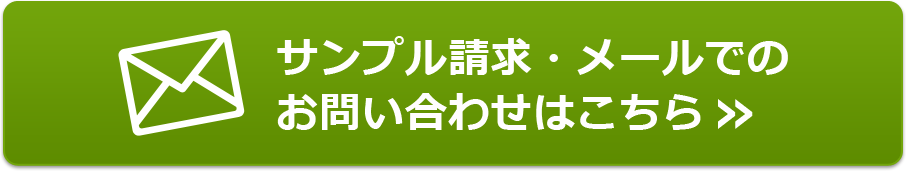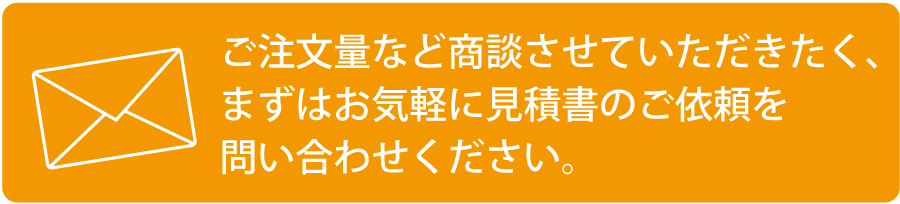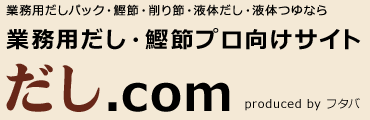飲食店の経営において、原価率は重要な指標の一つです。
適切に管理することで利益の最大化に繋がりますが、実際には計算やメニュー構成に悩むことも少なくありません。
この記事では、原価率の基本的な考え方から、メニュー戦略に活かす方法までを取り上げます。
さらに、コスト削減と食品ロス改善に効果的な濃縮出汁の活用法についてもご紹介します。
飲食店の原価率を正しく理解しメニューに活かす方法
飲食店原価率の基本計算と管理のポイント
原価率とは、売上に対する原材料費の割合を示す指標です。
具体的には、原材料費を売上高で割った数値で表されます。
例えば、売上が100万円で原材料費が30万円なら、原価率は30%です。
適切な原価率の設定は業態やメニューによって異なりますが、一般的には25%から35%が目安とされています。
原価率の管理は、材料の仕入れ価格や使用量を正確に把握することが基本です。
また、仕入れ先の選定や発注頻度の調整もコストコントロールには欠かせません。
定期的に原価率を計算し、目標値と比較して改善点を探ることが重要です。
メニュー構成が原価率に与える影響とは
メニューの構成は原価率に大きく影響します。
原価率の高いメニューばかり揃えると利益が圧迫されるため、バランスが求められます。
価格設定の際には、原価率だけでなく調理時間や販売数、客単価との関係も考慮しましょう。
また、季節や仕入れ状況によって材料費が変動するため、柔軟にメニューの見直しを行うことが求められます。
メニューの見直しには、原価率が高いメニューの材料を見直すほか、利益率の高いメニューの割合を増やす工夫も効果的です。
結果的に全体の原価率を適正に保ちながら、顧客満足も高められます。

濃縮出汁を活用して原価率を下げるメニュー戦略
濃縮出汁の特徴と原価削減効果
濃縮出汁は、素材の旨味を凝縮した調味料であり、使用量を抑えつつ味をしっかり出せるのが特徴です。
これにより、食材の無駄遣いを減らし、原材料費の削減に繋がります。
液体や粉末タイプがあり、調理の手間を減らしつつ均一な味付けが可能です。
濃縮出汁を使うことで、安定した品質を保ちながらもコストをコントロールできるため、原価率改善に寄与します。
また、保存期間が長いため仕入れ頻度を減らせ、在庫管理の負担軽減にもつながります。
食品ロス改善に役立つ濃縮出汁の使い方
濃縮出汁は、使用する量を正確に調整できるため、食材の過剰使用や廃棄を防げます。
メニューごとに適切な分量を設定すれば、無駄な材料の発注や余剰在庫を減らすことが可能です。
さらに、調理の効率化により、余った材料を使い切る工夫もしやすくなります。
これにより、食品ロスの削減と原価率の低減が同時に実現します。
特に飲食店など業務用の現場では、調理のムラを防ぎながらコスト管理を強化できる点が大きなメリットです。

まとめ
飲食店の原価率は、売上と原材料費のバランスを取ることで利益向上につながります。
計算方法や管理ポイントを理解し、メニュー構成を適切に調整することが重要です。
さらに、濃縮出汁を活用することで、原材料費を抑えつつ味の品質を保てます。
食品ロスの削減にも寄与するため、経営効率の改善に役立ちます。
こうした工夫を積み重ねることで、持続的な店舗運営が可能になるでしょう。