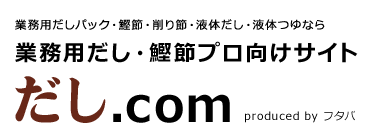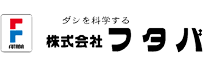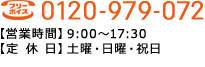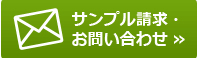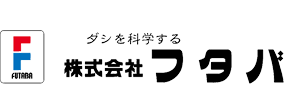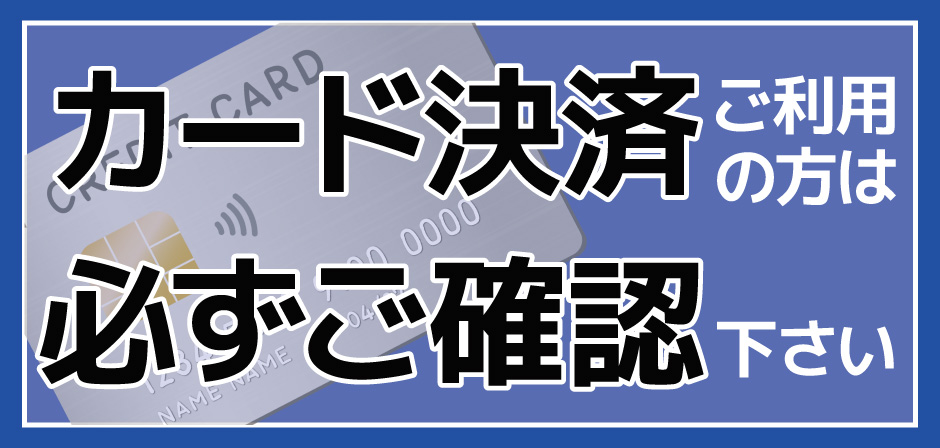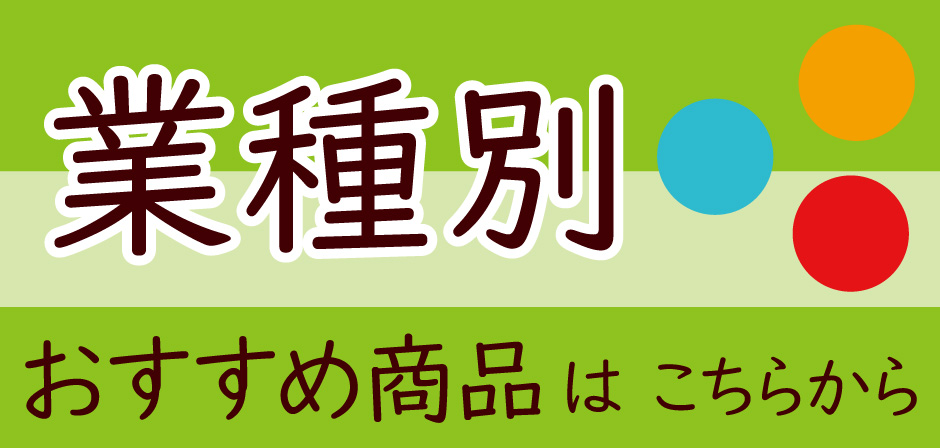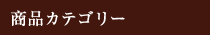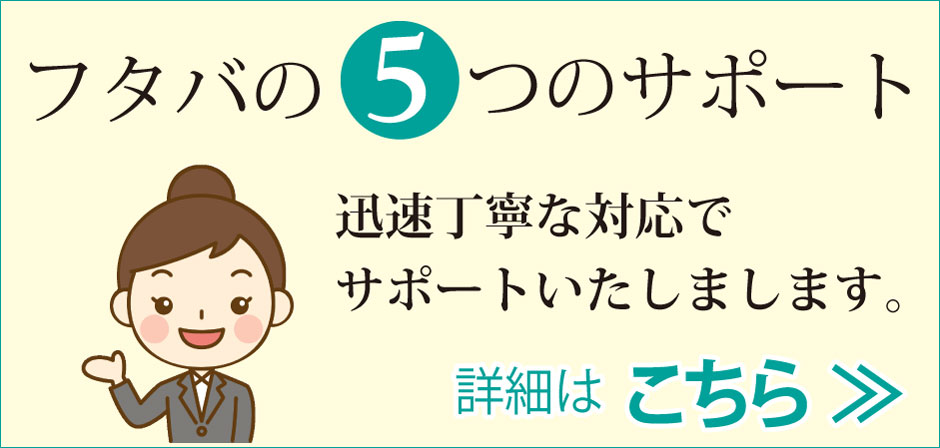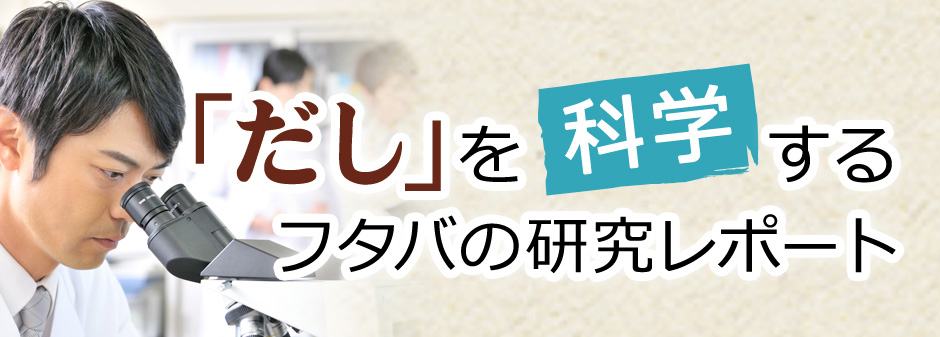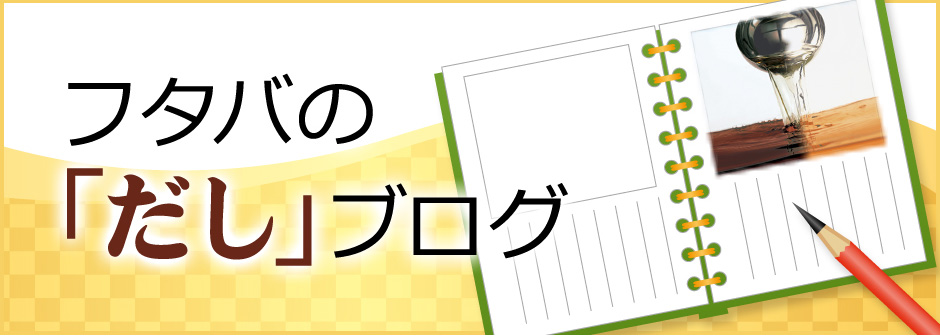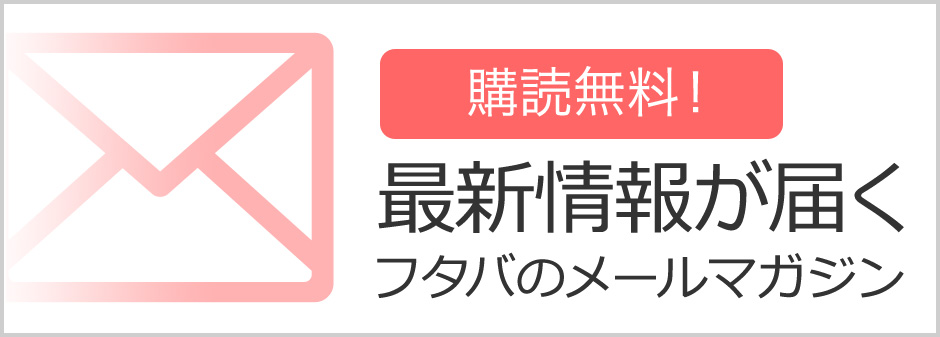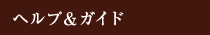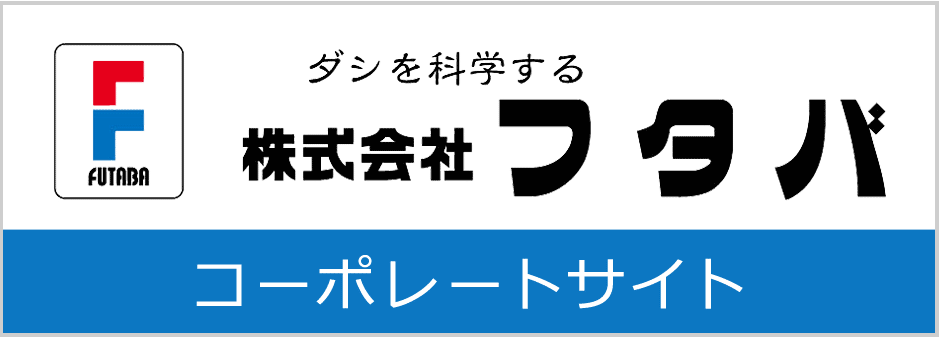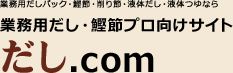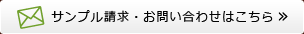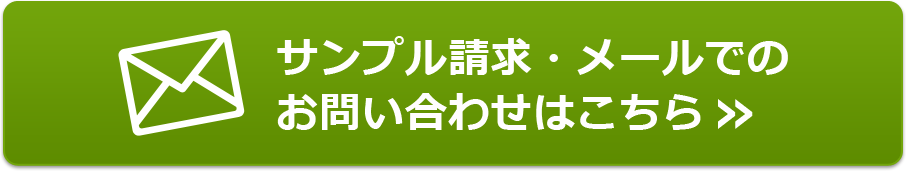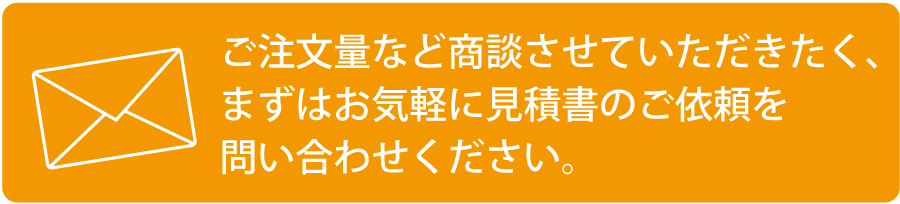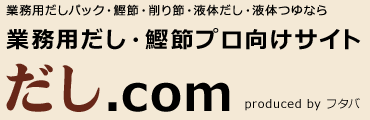飲食店にとって、原価率の最適化は経営の要ともいえる課題です。
売上があっても利益が出なければ、事業の持続は困難です。
特に、物価や人件費の上昇が続くなかで、どのようにして高品質かつ収益性の高いメニューを構成すべきか悩んでいる方も多いでしょう。
この記事では、原価率の基本的な考え方を踏まえつつ、濃縮出汁を活用した実践的なメニュー開発の考え方をご紹介します。
メニュー開発のコツを理解するための基本視点
メニュー開発における目的設定と方向性の考え方
メニュー開発に着手する前に、まず「何のために新しいメニューをつくるのか」という目的を明確にする必要があります。
売上向上、客層拡大、ランチ帯の強化など、狙いが異なれば選ぶ食材や価格帯も変わってきます。
目的に応じた方向性が決まることで、ブレのない開発が可能になります。
たとえば、回転率を上げたいなら提供スピードが重視され、粗利重視なら原価の安定性が求められます。
目的が曖昧なままでは、仕入れもオペレーションも非効率になり、結果的に原価率も上昇してしまいます。
顧客ニーズと競合動向を把握するためのリサーチ手法
現場感覚だけに頼らず、定量的なリサーチを行うことが求められます。
既存顧客からの声やSNS上の反応、さらに近隣競合のメニュー構成や価格帯を調査することで、自店が提供すべき価値が明確になります。
また、時間帯別の注文傾向や客単価を把握することで、最適な提供タイミングやセット構成も見えてきます。
競合との差別化ポイントを見出すためにも、リサーチは欠かせないステップです。
原価と売上データに基づくメニュー分析の基本
メニューごとの売上と原価を見える化することで、どのメニューが利益貢献しているか、どれが足を引っ張っているかが明らかになります。
食材単価だけでなく、ロスや仕込みにかかる人件費も含めた「実質原価率」で考えることが重要です。
売れているのに利益が出ていないメニューや、利益率は高いが回転率が悪い商品など、データをもとに改善余地を洗い出せます。
これにより、全体の収益構造を整えることが可能になります。

濃縮出汁を活用した効率的なメニュー開発の実践法
食材共通化によるロス削減とメニュー展開の工夫
濃縮出汁を使えば、味のベースを統一しつつ複数のメニューに展開できるため、食材の共通化が進みます。
たとえば、同じ出汁を使って煮物、うどん、炊き込みご飯などに応用できるため、仕入れと在庫管理が効率化します。
このように、限られた素材から多様なメニューを生み出すことで、食品ロス削減と原価率の安定を同時に実現できます。
特に、小規模店舗ではこのアプローチが大きな武器となります。
味の安定化と時短調理を実現する濃縮出汁の活用方法
濃縮出汁は調理の時短にも大きく寄与します。
再現性の高い味付けが可能になるため、仕込みの時間短縮だけでなく、スタッフ間での味ブレも防げます。
これにより、サービス提供時間の短縮と顧客満足の向上を両立できます。
また、濃縮タイプならストックしやすく、調整も自在なため、仕入れロスも最小限に抑えられます。
原価率の管理とともに、オペレーション効率の改善にもつながるのが利点です。
濃縮出汁を使ったメニュー設計の考え方と組み立て例
濃縮出汁を活かしたメニュー設計では、「主菜+副菜+主食」といった定番の組み立てをベースにしつつ、出汁の風味で統一感を持たせることがポイントです。
例えば、だし巻き玉子・煮物・だし茶漬けなど、出汁を軸に構成することで、統一感と調理効率の両立が可能になります。
また、ベースを同じにしつつトッピングや盛り付けを変えることで、異なるメニューとして見せる工夫も有効です。
こうした設計により、原価率を管理しながら魅力的なメニューラインアップを実現できます。

まとめ
原価率の適正化は、飲食店経営の土台を整えるうえで欠かせない課題です。
そのためには、目的設定やリサーチ、データ分析など基本的な視点を押さえることが出発点になります。
さらに、濃縮出汁を活用することで、調理の効率化・味の統一・原価率の安定といった複数の効果が得られます。
日々のメニュー開発において、戦略的にこうした要素を取り入れることで、持続可能で収益性の高い店舗運営につながります。