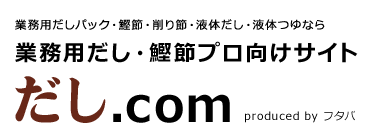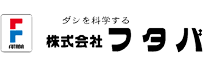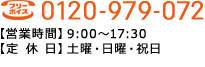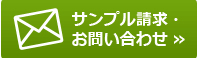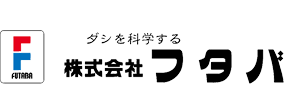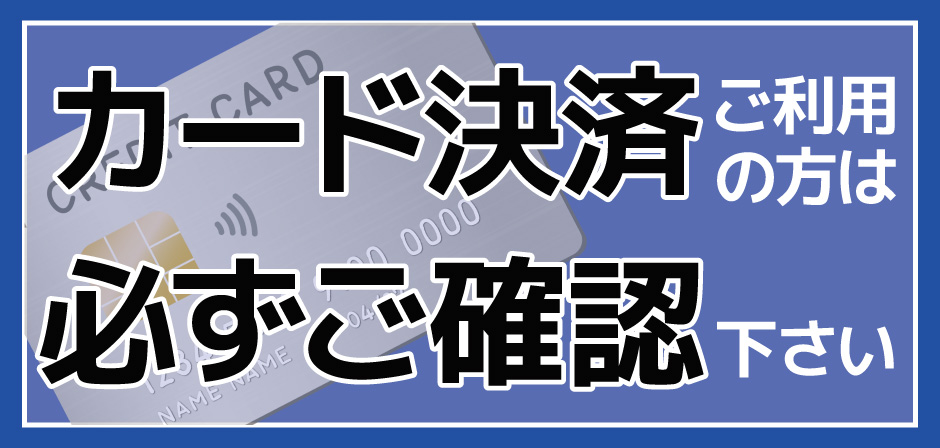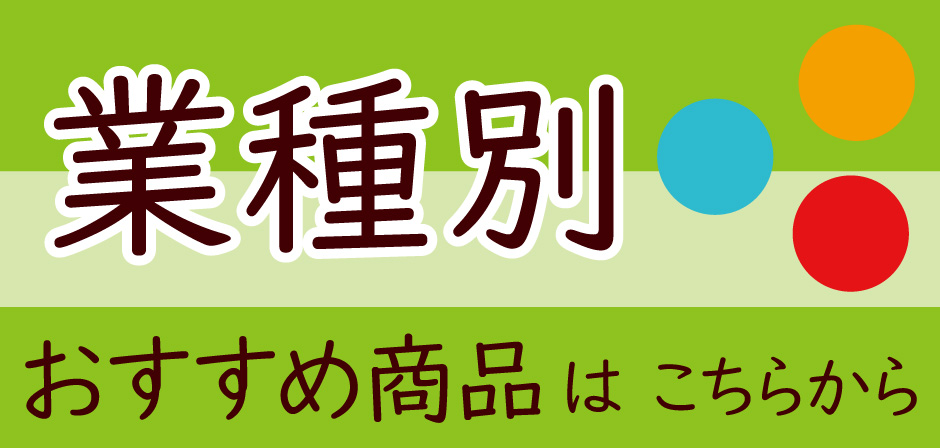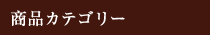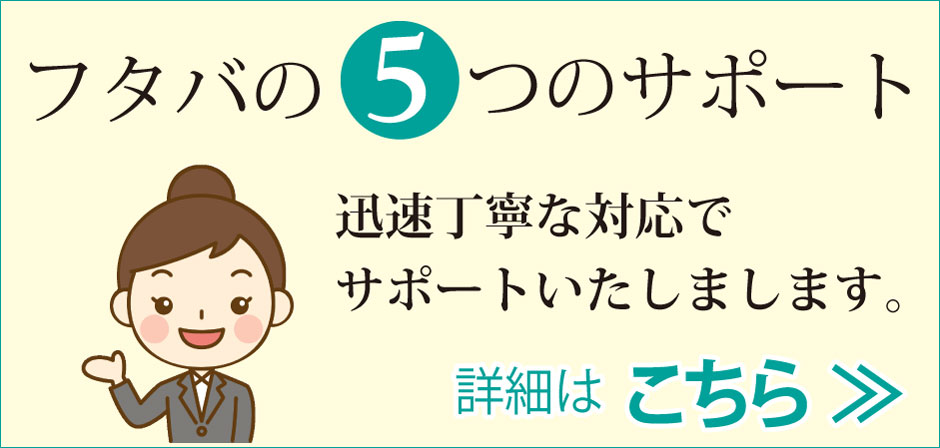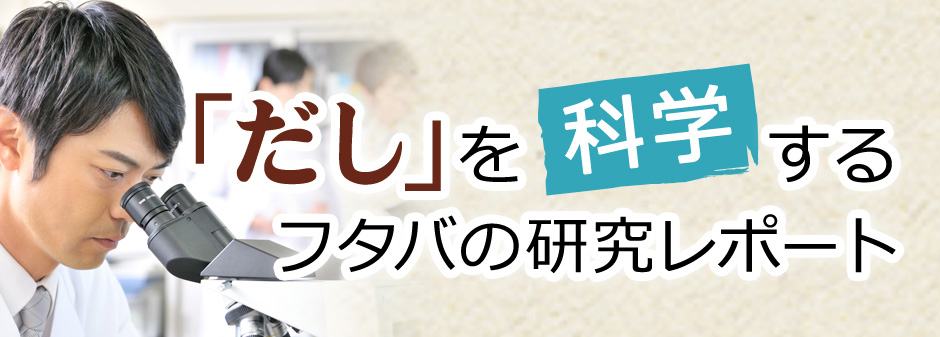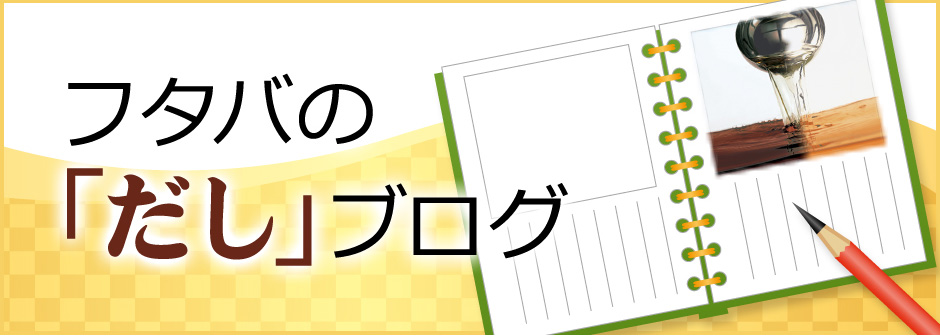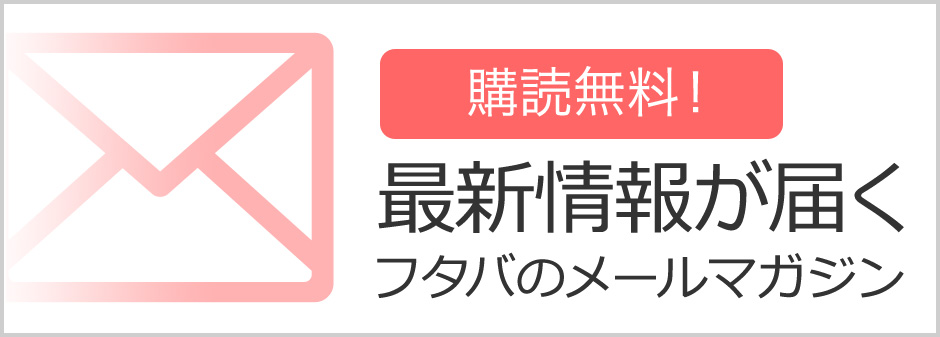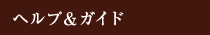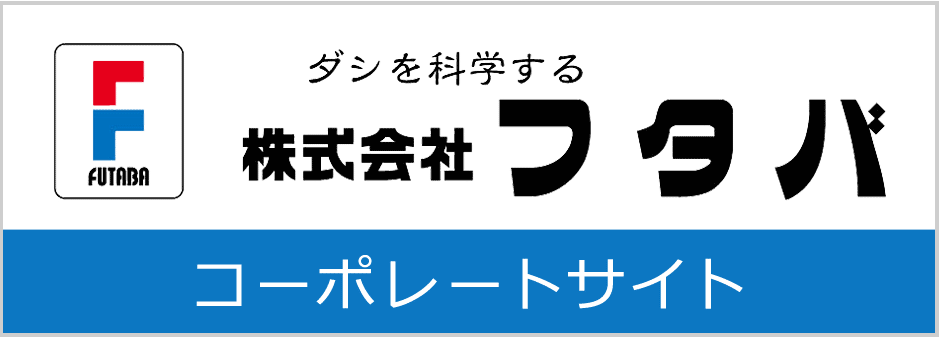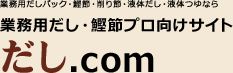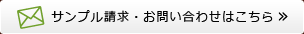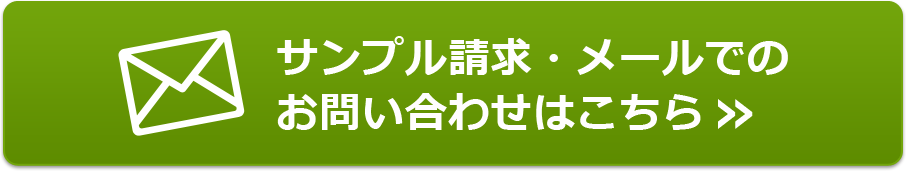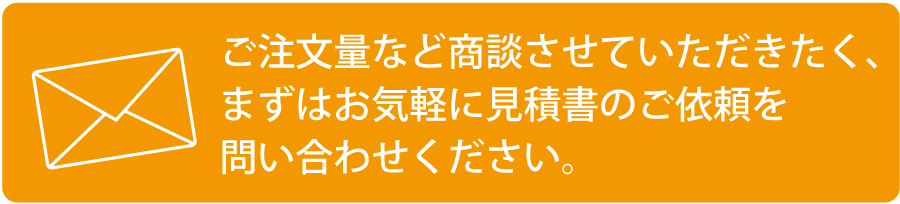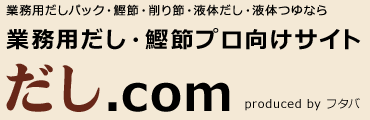飲食店の運営において、食品ロスは利益を圧迫する大きな要因の一つです。
仕入れた食材が使い切れず廃棄される、注文された料理が食べ残されるなど、ロスの形はさまざま。
特に近年は環境問題への配慮やコスト意識の高まりから、食品ロスへの対策は避けて通れないテーマとなっています。
本記事では、飲食店が実践できる食品ロス削減のためのメニュー設計と、その具体的な見直し方法をご紹介します。
食品ロス削減のためのメニュー設計
食材管理と仕入れの最適化
仕入れの量とメニュー内容が一致していないと、食材が余って廃棄につながるリスクが高まります。
まずは、食材ごとの使用頻度を洗い出し、使用量に基づいて仕入れ量を調整しましょう。
複数のメニューで共通して使用できる食材を積極的に選ぶことで、在庫の回転を早めることができます。
また、在庫の可視化もポイントです。
システムや管理表を活用し、日々の使用状況を明確に把握しておくと、ロスの兆候を早期に発見できます。
顧客の食べ残しを減らすメニュー構成
食べ残しが多いメニューには何らかの理由があります。
ボリュームが多すぎる、味のバランスが偏っている、盛り付けが食べづらい。
こうした点を見直すことで、顧客の満足度を保ちながら食品ロスを減らすことが可能です。
過去の注文データをもとに、食べ残しが多かった料理の傾向を把握し、改善につなげましょう。
メニューの写真や説明文を工夫することで、事前に量や内容がイメージしやすくなり、ミスマッチの防止にも役立ちます。
食べ切れる量を提供する工夫
メニューごとに量の選択肢を用意することも有効です。
「ハーフサイズ」「少なめオプション」などを設けることで、顧客が自分に合った量を選びやすくなります。
また、セットメニューの構成も見直しが必要です。
無理に品数を増やすよりも、顧客が完食できる内容にするほうが、結果的にロス削減につながります。
さらに、店舗スタッフによる量の提案も効果的。
オーダー時の一言が、ロスの防止につながることも少なくありません。

メニュー見直しで食品ロスを削減する方法
来店予測とメニュー構成の連動
来店数に波があると、仕込み量の過不足が発生しやすくなります。
過去の来店データや天候、曜日、イベントなどをもとにした来店予測を行い、それに合わせてメニュー構成を調整することで、不要な仕入れや食材の廃棄を防ぐことが可能です。
特にランチタイムとディナータイムで人気のメニューが異なる場合、それぞれの時間帯に合った食材準備が重要になります。
予測に基づく柔軟な対応が、安定した運営につながります。
インセンティブ制度の導入
食品ロス削減をお客様と共有する手段として、インセンティブ制度が効果を発揮します。
完食したお客様に対して次回割引を提供する、スタンプカードを進呈するなど、小さな工夫が顧客の意識を変えるきっかけになります。
これにより、量を調整した注文や完食への意識向上が期待でき、食べ残しの削減へとつながります。
店舗としても、無理なく顧客と一緒に食品ロスに取り組む姿勢をアピールできます。
フードシェアリングサービスの活用
余った料理や未使用の食材を廃棄せず、外部と共有する方法としてフードシェアリングサービスの活用があります。
特に、当日中に消費可能なメニューを割安で販売できるプラットフォームを使えば、食品の無駄を減らしながら売上の補填も可能になります。
食材や料理を「捨てずに生かす」選択肢を持つことが、食品ロス削減への一歩となります。
ただし、メニュー構成と連動させ、無理のない範囲で取り入れることが大切です。

まとめ
食品ロスは飲食店の利益や信頼に直結する課題です。
食材の管理と仕入れを最適化し、メニュー内容を見直すことで、日々の無駄を抑えることができます。
顧客のニーズに応じた量や構成を工夫することも、ロスの削減につながります。
さらに、来店予測やインセンティブ制度、外部サービスの活用など、多角的な視点での対応が効果的です。
継続的な取り組みが、店舗全体の持続性と競争力の向上にもつながります。