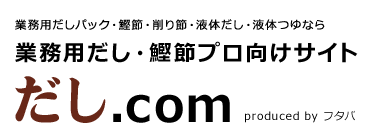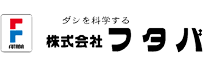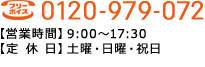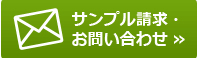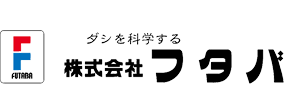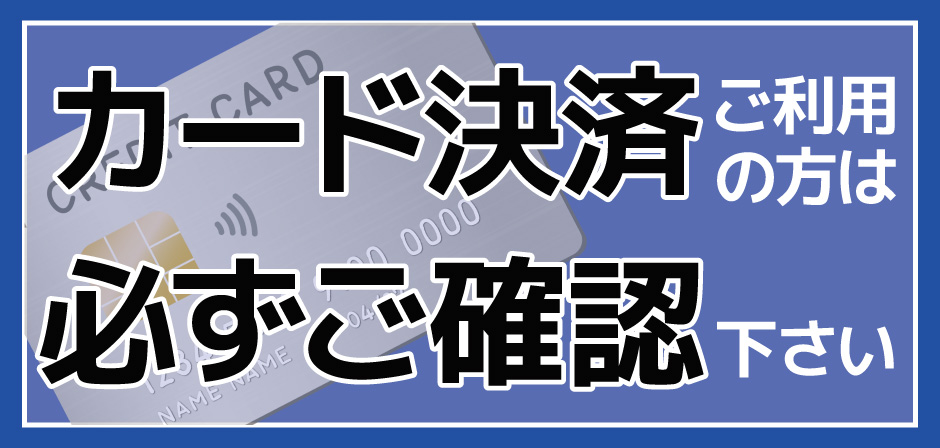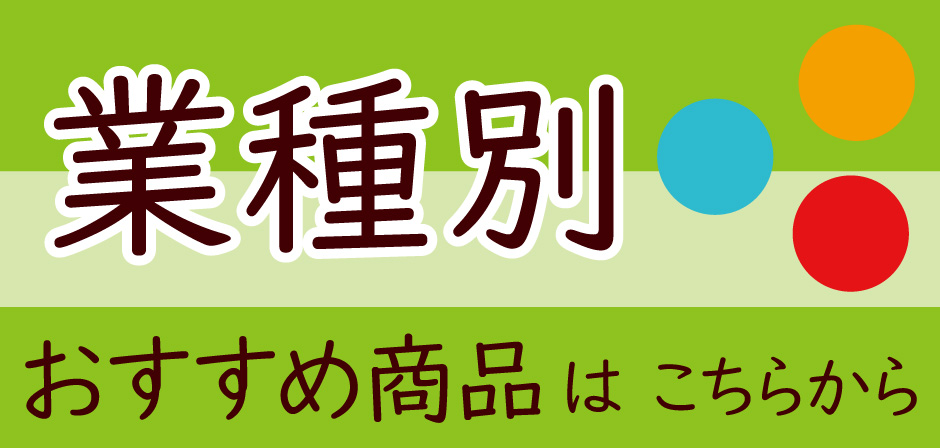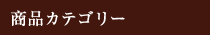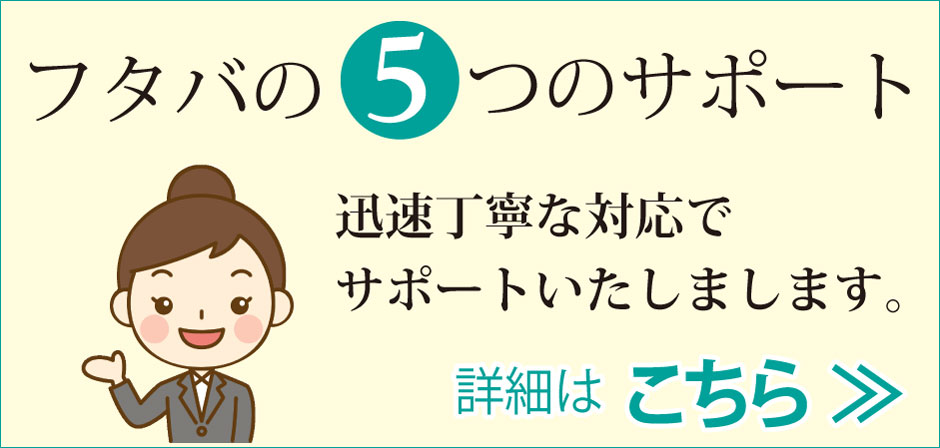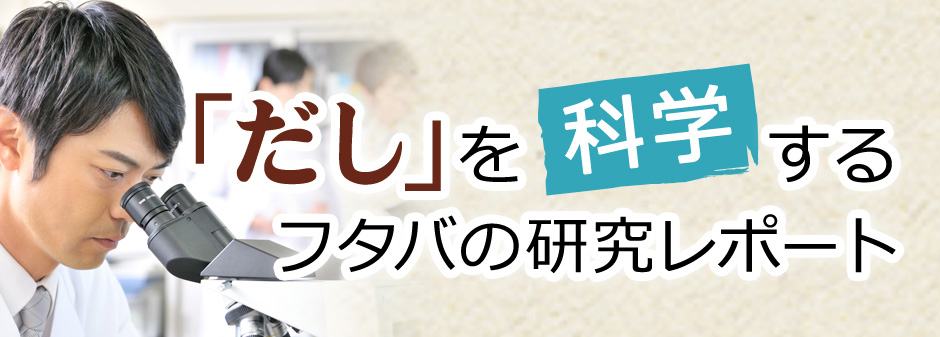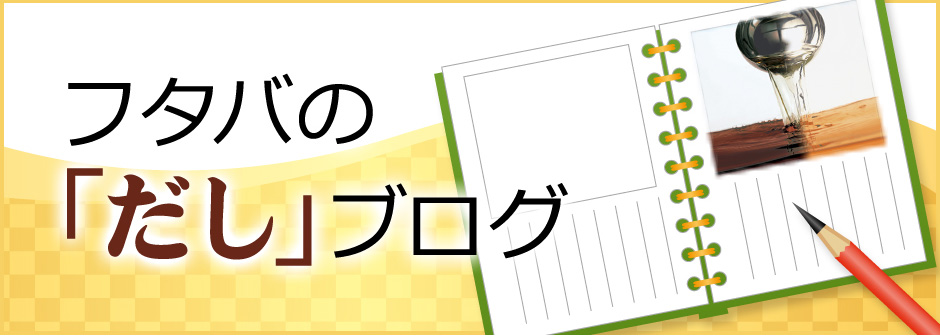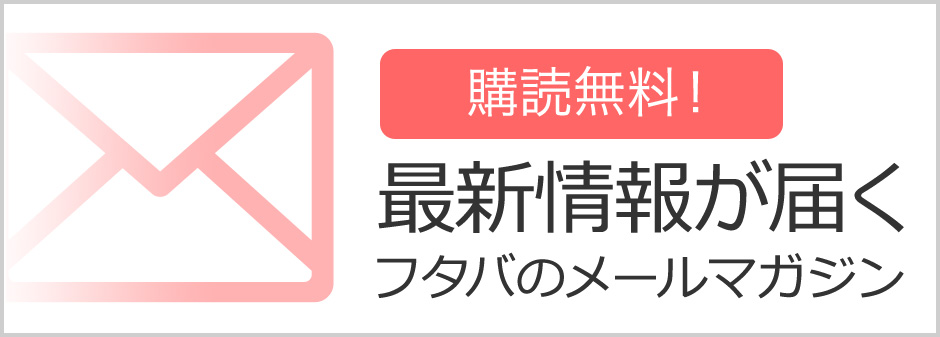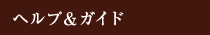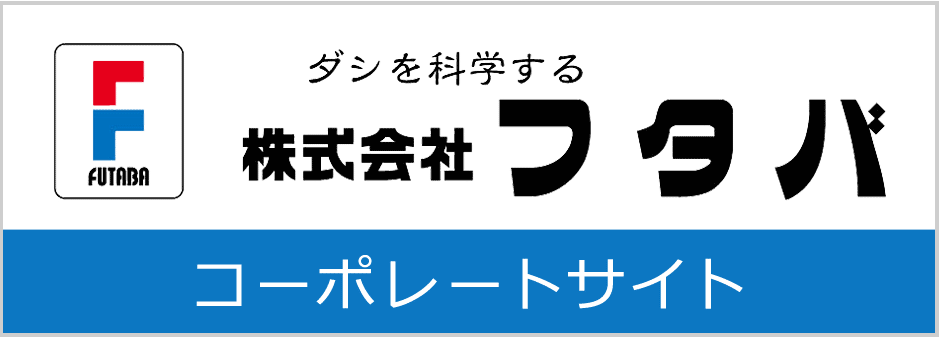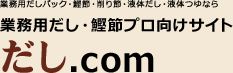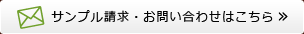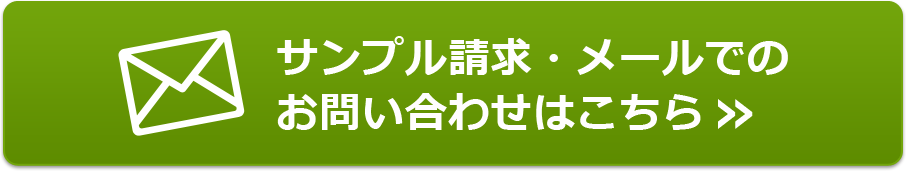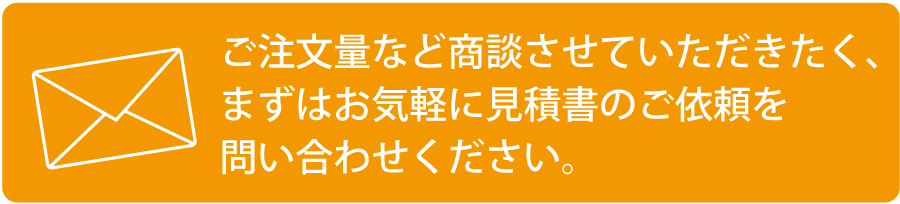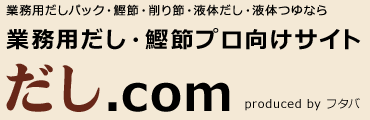- 2025.07.16 飲食店におけるメニュー価格設定の基本とは?
- 2025.07.14 飲食店の食品ロス対策とは?適切なメニュー構成を提案
- 2025.07.11 飲食店の原価率を下げる方法を解説
- 2025.07.09 飲食店向け時間のかかる料理ランキングTOP7!効率化への近道
- 2025.07.04 うま味の世界的人気とその背景を探る
- 2025.07.02 精進出汁の応用とは?可能性を広げるレシピアイデア集
- 2025.06.30 ヴィーガンの出汁の選び方と料理への応用と差別化戦略
- 2025.06.27 ヴィーガンの日本食とは?選び方や楽しみ方から文化的な側面まで様々な反応
- 2025.06.25 水出し出汁で健康的な食生活を!栄養素と効果的な摂り方
- 2025.06.23 高単価メニューのだし素材活用法とプロの技
飲食店を運営する中で、メニューの価格設定は利益に直結する重要な要素です。
しかし、感覚に頼った価格設定では収益が安定しづらく、結果として経営を圧迫してしまうこともあります。
では、どのように価格を設定すれば、適切に利益を確保できるのでしょうか。
本記事では、飲食店のメニュー価格設定に必要な基本的な知識から、実際の設定手法までを紹介します。
価格設定に迷ったときの指針として活用できる内容です。
飲食店メニューの価格設定に必要な基本知識
原価率・FLR比率・FD比率とは何か
メニュー価格を決める際にまず押さえておきたいのが「原価率」です。
一般的に、飲食店の原価率は25〜35%が目安とされます。原価率が高すぎると利益が圧迫され、低すぎると品質への不信感を招きかねません。
次に「FLR比率(Food・Labor・Rent)」ですが、これは食材費・人件費・家賃を足したコストが売上の何割かを示すもので、理想は70%以下。
これを超えると利益の確保が難しくなります。
また「FD比率(Food・Drink)」もメニュー構成に影響します。
利益率の高いドリンクを上手く組み合わせることが、全体の収益改善につながります。
客単価の目安と売上シミュレーションの考え方
メニュー価格は、想定される客単価に大きく影響されます。
客単価は「売上 ÷ 来店人数」で求められ、自店の席数や回転数、客層に合わせて現実的な水準を設定することが大切です。
例えば、1日50人の来店で客単価1,000円なら、売上は5万円。
ここから逆算して、FLR比率を守りつつ、どの価格帯のメニューをいくつ揃えるかを考えると、現実的な価格戦略が見えてきます。
利益確保に向けた価格設定のポイント
利益を意識した価格設定では、利益率の高いメニューを主力に据えたり、トッピングやセットメニューで付加価値を加える工夫が求められます。
また、価格帯を3段階程度に分けると、選ばれやすい中間価格帯の商品に収益を集中させることができます。
さらに、仕入れ価格の変動を定期的に見直し、原価率を再計算することも重要です。
継続的な微調整が、長期的な利益維持につながります。

実践に活かすメニュー価格設定の考え方
競合店の価格帯と差別化戦略
自店の価格が高すぎると感じられるか、逆に安すぎて不安に思われるかは、周囲の競合店の存在によって左右されます。
競合店の価格やメニュー構成を調査することで、自店の立ち位置を見極めましょう。
差別化を図るには、例えば「専門性」「地産地消」「ボリューム感」など、明確な強みを持たせたうえで価格を設定することが効果的です。
メニュー構成と価格バランスの整え方
価格設定は単品ごとに行うのではなく、全体のメニュー構成とのバランスが重要です。
高価格帯の商品ばかりでは手が出づらくなり、逆に低価格帯ばかりだと利益が取りにくくなります。
利益率の高い商品を中心に、利益の出にくい看板商品や集客商品とのバランスをとることで、全体として安定した利益を目指すことができます。
心理効果を活かした価格表示の工夫
価格には心理的な印象も大きく関係します。
たとえば「980円」と「1,000円」では、たった20円の差でもお得感に差が出ます。
また、価格を端数にする、税込表示にする、価格帯を並べる順序を工夫するなど、細かな工夫で注文数が変わることもあります。
こうした心理効果をうまく活かすことで、実際の価格以上の満足感を提供しやすくなります。

まとめ
メニュー価格設定は、感覚や経験だけに頼らず、数字と論理に基づいた判断が必要です。
原価率やFLR比率などの基本指標を理解したうえで、客単価や売上のシミュレーションを行い、利益が見込める価格帯を検討しましょう。
また、競合分析や心理効果の活用も有効です。
価格は一度決めて終わりではなく、定期的な見直しが求められる要素でもあります。
安定した収益を確保するために、価格設定の見直しを習慣化することが鍵です。