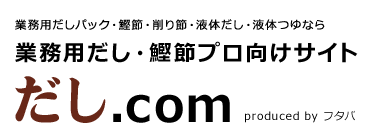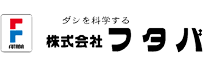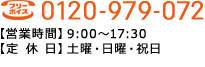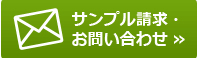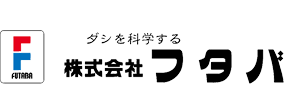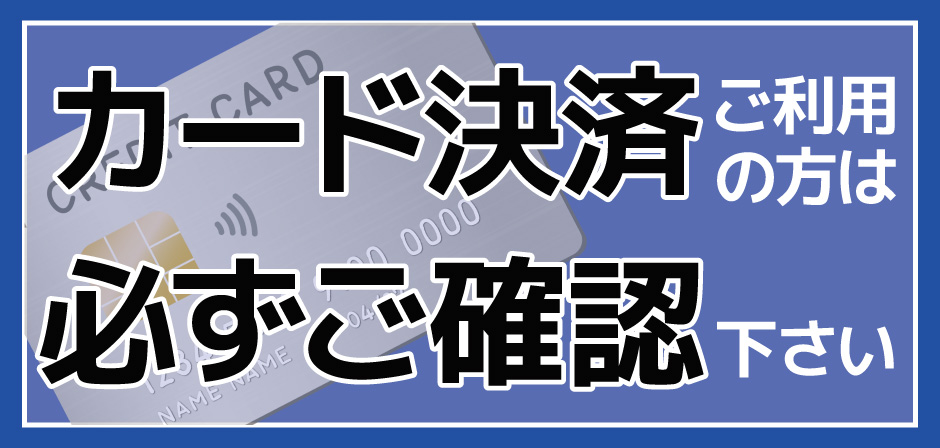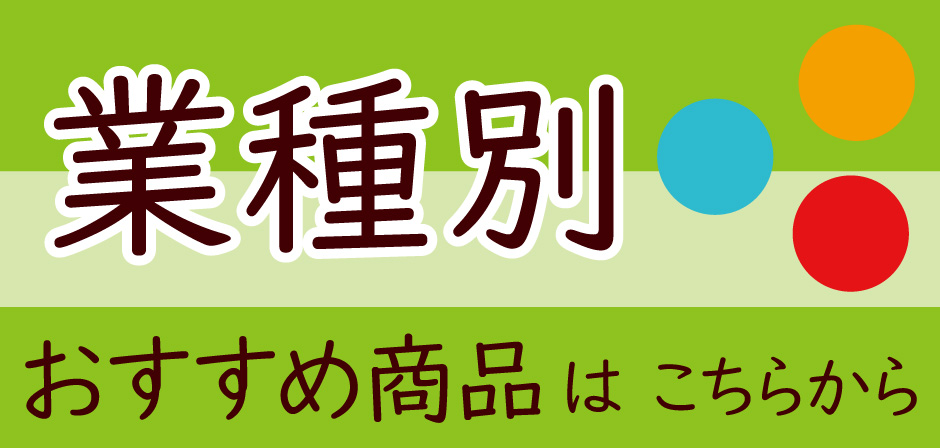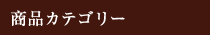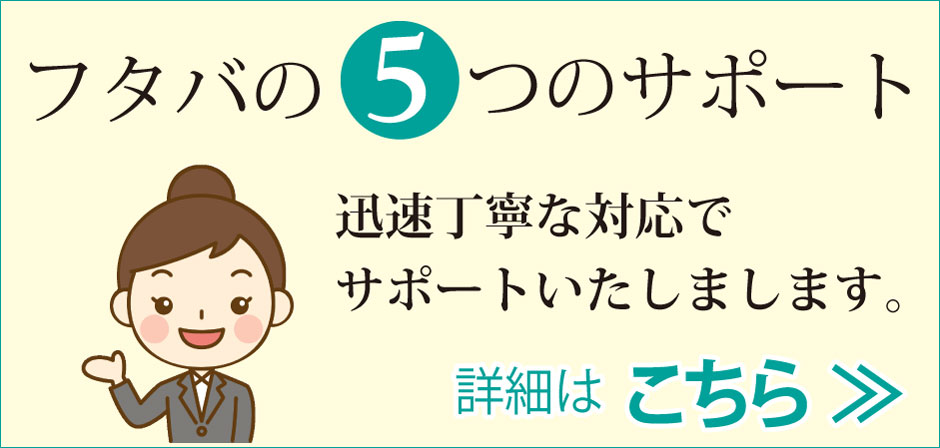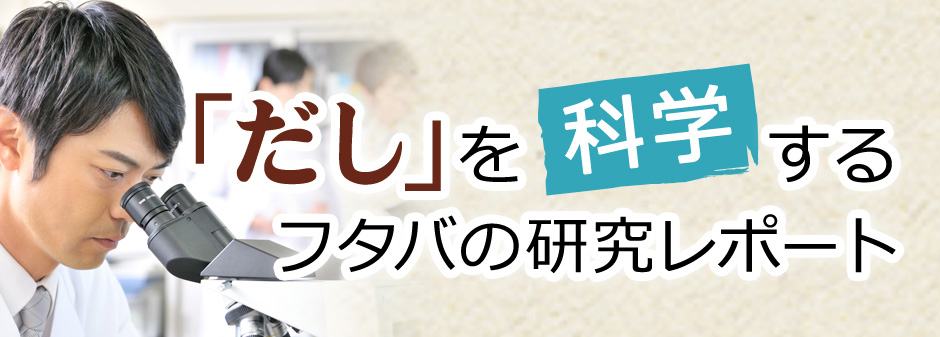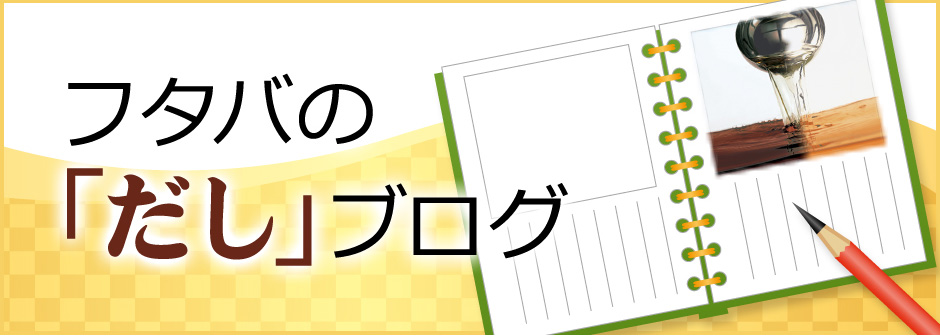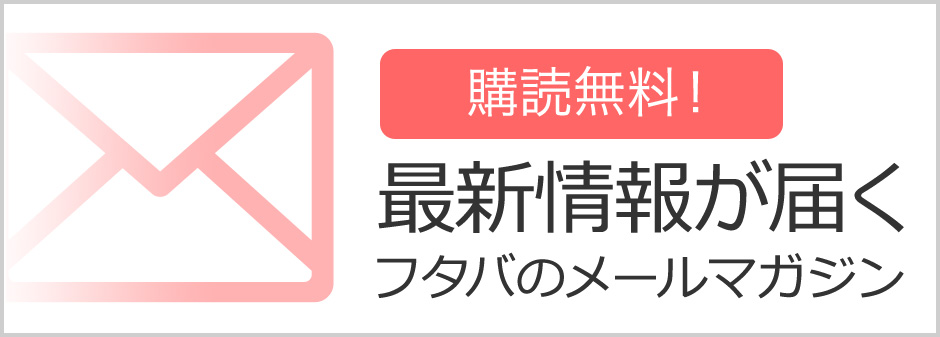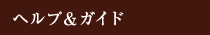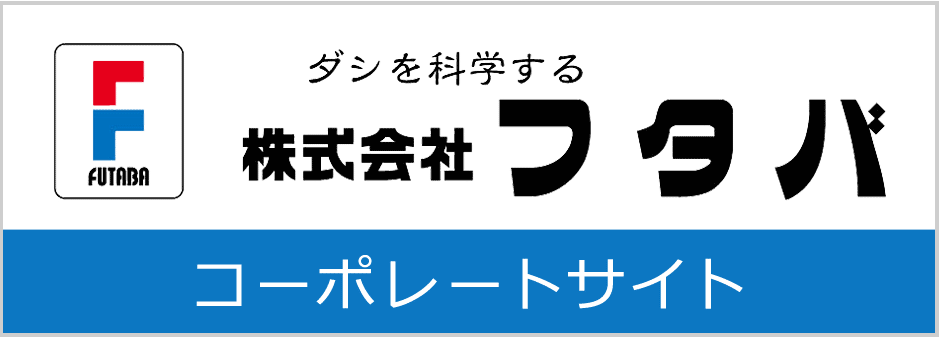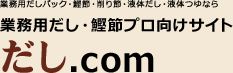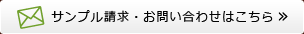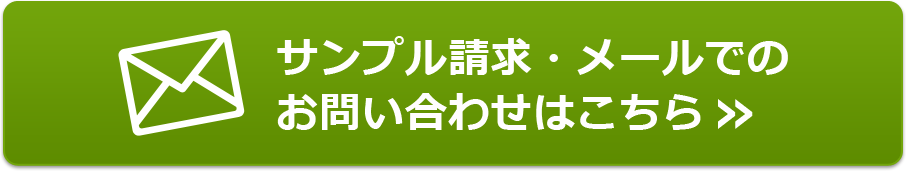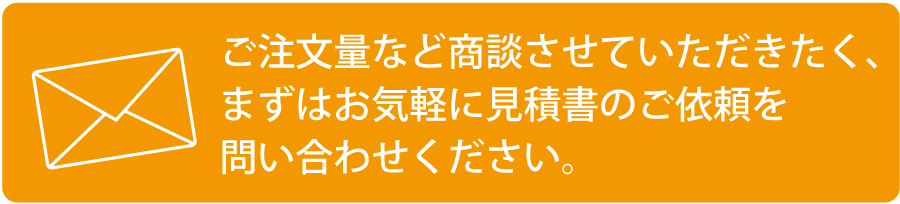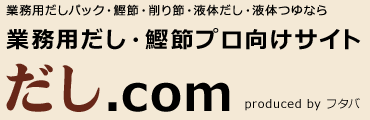ヴィーガン食は、動物性食品を一切摂取しない食事法です。
近年、健康志向の高まりや環境問題への関心の高まりから、ヴィーガン食を実践する人が増えています。
ヴィーガン食は、肉や魚、乳製品、卵などを食べないため、どうしても不足しがちな栄養素があります。
特に、糖尿病の人は、ヴィーガン食を始める前に、十分な知識と注意が必要です。
この記事では、ヴィーガン食と糖尿病の関係について、解説していきます。
ヴィーガン食の糖尿病に対する効果は?
ヴィーガン食は、糖尿病の改善に役立つ可能性があるとされています。
その理由は、ヴィーガン食が持つ以下の特徴にあります。
1:血糖値の上昇を抑える効果
ヴィーガン食は、動物性食品に比べて食物繊維が豊富です。
食物繊維は、消化がゆっくり進むため、血糖値の急上昇を抑える効果があります。
また、ヴィーガン食には、血糖値の上昇を抑える効果があると言われているα-リノレン酸や、インスリン感受性を高める効果があると言われているクロムなどのミネラルも豊富に含まれています。
2:インスリン抵抗性を改善する効果
インスリン抵抗性は、インスリンが正常に働かなくなり、血糖値がなかなか下がらない状態です。
ヴィーガン食は、低脂肪で食物繊維が豊富であるため、体重管理に役立ちます。
肥満はインスリン抵抗性の大きな原因の一つであるため、ヴィーガン食による体重管理は、インスリン抵抗性の改善につながる可能性があります。
3:炎症を抑える効果
ヴィーガン食には、抗酸化作用のあるポリフェノールやビタミンなどが豊富に含まれています。
これらの成分は、体内の炎症を抑える効果があり、インスリン感受性を改善する効果も期待できます。
ヴィーガン食は、血糖値の上昇を抑え、インスリン抵抗性を改善する効果が期待できるため、糖尿病の改善に役立つ可能性があります。
ヴィーガン食における注意点
ヴィーガン食は、栄養バランスを意識しないと、様々な栄養素が不足する可能性があります。
特に、糖尿病の人は、不足しがちな栄養素を補う食事を心がけることが重要です。
1:タンパク質不足
ヴィーガン食では、タンパク質を多く含む肉や魚を摂取しないため、タンパク質不足に陥りやすいです。
タンパク質は、筋肉や臓器、ホルモンなどの重要な構成成分です。
不足すると、筋肉量が減り、体力低下や免疫力低下につながる可能性があります。
2:鉄分不足
鉄分は、血液中のヘモグロビンを作るために必要なミネラルです。
鉄分が不足すると、貧血になることがあります。
ヴィーガン食では、ヘム鉄と呼ばれる吸収率の高い鉄分が少なく、非ヘム鉄と呼ばれる吸収率の低い鉄分しか摂取できません。
そのため、鉄分不足になるリスクが高いです。
3:亜鉛不足
亜鉛は、免疫機能や味覚、皮膚の健康維持に重要なミネラルです。
ヴィーガン食では、亜鉛を多く含む肉や魚を摂取しないため、亜鉛不足になる可能性があります。
4:カルシウム不足
カルシウムは、骨や歯の健康維持に重要なミネラルです。
ヴィーガン食では、カルシウムを多く含む乳製品を摂取しないため、カルシウム不足になる可能性があります。
5:ビタミンB12不足
ビタミンB12は、神経細胞の働きや赤血球の生成に重要なビタミンです。
ヴィーガン食では、ビタミンB12を多く含む動物性食品を摂取しないため、ビタミンB12不足になる可能性があります。
ヴィーガン食では、上記の栄養素が不足しやすいので、意識して摂取するようにしましょう。
まとめ
ヴィーガン食は、糖尿病の改善に役立つ可能性がある一方で、栄養バランスを意識しないと、様々な栄養素が不足する可能性があります。
糖尿病の人は、ヴィーガン食を始める前に、医師や管理栄養士に相談し、適切な食事指導を受けることが大切です。
ヴィーガン食を実践する際は、不足しがちな栄養素を補う食事を心がけ、健康的にヴィーガンライフを送りましょう。