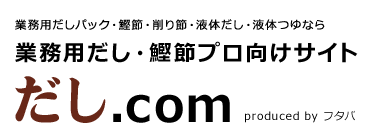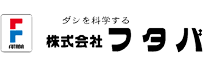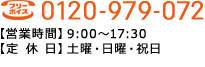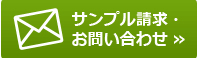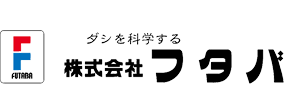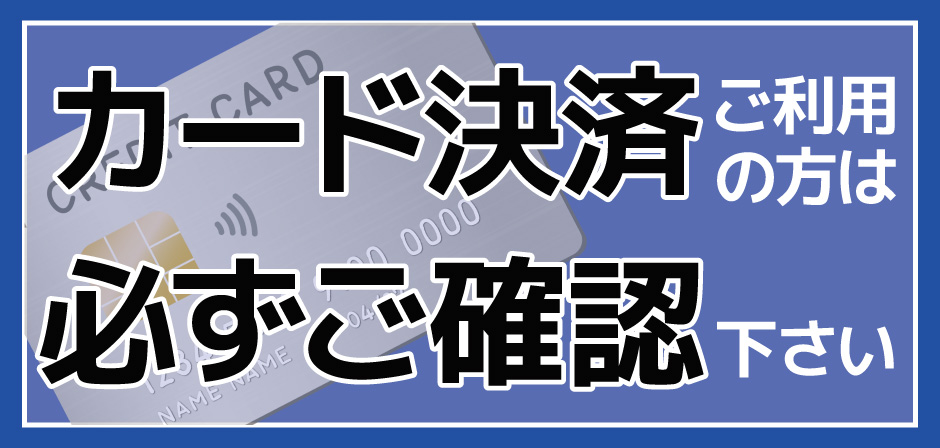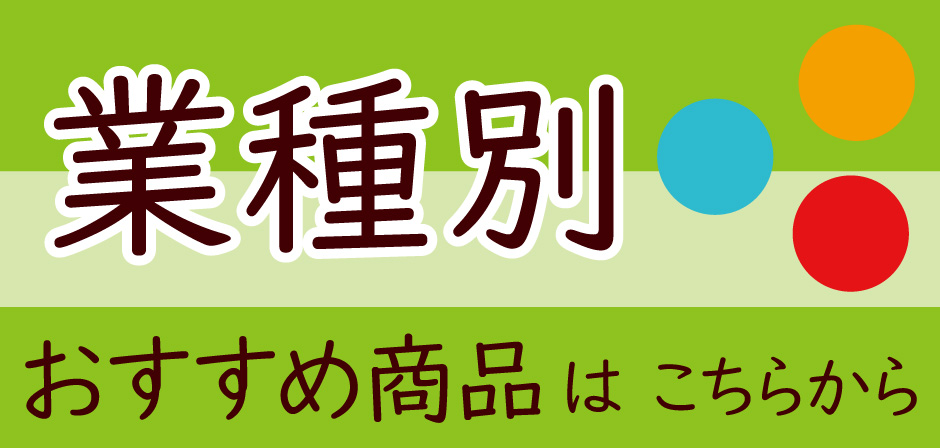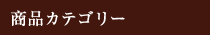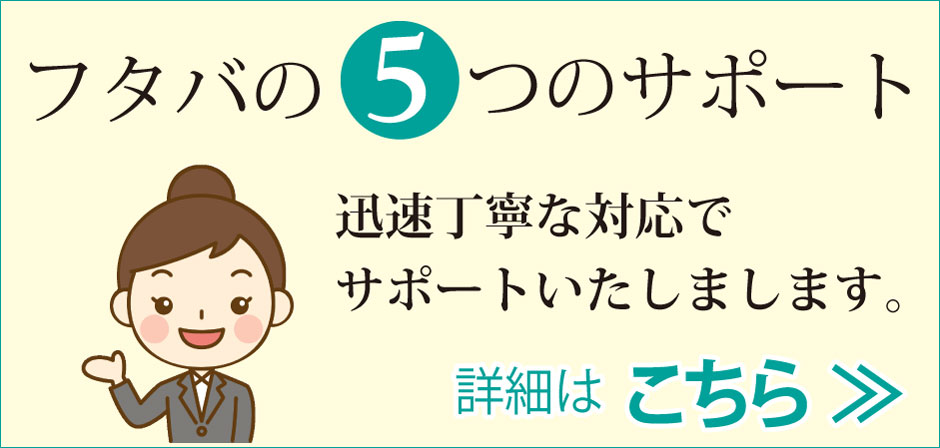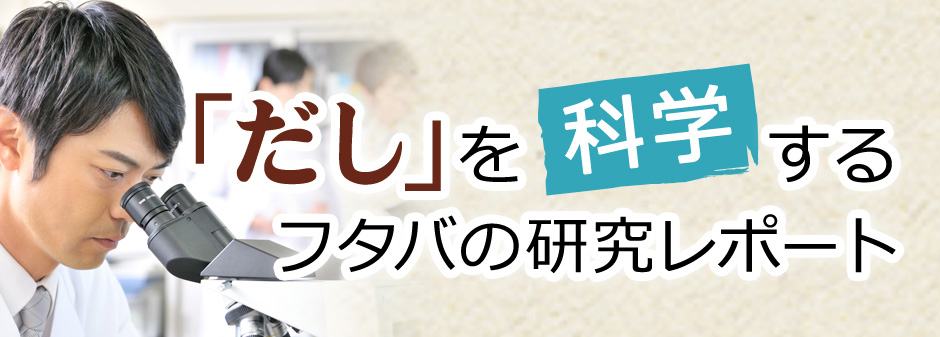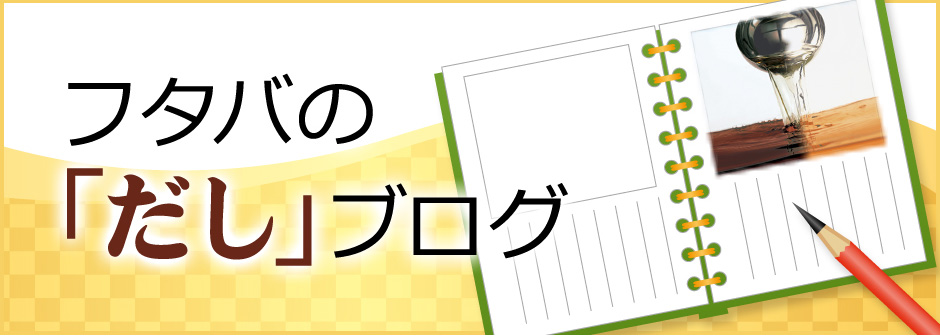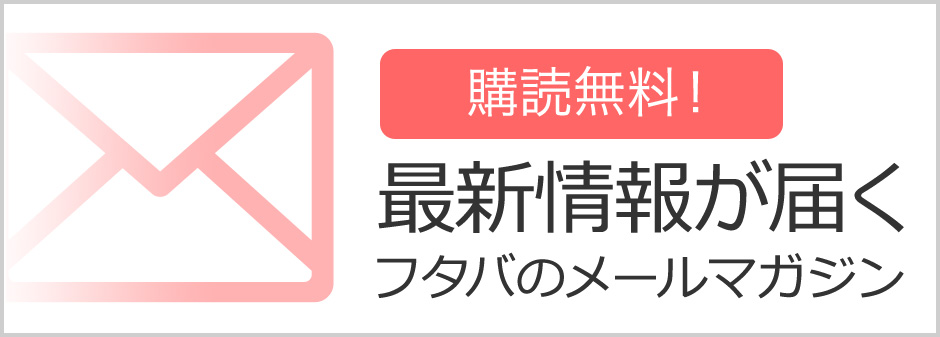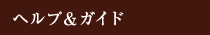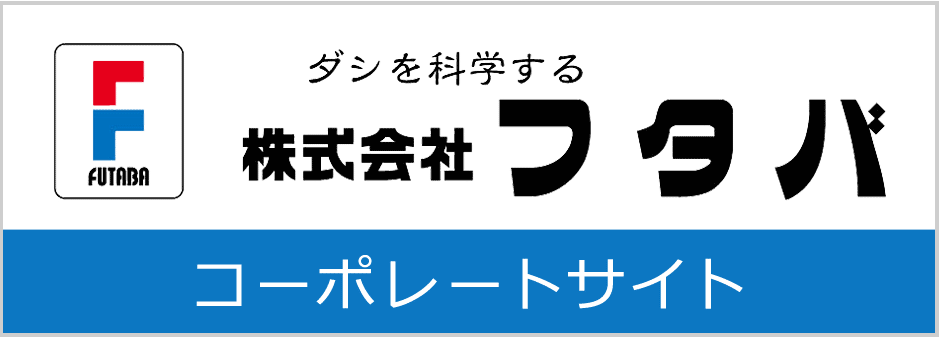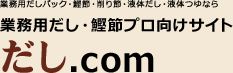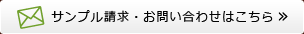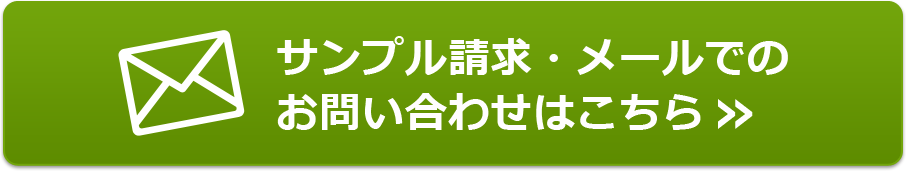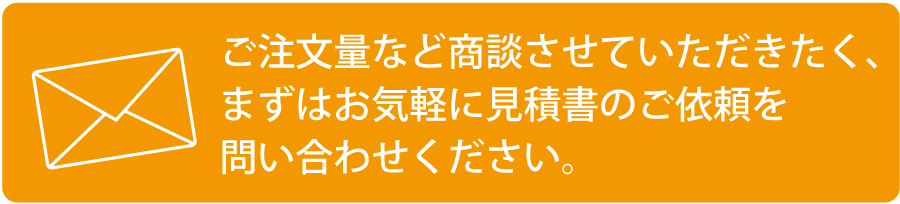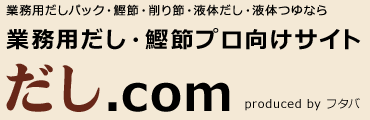動物性不使用とは何なのか?
今回は、動物性不使用の食事「ビーガン」について、その概念やメリット、選び方のポイントを解説します。
実践的な知識を紹介することで、皆さんが安心してビーガン食を取り入れられるようにサポートします。
□動物性不使用とは?ビーガン食の基礎知識
動物性不使用の食事「ビーガン」は、環境や動物保護を目的として、動物性の食品や製品を避けるライフスタイルです。
1900年代のイギリスで生まれたこの考え方は、近年、世界中で注目を集めています。
1: ビーガンとは
ビーガンは、肉や魚、卵、乳製品など、動物から得られるあらゆるものを食べません。
完全菜食主義とも呼ばれ、ベジタリアンの中でも最も厳格な食事スタイルと言えるでしょう。
2: ベジタリアンとの違い
ベジタリアンは、肉を食べない人を指しますが、その中には魚や卵、乳製品を食べる人もいます。
ビーガンは、動物性食品を一切口にしない点が、ベジタリアンとの大きな違いです。
3: エシカル・ヴィーガン
ビーガンは食事だけでなく、衣食住においても動物性の製品を使わない「エシカル・ヴィーガン」という考え方もあります。
例えば、動物の皮や羽毛を使った製品を買わない、コスメは植物由来のものを使用するなど、日常生活における倫理的な選択を重視するスタイルです。
4: ハラル食との違い
ハラル食は、イスラム教の教えに基づいた食生活です。
豚肉やアルコールなど、イスラム教で禁じられているものは食べません。
ビーガンは、動物福祉や環境保護という倫理的な理由に基づいた食生活であるのに対し、ハラル食は宗教的な理由に基づいた食生活です。
□ビーガン食を取り入れるメリット
1: 動物福祉への配慮
家畜は、食肉や乳製品、卵などのために飼育されています。
しかし、多くの家畜は狭いケージの中で飼育され、自由に動き回ることや自然な行動をとることができません。
また、卵を産むための鶏のオスは、産卵能力がないことから、孵化後すぐに処分されるという残酷な現実もあります。
2: 環境保護への意識
畜産業は、温室効果ガスの排出源として大きな問題となっています。
家畜の飼育や糞尿の処理などによって、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが排出され、地球温暖化を加速させています。
また、家畜の餌となる穀物の生産には、多くの水や土地が必要となり、森林伐採や水資源の枯渇につながることもあります。
ビーガン食は、畜産業による環境負荷を軽減し、地球環境を守るために有効な手段と言えます。
3: 多様性への対応
アレルギーや宗教上の理由で、特定の食品を制限する必要がある人もいます。
ビーガン食は、卵や乳製品、肉など、さまざまなアレルギーに対応できる食事スタイルです。
また、宗教上の理由で豚肉やアルコールを避ける必要がある人にとっても、ビーガン食は選択肢の一つとなります。
□まとめ
ビーガン食は、動物福祉や環境保護、そして私たちの健康にも多くのメリットをもたらす食生活です。
ビーガン食は、単なる食事制限ではなく、動物や地球環境に対する倫理的な責任を果たすライフスタイルです。