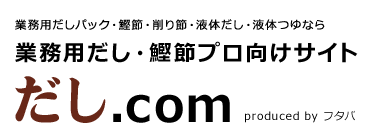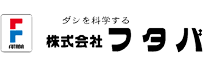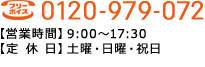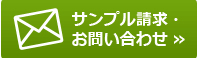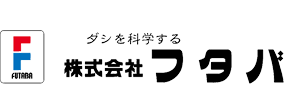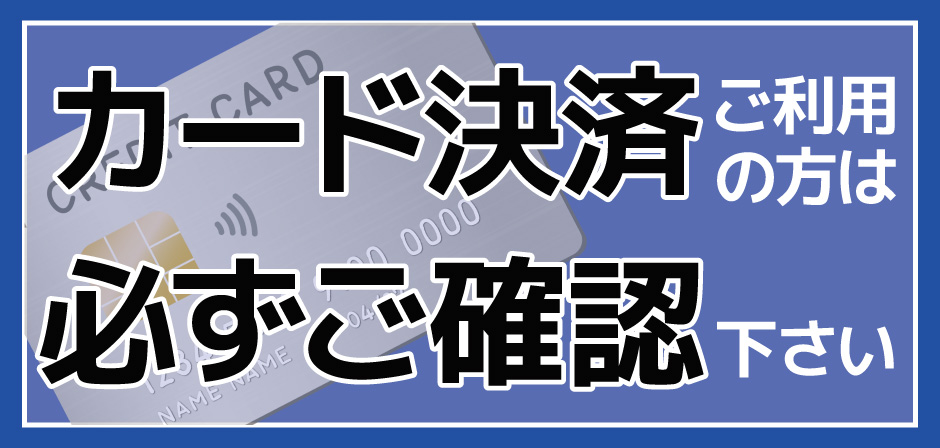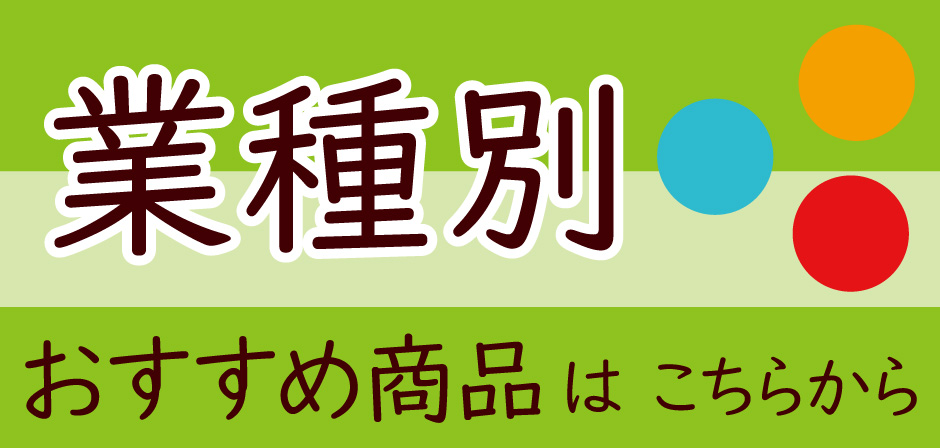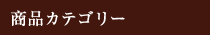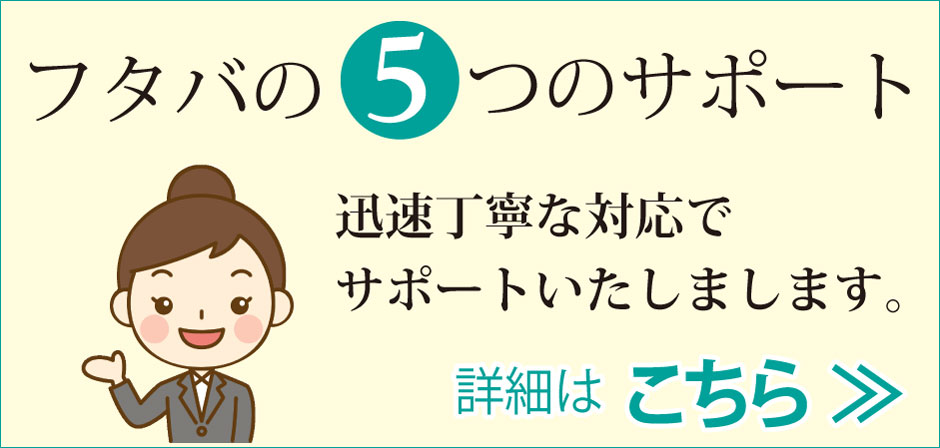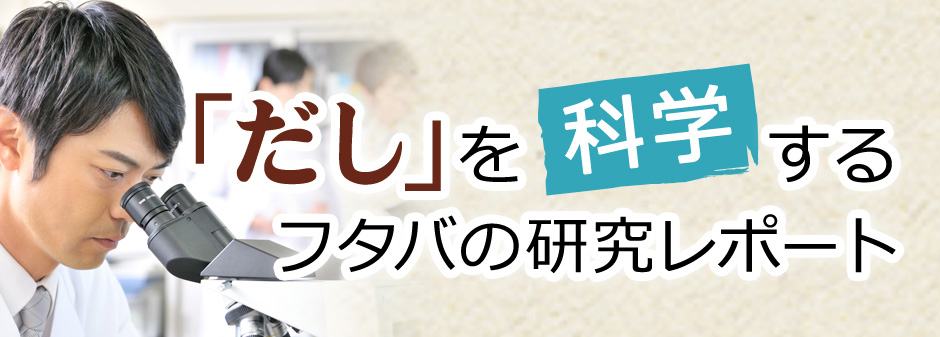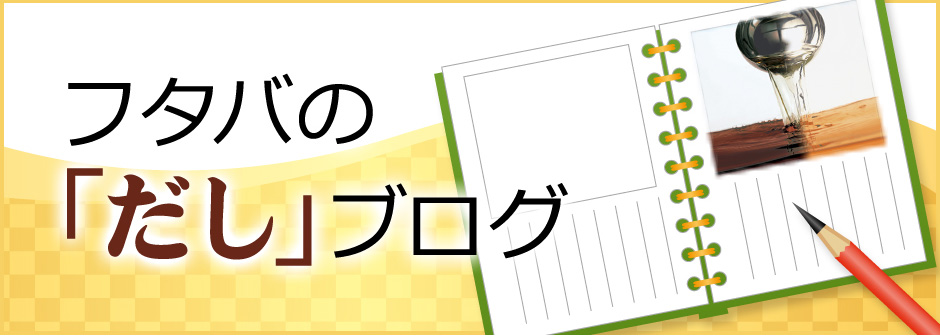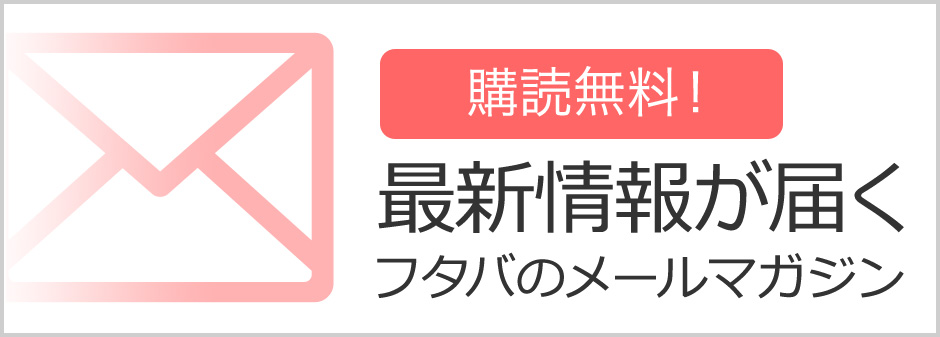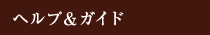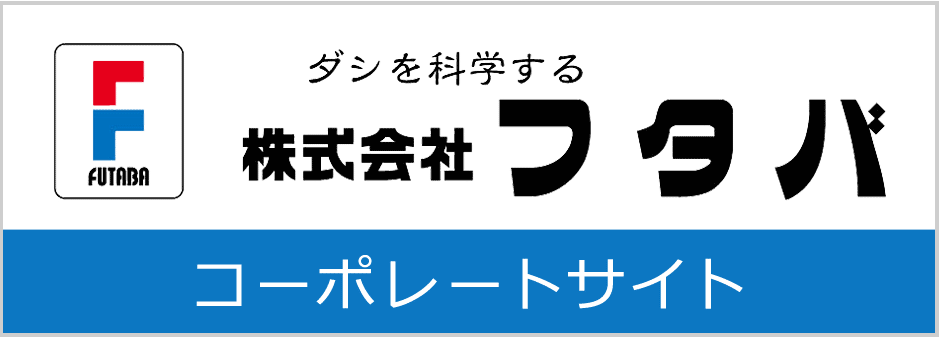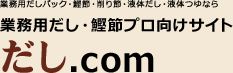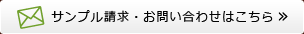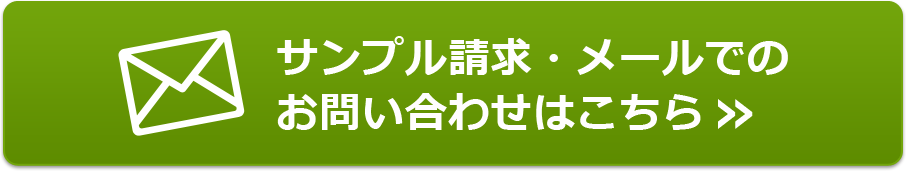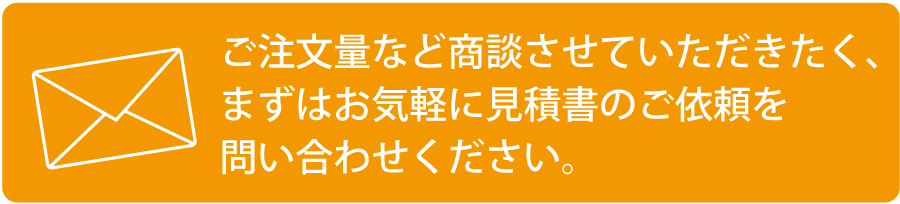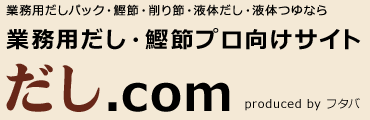- 2026.02.02 飲食店の回転率を上げるには?オペレーション改善と最新テクノロジー活用法
- 2026.01.30 「出汁を取る」と「出汁を引く」の違いとは?うま味を引き出すそれぞれの方法を解説
- 2026.01.28 一番だしと二番だしは何が違う?料理での使い分けポイントを解説
- 2026.01.26 鍋つゆの原価率を改善する秘訣とは?コスト削減とサプライチェーン連携のポイント
- 2026.01.23 業務用だしを常温保存する?種類と注意点とは
- 2026.01.21 三番だしとは?旨味や香りが乏しい出汁は何に使うのか
- 2026.01.19 二番だしは何に使う?一番だしのだしがらで作る濃厚な旨味の活用法
- 2026.01.16 セントラルキッチンでの出汁の作り方とは?店舗との違いも解説
- 2026.01.14 業務用スープベースのだしで叶える!本格洋食とは
- 2026.01.12 業務用だしの濃度調整方法とは?旨味と塩味のバランスを整えるコツ
多くの飲食店にとって、限られた時間と空間で、より多くのお客様に満足していただくことは、経営の根幹に関わる重要なテーマです。
来店されたお客様に快適な時間を過ごしていただきつつ、店舗の活気を高めるためには、どのような工夫が考えられるでしょうか。
スムーズなサービス提供と、お客様の満足度を両立させるための具体的なアプローチを見ていきましょう。
飲食店回転率を上げるには
オペレーション効率化で時間短縮
店舗運営におけるオペレーションの効率化は、客席回転率向上のための基本となります。
オーダー受付から料理の提供、そしてテーブルの片付け(バッシング)に至るまで、各工程の時間を短縮することが重要です。
例えば、スタッフのスキルアップや作業手順の見直し、厨房とホールの連携強化などが挙げられます。
また、食事の途中で不要な食器を片付ける中間バッシングを徹底することで、次のお客様へのスムーズな案内とテーブルセッティングが可能になります。
メニュー工夫で注文スムーズに
お客様がメニューを決めるまでの時間を短縮することも、回転率向上に効果的です。
メニュー数を絞り込んだり、写真やイラストを豊富に使い、料理のイメージが湧きやすいように工夫したりすることが有効です。
また、席に着く前や、席に着いてすぐにメニューを把握できるよう工夫することで、注文までのリードタイムを短縮できます。
席の有効活用で機会損失減
限られた座席を最大限に活用することも、機会損失を減らす上で重要です。
少人数のお客様には、よりコンパクトな席へ案内したり、混雑時には相席をお願いしたりすることも検討できます。
また、テーブルの配置や、お客様が長居しにくいような空間づくりも、結果として席の回転率を高めることに繋がります。
ただし、顧客満足度を損なわないよう、快適性とのバランスが不可欠です。

回転率向上に役立つテクノロジー
セルフレジ・券売機で会計迅速化
会計プロセスを効率化するテクノロジーの導入も、回転率向上に大きく貢献します。
セルフレジや券売機は、顧客自身が注文から支払いまでを完結できるため、レジでの待ち時間を大幅に短縮できます。
これにより、スタッフの負担軽減にも繋がり、次のお客様への対応が迅速に行えます。
オンラインオーダーで事前注文促進
オンラインオーダーシステムを活用することで、顧客は来店前にスマートフォンなどから注文を完了できます。
これにより、店舗到着後の注文待ちや料理提供までの時間を削減でき、スムーズな来店・退店を促すことが可能です。
特に混雑時においては、顧客体験の向上と回転率の向上を同時に実現できます。
配膳ロボでサービス効率向上
配膳ロボットの導入は、店舗のサービス効率を一層向上させます。
料理の配膳や使用済み食器の下げ膳をロボットが担当することで、スタッフはより顧客とのコミュニケーションや、注文受付、案内といったコア業務に集中できるようになります。
これにより、店舗全体のオペレーションが円滑になり、結果として客席の回転率向上に繋がります。

まとめ
飲食店が売上を伸ばすためには、客席回転率の向上が不可欠です。
そのためには、日々のオペレーションの見直し、メニューや席の工夫によるスムーズな顧客誘導、そしてセルフレジやオンラインオーダー、配膳ロボといったテクノロジーの活用が有効な手段となります。
これらの施策をバランス良く実施し、顧客満足度を維持・向上させながら、効率的な店舗運営を目指していくことが、持続的な成長に繋がるでしょう。