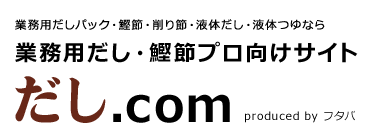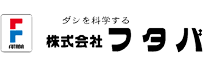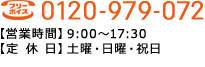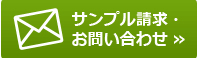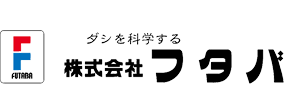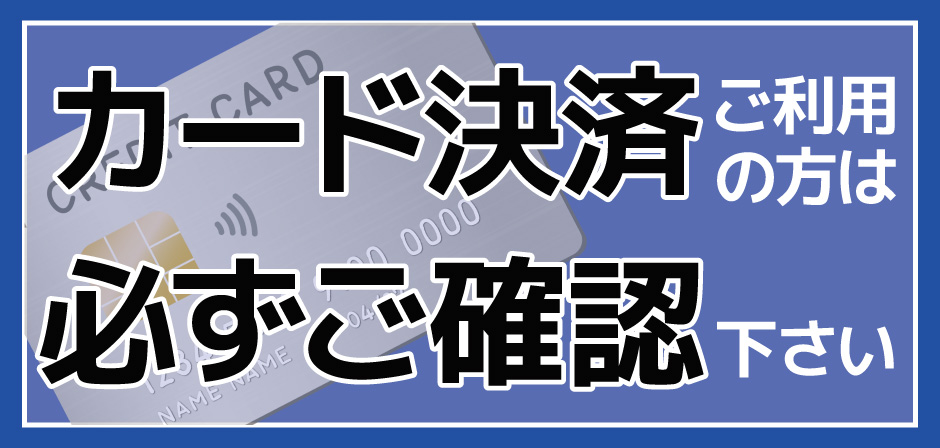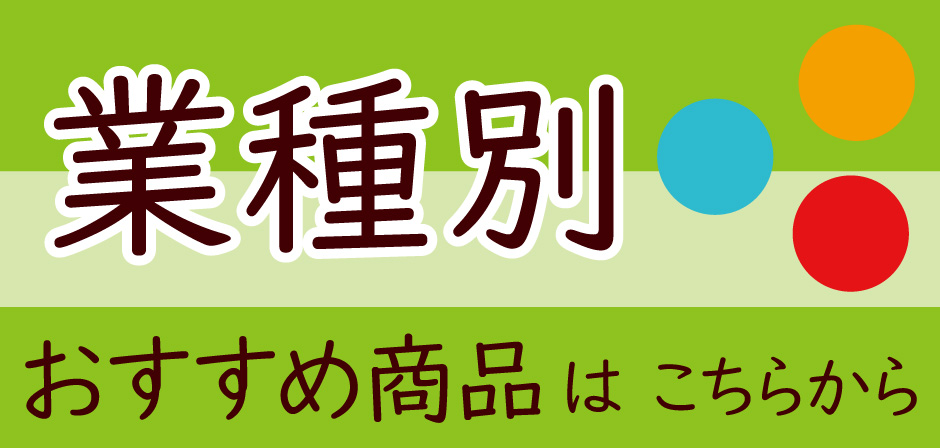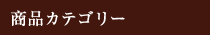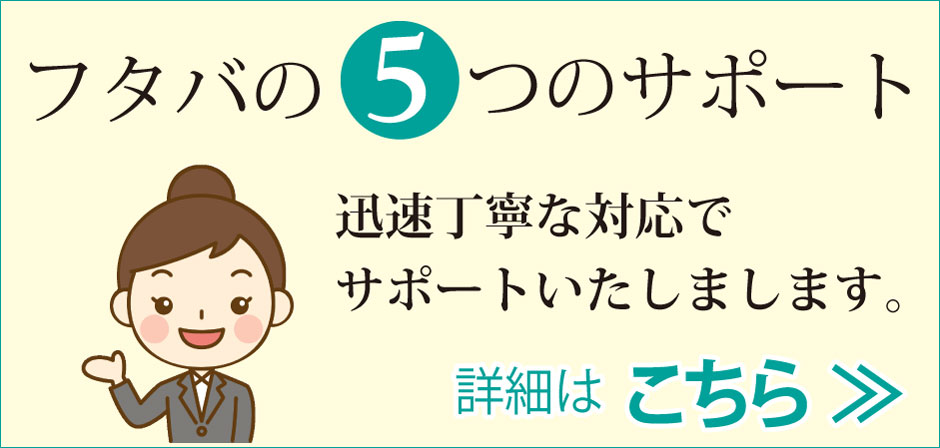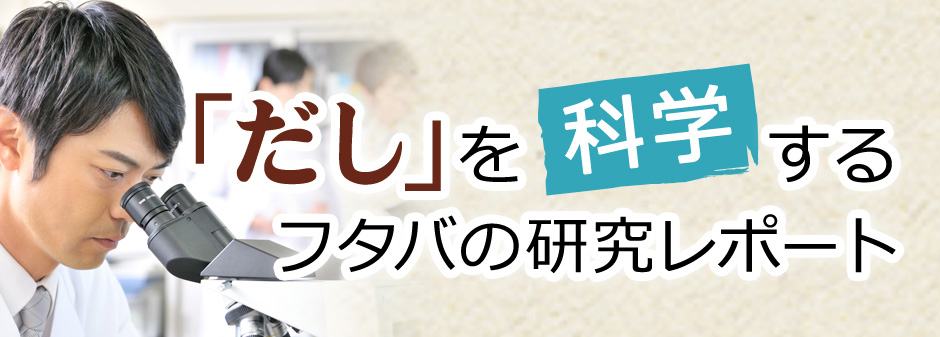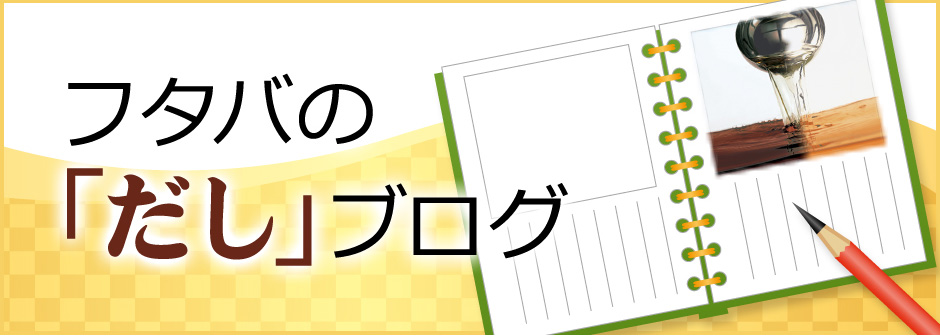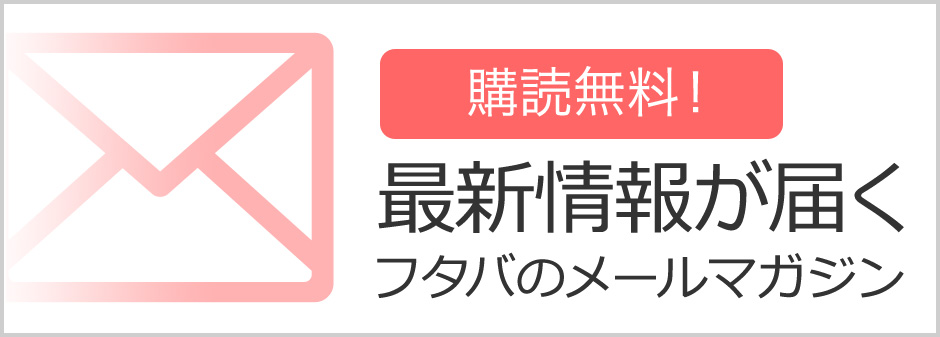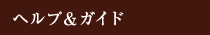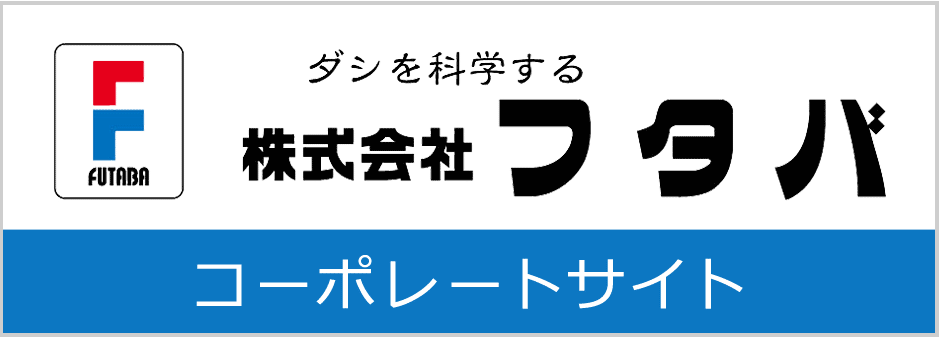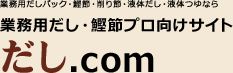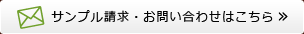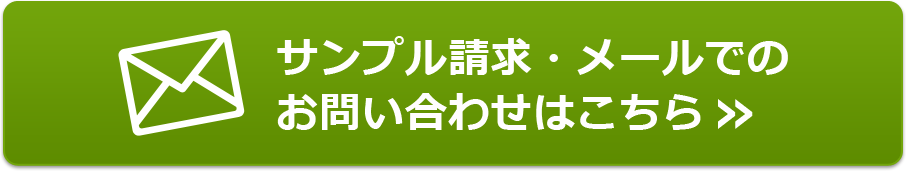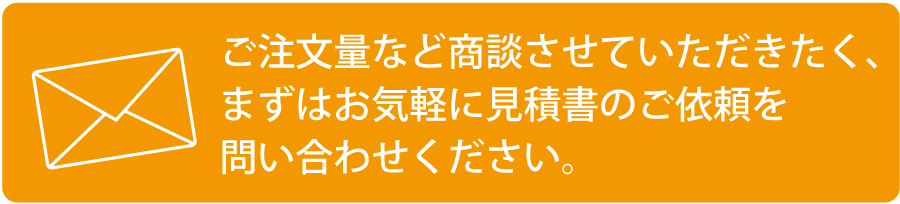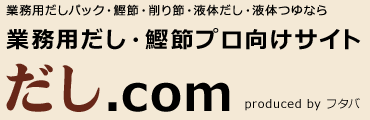- 2026.02.20 飲食店が業務用ほたてだしを活用する理由とは?
- 2026.02.18 飲食店で酒蒸しのだしを強化する理由とは?旨味やコクを増す方法
- 2026.02.16 飲食店で旨味と奥行きを出す方法とは?香味野菜や発酵調味料でコクを深めるコツ
- 2026.02.13 業務効率アップ!使いやすい業務用液体だしの選び方とは
- 2026.02.11 うま味の相乗効果とは?料理のコクが深まる具体例を解説
- 2026.02.09 海外客向けだし事情とインバウンド対応のポイントは?食事制限への配慮が鍵
- 2026.02.04 業務用あごだしを使う!高級感を出す方法とは
- 2026.02.02 飲食店の回転率を上げるには?オペレーション改善と最新テクノロジー活用法
- 2026.01.30 「出汁を取る」と「出汁を引く」の違いとは?うま味を引き出すそれぞれの方法を解説
- 2026.01.28 一番だしと二番だしは何が違う?料理での使い分けポイントを解説
料理の味を左右する「だし」。
特に、繊細で豊かな風味を持つほたては、多くの料理に深みを与えてくれます。
近年、ホテルやレストランといったプロの現場で使われてきた高品質な業務用だしが、家庭でも手軽に楽しめるようになりました。
その中でも、ほたての旨味を凝縮しただしは、いつもの食卓を格別なものへと変える可能性を秘めています。
今回は、そんな業務用ほたてだしの魅力と、その活用法についてご紹介します。
飲食店で業務用ほたてだしを活用する理由
プロ向け濃厚旨味を家庭でも再現
かつてはホテルや旅館、飲食店といったプロの現場で主に利用されていた業務用ほたてだしが、今では手軽に購入できるようになりました。
これは、家庭料理の味に深みを加えたい、本格的な味を再現したいという声に応える形で商品化されたものです。
専門的な技術で丁寧に抽出されたほたて本来の濃厚な旨味は、いつもの料理に加えるだけで、まるでプロが作ったかのような格別な味わいをもたらします。
手間をかけずに、家庭でワンランク上の味覚体験ができるのが、業務用ほたてだしの大きな魅力と言えるでしょう。
パスタソースやスープのベースに最適
業務用ほたてだしは、その濃厚な旨味と使いやすさから、様々な料理のベースとして活躍します。
特にパスタソースやスープにおいては、その真価を発揮します。
例えば、クリームパスタや魚介系のソースに少量加えるだけで、ほたての豊かな風味が全体に広がり、奥行きのある味わいに仕上がります。
また、コンソメスープやポタージュスープにベースとして使えば、素材の繊細な甘みとコクが加わり、格別な一杯へと格上げされます。
炒め物や煮物、リゾットなど、和洋中を問わず幅広い料理に応用できる万能調味料としても重宝します。

ほたてだしで飲食店メニューを格上げ
国産ほたてをまるごと使用した贅沢なうまみ
飲食店で使われる業務用ほたてだしは、素材選びからこだわり抜かれています。
特に、上質な国産ほたてをまるごと使用し、その旨味を余すところなく引き出している点が特徴です。
身だけでなく、旨味が凝縮された貝ヒモなども含めて丁寧に抽出されることで、海の幸ならではの芳醇で贅沢なうまみが生まれます。
この素材本来の豊かな風味は、料理に複雑さと深みを与え、他にはない特別な味わいを実現します。
ほたてペーストを使った濃厚だし
業務用ほたてだしの中には、ほたてペーストを活用しただしもあります。
ほたて本来の自然な甘みと旨味を強く強調しており、料理に豊かなコクと深みを加えます。
中華や洋食など、様々な用途に使うことができるだしになっています。

まとめ
業務用ほたてだしは、プロの現場で培われた品質と旨味を手軽に再現できる優れた調味料です。
国産ほたてをまるごと使用した贅沢なうまみと、自社での厳しい原料選定よる安心・安全性が大きな魅力となっています。
パスタソースやスープのベースとしてはもちろん、様々な料理に加えるだけで、いつものメニューを格別なものへと変えてくれるでしょう。
この一杯のだしが、あなたの料理の可能性を広げ、さらなる豊かさをもたらすはずです。